ダボスの飼い犬のエア科学者
6.1 1.5℃目標、アドボカシー
第4章第2節と前章第14節で説明したとおり、環境団体が主導して京都議定書を結ばせた。
それを正当化するために、マイケル・マンらが直ちにホッケー・スティック曲線をでっち上げ、IPCCは第3次報告書で目玉論文として採用した。
前章の冒頭で採り上げている2019年1月27日の朝刊紙面に見えるとおり、パリ協定も環境団体が牛耳っていた。
前章第14節で採り上げた論説が「そのIPCCがパリ協定の発効後の昨年10月にまとめたのが、『1.5度特別報告書』だ」と囃し立てていたとおり、「1.5度特別報告書」もなかったのに、第1部第5章の冒頭で採り上げている2015年12月15日の社説が「それでも、平均気温の上昇を2度未満に抑えるというこれまでの目標だけでなく、『1.5度未満に抑えるよう努める』と明記した意義は大きい」「国土の水没を恐れるツバルなど小さな島国の懸命な訴えを、大国も軽んじられなかったのだ」と喚き立てたのは、環境団体が主導した結果。
第1部第13章第1節で説明したとおり、ツバルの国土面積は増加しているにもかかわらず、「私の国を救えれば、世界が救える」と泣き喚き、第10節で紹介したとおり、我国の潮位にCO2排出に因る変化は認められないにもかかわらず、「最初の被害者は私の母国かもしれないが、次はあなた方だ」と泣き喚いたのは、そして、第2節で説明したとおり、キリバスの土人が「愛の反対とは、憎しみや恨みではなく無知と無関心。関心を持たれないことは一番つらい」と泣き喚き、「助け合えるなら、私の島は沈まない」と泣き喚いたのは、先進国の環境団体が焚きつけたから。
やはり、エア科学者らはその後づけに奔走した。
第1部第13章第8節で解説しているとおり、「パリ協定の発効後の昨年10月にまとめたのが、『1.5度特別報告書』」では、データを改竄・捏造してハイエイタスを消し去り、第9節で解説しているとおり、ホットハウス・アースをでっち上げた。
第9節で採り上げている2019年11月2日の朝刊紙面では、「私たちは10年前から1.5度が境界であると主張してきました」と放言しているけれど、「私たち」とは「環境団体の指示を受けた私たち」。
第4章第1節で解説したとおり、環境団体は国際主義エリートの投資家の資金で活動している。
エア科学者は国際主義エリートの飼い犬であり、環境団体に調教されているわけである。
だから、第4章第6節で説明した「グローバル気候行動サミット」に招かれて登壇した。
(第1部第13章第9節で採り上げている2018年8月2日の朝刊紙面に見えるとおり、当人が「米サンフランシスコで『グローバル・クライメイト・アクション・サミット』を開きます」とはしゃいでいた。)
第1章第1節で解説したとおり、企業の収益は剰余価値であり、第2節で解説したとおり、それは労働時間だけで決まる。
労働時間が同じで、労働者数が同じなら、収益は何を生産するかに依らない。
しかも、第3章で解説したとおり、再生エネと称する紛い物は剰余価値を産まない。
にもかかわらず、第1部第13章第9節で採り上げている2018年8月2日の朝刊紙面に見えるとおり、「いまや、収益性の高いビジネスや成功の好機になりました。例えば、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行は、急速な技術的進歩もあり、大きなビジネス機会になっています」と囃し立てている。
第4章第14節で解説したとおり、「利潤率の低下を阻止し新資本の形成によって資本価値の蓄積を促進するため」に、飼い犬のエア科学者らに人為的(排出CO2)温暖化を煽り立てさせているから、ホットハウス・アースをでっち上げた飼い犬が「いまや、収益性の高いビジネスや成功の好機になりました」と吠えているのである。
COPの議長をしていたメス犬も招かれ、そろって登壇しているのは、国際主義エリートの投資家が脱炭素の主体であることを明確に示している。
「2℃目標」を主導し、「ホットハウス・アース」論文にも関与した人物も、朝日新聞のWEBRONZAで喚いていた。
江守:このたびはインタビューの機会を頂きありがとうございます。あなたが「2度目標」の生みの親であるとどこかで読んだのですが、正しいですか?
シェルンフーバー:温暖化を2度で抑えるのが合理的だと言った人は他にもいたが、私の知る限り、それを政治プロセスに持ち込んだのは私が関わったものが初めてだ。1994年にドイツの「地球変動に関する諮問委員会」の中で私が言い出して議論し、1995年にベルリンで行われたCOP1に向けてドイツ政府に提案した。COP1を取り仕切っていたのは現在ドイツ首相であるアンゲラ・メルケルだ。
江守:当時は環境大臣でしたね。
シェルンフーバー:私が彼女に「2度」を提案した。その後、この提案はドイツ政府を通じて欧州理事会で議論され、1996年に欧州理事会の正式な決議になった。
「失われた20年」を振り返る
江守:それからちょうど20年が経っています。今やそれが国際合意になったのはすごいことです。しかし、その20年の間に温室効果ガスの排出量も大気中濃度も上昇を続け、目標の達成はどんどん難しくなってきました。20年間で、「2度目標」に関するあなたの認識は変化しましたか?
シェルンフーバー:まず、国際合意になったのは本当にすごいことだ。今やわれわれは気候問題の対策において一つのナラティブ(物語)を共有しているのだから。そして、一つの数字(2度)をも共有している。これが非常に重要だ。世界の気温上昇は、温室効果ガスの排出量の累積に依存するので、残された排出可能な量が規定される。言ってみれば「2度」がすべてを規定するのだ。
一方で、おっしゃるとおり、そこに至るのは非常に遅かった。1996年に欧州理事会が「2度」を採用したときに、中国、米国なども合意していたら……と思うが、もちろんそれは当時不可能だった。中国も、インドも、排出の権利を主張していた。それが政策決定の現実だ。みんなが合意するには、長い長い時間がかかる。20年が失われた。「2度未満」の実現は、20年前は比較的実現性が高かったが、今は非常に難しい。
しかし同時に、この20年の間に2度を超えるべきでない理由がより明らかになった。いくつかの危険なティッピングポイント(大規模で不可逆な影響の起きる閾値)を超えてしまうかもしれないといったことだ。それに、「2度」は非常に難しいが不可能ではない。特にドイツの固定価格買い取り制度導入以降、太陽光発電と風力発電のコストが劇的に安くなってきている。
つまり、失われた20年の間に得られるものもあったということだ。希望はまだある。
・・・中略・・・
江守:われわれ専門家や科学者の役割は何でしょうか?
シェルンフーバー:私は基礎物理学の出身だ。博士論文では物理学の重要な問題を解いたが、社会的な議論とはまったく関係がなかった。気候科学者も、科学的な水準は基礎物理と同じように高くなければいけない。一方で、気候科学者の知見は社会に直接的な意味を持つ。その点が基礎物理と違う。
たとえば、あなたがウィルス学者だったとして、感染力が強く対処法の知られていない新種のウィルスを発見したらどうするか。論文誌に発表して仲間内だけで議論するのか、それとも政策決定者に伝える責任があると思うのか。気候科学者も同じで、高水準の科学研究を行うと同時に、その意味するところを一般市民や政策決定者に説明しなければならない。ある意味で2つの人格を持つ必要がある。
科学者は政治的主張を避けるべきか
江守:科学者が政治的な主張をすると、その人の科学自体も政治的に偏っているという印象を与え、科学の信頼性を貶めるという見方もあります。科学とアドボカシー(特定政策の提言、擁護)についてどう考えますか?
シェルンフーバー:その問題は私もずっと考え続けてきた。それについて、私のロールモデル(模範となる人物)はアルバート・アインシュタインだ。アインシュタインは間違いなく最も偉大な科学者の一人だが、同時に非常に政治的でもあった。彼は平和、文化、宗教などについて考え、1955年には有名なラッセル=アインシュタイン宣言で軍拡競争に反対した。アインシュタインの人生を見ると、最高水準の科学と、その意味を社会に説明する責任は必ずしも矛盾しないことがわかる。
あなたの科学が社会に高い関連性を持つならば、その意味を社会に説明する道義的責任があると思う。それを仲間内だけで話しているのはほとんど犯罪的ではないか。科学の意味を社会に説明することが科学の質を損なうという誤った考えは、温暖化否定論者が持ち込んだものではないかと思う。
まとめると、アドボカシーはあなたの科学の質を損なわないし、あなたの科学が人類の重大な関心事であるならばアドボカシーはむしろ必要である。
(「『脱炭素』は、産業革命か、共産主義革命か」より。WEBRONZAは購読しないと一部しか読めないけれど、コチラにほとんど同じ文章が掲載されている。)
「この20年の間に2度を超えるべきでない理由がより明らかになった」のなら、科学的根拠は希薄にもかかわらず、「1994年にドイツの『地球変動に関する諮問委員会』の中で私が言い出して議論し、1995年にベルリンで行われたCOP1に向けてドイツ政府に提案し」、「1996年に欧州理事会の正式な決議になった」ことが「明らかになった」だけ。
国際主義エリートからの指示を受けた環境団体に命じられ、「1994年にドイツの『地球変動に関する諮問委員会』の中で私が言い出して議論し、1995年にベルリンで行われたCOP1に向けてドイツ政府に提案し」、「1996年に欧州理事会の正式な決議になった」ことが「より明らかになった」だけ。
「20年が失われた。『2度未満』の実現は、20年前は比較的実現性が高かったが、今は非常に難しい」と泣き喚いているけれど、現実には「この20年の間に2度を超えない理由がより明らかになった」。
第1部第10章第6節で解説しているとおり、「20年を振り返る」と、「その20年の間に温室効果ガスの排出量も大気中濃度も上昇を続け」たにもかかわらず、「1994年にドイツの『地球変動に関する諮問委員会』の中で私が言い出して」から気温上昇は進んでいない。
第1部第5章第1節と第12章第8節で解説しているとおり、CO2の温室効果は飽和に近いから、「世界の気温上昇は、温室効果ガスの排出量の累積に依存するので」、「温暖化が失われた20年」だった。
それを誤魔化すために、第1部第13章で解説しているとおり、データを捏造・改竄してハイエイタスを消し去り、それを正当化するために「いくつかの危険なティッピングポイント(大規模で不可逆な影響の起きる閾値)を超えてしまうかもしれない」と泣き喚き、「今やわれわれは気候問題の対策において一つのナラティブ(物語)を共有しているのだから」と「仲間内だけで話しているのはほとんど犯罪的ではないか」。
だから、第1部第12章第1節で紹介しているとおり、「ハイエイタスが90年代終わりから続いているのは率直に言って意外だ」と泣き喚いていたにもかかわらず、1.5℃特別報告書でハイエイタスが消えてしまったことには知らんぷり。
・気候変動による悪影響のリスクは、1.5℃温暖化した世界では現時点よりも顕著に大きくなり、2℃温暖化すればさらに大きくなる。
・温暖化を1.5℃で止めるには、2050年前後には世界全体のCO2排出量を正味でゼロにし、メタンなどCO2以外の温室効果ガスの排出も大幅に削減する必要がある。

世界平均気温の変化と1.5℃目標の関係(IPCC SR1.5 FAQ1.2に基づく)
しかし、これだけを聞いても、多くの人は「温暖化を1.5℃で止めないと何が本当にまずいのか」がよくわからないだろうし、「2050年前後に世界のCO2排出量をゼロにするなんて、もちろん無理でしょ」というところで思考が止まるのではないだろうか。
そこで本稿では、この報告書をどう受け止めたらよいのかについて、筆者なりの考えを書いてみる。筆者はこの報告書の執筆に参加していないし、仮に執筆者であってもIPCCの見解を代表することはできない。本稿はあくまで一専門家の立場からの解説である。
・・・中略・・・
ここで注目してほしいのは、仮にあなたが平気だったとしても、現時点の(1℃の)温暖化でも、既に受け入れられない悪影響が出ていると感じている人がいるであろうことだ。つまり、1.5℃なら平気で2℃だとたいへんだということではなく、現時点で既にたいへんで、1.5℃だともっと、2℃だともっともっとたいへんなので、せめて1.5℃で止めてほしい、という願いがあるということだ。
日本国内においても、この夏に豪雨による被害や熱波による健康被害に見舞われた方は、このような状況がさらに悪化するのは勘弁してほしいと願っていることだろう。
さらに深刻な悪影響を被るのは、発展途上国の貧しい人々である。干ばつの増加、生態系変化、海面上昇、嵐の激化などで生活基盤を失い、生命の危機に直面する、乾燥地域、北極域、沿岸域、小さい島国などに住む貧しい人々や先住民族などだ(しかも彼らは問題の原因である温室効果ガスを先進国の人々に比べてほんの少ししか排出していない)。そのような被害は彼らの貧困をさらに悪化させる。報告書によれば、温暖化を1.5℃で止めれば、2℃の場合と比べて、そのような影響に直面する人口を2050年時点で数億人減らすことができる。
海面上昇は、2℃に比べて1.5℃だと2100年時点で10cm ほど抑えられると評価されている。たった10cmという気もするが、危機に直面している人たちにとっては、少しでも猶予があることで、危機に対処する時間が生まれる。
また、1.5℃温暖化すれば、グリーンランドの氷床が不安定化する臨界点を超える可能性があり、2℃ならばその可能性はさらに高くなる。これが起きると数百年~数千年かけて、海面は数m上昇する。(直近の研究なので報告書の評価には含まれていないが、同様な臨界点現象の連鎖によって気温上昇が4~5℃上昇する引き金を引いてしまう「ホットハウス・アース」の可能性も、2℃に近づくほど高まる)
他にも、生態系の一部にはすでに大きな被害が出ており、1.5℃、2℃と行くにつれてさらに深刻化する。温水域のサンゴ礁は、1.5℃で今よりさらに70~90%が失われ、2℃で99%以上が失われると評価されている。一度失ってしまうと元に戻せないような生態系の損失が温暖化により進行し、生態系の恩恵が失われることで、人間社会にも予期せぬ影響が跳ね返ってくるかもしれない。
このように見ていくと、「そりゃあ、できることなら、なるべく低いところで温暖化を止められるに越したことはないだろう」と思う方は多いのではないか。
(「地球温暖化対策 なぜ1.5℃未満を目指すのか-IPCC特別報告書を読む」より)
改竄・捏造されたグラフを盾に、しかも、第1部第14章で解説しているとおり、CO2排出と異常気象に因果関係は認められないにもかかわらず、「ここで注目してほしいのは、仮にあなたが平気だったとしても、現時点の(1℃の)温暖化でも、既に受け入れられない悪影響が出ていると感じている人がいる」と泣き喚くのが、「その意味するところを一般市民や政策決定者に説明しなければならない」の「意味するところ」。
だから、「その意味を社会に説明する道義的責任がある」と嘯きながら、そして、江守正多自身も気象学会の会誌「天気,62(2015)591」で同じようなことを嘯きながら、第1部第13章の図13-40にも知らぬ顔の半兵衛。
環境研究所のホームページでも頬被りを決め込んでいる。
破廉恥なエア科学者どもは、「その意味するところを一般市民や政策決定者に説明しなければならない」と嘯いて、庶民=労働者階級を欺く。
庶民=労働者階級を欺くために、「その意味を社会に説明する道義的責任がある」と嘯く。
第1部第16章第5節でも指摘したけれど、科学が進歩した結果、ハイエイタスは存在しなかったことが分かったのだ、と言い張るのなら、ハイエイタスに関するエア科学者の抗弁に納得しなかった「温暖化否定論者」の方が正しかった、と認めねばならない。
「温暖化否定論者」の批判は、データを見直してハイエイタスが存在しなかったことを見出すきっかけとなった、「温暖化否定論者」との科学論争は「科学の意味を社会に説明することが科学の質を高める」好例となった、と評価すべきであろう。
にもかかわらず、あべこべに「科学の意味を社会に説明することが科学の質を損なうという誤った考えは、温暖化否定論者が持ち込んだものではないかと思う」のは、エア科学は「科学の質を損なう」ことをハッキリと示している。
マルクス「資本論」、岩波文庫第一巻p125より
「科学の意味を社会に説明することが科学の質を損なうという誤った考えは、温暖化否定論者が持ち込んだものではないかと思う」ような小賢しさが、今日ある仲間で「科学」の名で流行するというようなことを妨げないのである。
IPCC学派ほどに、「科学」という言葉を乱用した学派はかつてなかった。
まさに概念の欠けているところに、言葉がうまく間に合うようにやって来るものなのだ!
だから、ホットハウス・アース論文(もどき)を盾に「このように見ていくと、『そりゃあ、できることなら、なるべく低いところで温暖化を止められるに越したことはないだろう』と思う方は多いのではないか」と喚き立て、さらに、こんなことを喚いている。
以上が、筆者の理解したホットハウス・アースの根拠だ。論文では、ホットハウス・アースに至るフィードバックの連鎖を、具体的、定量的に分析した結果を示しているわけではなく、連鎖の可能性を指摘し、例示しているだけである。しかし、実際に中新世中期には現在に近いCO2濃度でホットハウス・アースが実現していたこと、地球史の中での異なる気候状態の間の遷移においては、ここに挙げたようなフィードバックの連鎖が実際に起きていたと考えられることなどから、筆者たちは、この議論は説得力がある(credible)と主張している。
ミニ氷河期はどうなのか
ここで、少し脇道にそれるが、この論文では触れられていない、太陽活動変動の影響について簡単に見ておこう。
現在、太陽活動は弱まる傾向にあり、太陽活動が今世紀中に長期的な不活発期に入るという予測がある。300年ほど前の同様な不活発期(マウンダー極小期)に英国のテムズ川が凍ったなどの記録があることから、温暖化を打ち消して寒冷化をもたらすような「ミニ氷河期」が来ると考える人たちがいるようだ。
しかし、300年前のミニ氷河期は、世界平均ではそれほど大きな気温低下をもたらしておらず、かつ原因の一部には火山噴火の影響も含まれることから、太陽活動低下の影響は世界平均気温でせいぜい0.3℃程度と評価されている。太陽活動の影響には「宇宙線」と雲の変化等を通じた未解明の増幅効果があることも指摘されているが、300年前を参考にするならば、それらの増幅効果を含めた大きさが高々0.3℃ということになる。
・・・中略・・・
また、筆者はこれまで、「パリ協定の目標は、なぜ2℃未満なのか?」と質問されると、「2℃」は科学的に決まったわけではなく、科学を参考にした社会的、政治的な判断だと答えてきた。「2℃」を超えると何かが起こるので避けるべきというよりは、気温上昇に伴い様々な影響が深刻化するので、特に、温暖化の原因に責任がないにもかかわらず深刻な被害を受ける途上国の人々や将来世代のことなども考えて、「2℃未満」が合意されたと理解していたのだ。
しかし、今回の論文には、パリ協定の「2℃」という数字に、(不確かさは依然大きいものの)より科学的な意味付けを与える効果があるように感じられる。社会の価値判断や政治判断によらず「2℃」を超えてはまずいということ、また、「2℃より十分低くするのが難しそうなら、2℃ぎりぎりでも、2℃を少し超えてもしょうがないのではないか」というような妥協を考えるのはまずいということを、この論文が主張しているように思われるのだ。
・・・中略・・・
最後に、このように対策オプションを並べられると、科学者が検討をして、こうすべきだ、ああすべきだと、社会に「上から」指示を出そうとしているように思われるかもしれない。しかし、この論文の著者らが重要な役割を果たしている国際研究プラットフォームである「Future Earth」では、地球の課題をいかに解決するかはもちろんのこと、そのためにどんな研究が必要かさえも、科学者は社会の様々な立場の人たちと一緒に考え、一緒に研究を進めていこうという姿勢が強調されている。
未来の地球は不確かさで満ちている。地球システムの様々なフィードバックも、太陽活動の変動も、そして我々人類の社会がどのように変化していくかも不確かな中で、人類は持続可能な未来を切り開いていかねばならない。そのためには、今回の論文が提示するような問題を、科学者だけでなく、社会全体で考えていくことが求められているのだ。
(「地球温暖化はもう手遅れか?(はたまたミニ氷河期到来か)」より)
第1部第11章第14節で採り上げている2017年5月7日の朝刊紙面は「北米大陸を2万年前まで覆っていた氷床の場合、いったん解けてしまうと、解け続ける臨界点の温度よりも2~3度低くならないと再び凍り始めない」と泣き喚いていた。
「臨界点の低い(1~3℃の)フィードバックのスイッチが入り・・・ホットハウス・アースへの移行が止められなくなる」、そして、「実際に中新世中期には現在に近いCO2濃度でホットハウス・アースが実現していたこと、地球史の中での異なる気候状態の間の遷移においては、ここに挙げたようなフィードバックの連鎖が実際に起きていたと考えられる」のなら、「中新世中期」以降はずっと「ホットハウス・アース」のはず。
北極と南極の氷が完全に解けてしまっていれば、第1部第6章の図6-1に見えるような氷河期は存在しなかったはず。
第1部第6章の図6-3を基に人為的(排出CO2)温暖化を煽り立てているけれど、ホットハウス・アース論文(もどき)はそれを否定してしまった。
ホットハウス・アース論文(もどき)はそれ自体が依拠する人為的(排出CO2)温暖化説を否定してしまったのだ。
にもかかわらず、「このように対策オプションを並べられると、科学者が検討をして、こうすべきだ、ああすべきだと、社会に『上から』指示を出そうとしているように思われるかもしれない」と泣き喚いているけれど、江守正多らごときが「社会に『上から』指示を出せる」はずもない。
第1部第16章第3節と第4節でも説明しているとおり、「Dana Nuccitelli らが検討をして、こうすべきだ、ああすべきだと、エア科学者に『上から』指示を出している」
その証拠に、第1部第5章第4節で解説しているにもかかわらず、「しかし、300年前のミニ氷河期は、世界平均ではそれほど大きな気温低下をもたらしておらず、かつ原因の一部には火山噴火の影響も含まれる」と泣き喚き続けているけれど、「0.3℃程度と評価されている」のリンク先は、やはり Nuccitelli!
もちろん、 Nuccitelli らは、何処からか金を貰って、温暖化を煽る活動をしてるだけ。
「何処ぞの誰かが検討をして、こうすべきだ、ああすべきだと、Dana Nuccitelli らに『上から』指示を出している」。
それを受けて、「Nuccitelli らが、こうすべきだ、ああすべきだと、江守正多らエア科学者に『上から』指示を出している」
言うまでもなく、「『最も上から』指示を出している」のは国際主義エリ-トの投資家様。[注1]
だから、こんなことを喚いている。
・・・中略・・・
ここからは完全に筆者個人の意見になるが、どうせならこの報告書のメッセージを前向きにとらえた方がよいと思う。つまり、「1.5℃を超えたらひどいことになるらしい」「いろいろ犠牲を払って温暖化を止めなくてはならないらしい」「何を我慢させられるのだろう、いくら支払わせられるのだろう」「どうせもうだめだ」という感じで、後ろ向きにこの問題を捉えても、何もいいことは起きないと思うのである。
そうではなくて、どのみち世界はSDGs の達成を目指しているのだから(平たくいえば、どのみちみんな「社会を良くする」ことを目指しているのだから)、「1.5℃目標」は世界の持続可能性に向けた取り組みを加速する「機会(opportunity)」だと思ったらよいのではないだろうか。
その取り組みを具体的に論じることは筆者の能力を超えるが、たとえばビジネスであれば、持続可能な社会に寄与するシステムの構築やサービスの提供が、投資家から評価され、顧客からも喜ばれ、利益も生む、といった方向性が主流になり、そういうビジネスが競争すればするほど社会が良くなり、同時に「1.5℃目標」の達成にも近づいていく、ということが起こればよいと思っている。
個人レベルでは、「行動変容」という項目があるように、ライフスタイルの変化ということがよく言われるが、これも、不便で面倒で質素な生活を強要されていると捉えるべきではないだろう。例えば、肉ばかり大量に食べて、しかも大量に捨てて、車だけで移動し、運動不足で病気になるようなライフスタイルよりも、バランスの良い適量の食事をとり、適度に歩いて健康に過ごした方が、自分にとっても社会にとっても良いというのだから、それを目指して損はないのではないか。
・・・中略・・・
しかし、これを考慮したとしても、本稿の結論は変わらない。1.5℃を全力で目指しても大きな影響が出てしまう場合にどうするかといったことは、走りながら考えることにして、差し当たって、社会は「1.5℃目標」を全力で、前向きに、かつ賢明に(つまり持続可能性とのトレードオフをうまく制御しながら)目指せばよいのではないか。
なにせ、温暖化を1.5℃未満に抑える「努力を追求する」ことに、国際社会はすでに合意しているのだから。
(「地球温暖化対策 なぜ1.5℃未満を目指すのか-IPCC特別報告書を読む」より)
「その意味するところを一般市民や政策決定者に説明しなければならない」と喚きながら、ハイエイタスが消えてしまったことに頬被りを決め込んで、「どうせならこの報告書のメッセージを前向きにとらえた方がよいと思う」、「後ろ向きにこの問題を捉えても、何もいいことは起きないと思う」のは、江守正多らエア科学者がどちらの方を向いているかを如実に示している。
市民に背を向け、投資家の方を向き、「前向き」と喚き立てているのである。
第4章第1節でも引用したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p232-233より
から、「こういった移行に伴って失業や貧困が生じることも重要なトレードオフだ」。
国民の血税で生活し、失業や貧困の不安がない輩が、平然と「こういった移行に伴って失業や貧困が生じることも重要なトレードオフだ」と言ってのけるところに、脱炭素の真実が顕われている。
第4章第7節でも引用したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p229より
「この点に配慮して、国や国際社会が移行を支援する必要があるだろう」と言い立てるのは、「自分の肩から労働者階級および下層中間階級の肩に転嫁することを心得ている」わけである。
前章第16節でも引用したけれど、
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p88より
「国際主義エリートの投資家は、自分たちが支配する世界を、当然もっともよい世界と考える」から、飼い犬のエア科学者が「どのみちみんな『社会を良くする』ことを目指している」と吠え立てる。
「脱炭素社会主義は、この楽しい考えを半体系または全体系にまで作りあげる」から、「投資家から評価され、顧客からも喜ばれ、利益も生む、といった方向性が主流になり、そういうビジネスが競争すればするほど社会が良くなり」と吠え立てる。
「方向性が主流になり」は「奉公性が主流になり」に他ならない。
飼い犬に「不便で面倒で質素な生活を強要されていると捉えるべきではないだろう」、「自分にとっても社会にとっても良いというのだから、それを目指して損はないのではないか」と吠え立てさせて、「脱炭素社会についてのいまわしい観念をぬぎ捨てることを要求する」。
「国際社会はすでに合意している」は「貴族社会はすでに合意している」
「国際合意になったのは本当にすごいことだ。今やわれわれは気候問題の対策において一つのナラティブ(物語)を共有しているのだから」とは、「ダボスの合意になったのは本当にすごいことだ。今やわれわれは庶民=労働者階級の収奪において一つのナラティブ(物語)を共有しているのだから」。
「あなたの科学が人類の重大な関心事であるならばアドボカシーはむしろ必要である」は、「あなたのエア科学が国際主義エリートの重大な関心事であるならばアドボカシーはむしろ必要である」に他ならない。[注2]
[注1] もちろん、江守正多らエア科学者は「自分たちが検討をして、こうすべきだ、ああすべきだと、社会に『上から』指示を出そうとしている」と思い上がっている。
けれど、ダボス様はそれを容認している。
むしろ、思い上がってくれれば都合が良い。
彼らがそう思い上がっていれば、脱炭素の真の主体はダボス様であることが、庶民=労働者階級からの収奪を強めるための脱炭素であることが、覆い隠されるから。
[注2] 第1部第16章第2節で解説しているとおり、自然科学の他の分野なら研究者生命を絶たれているはずのマイケル・マンが「科学がこれほど攻撃を受けたことはなかったし、これほど必要とされたこともない」と泣き喚いたのは、「科学がこれほど攻撃を受けたことはなかったし、エア科学がこれほど国際主義エリートの投資家に必要とされたこともない」ことを、ハッキリと示している。
にもかかわらず、アメリカ科学振興協会(AAAS)は「その意味を社会に説明する道義的責任」のお手本として賞した!
「アドボカシー」の真相が良く分かる。
6.2 ダボス
だから、「グローバル気候行動サミット」に招かれたエア科学者は、「グレた娘」と共にダボス会議に招かれた。
もちろん、朝日新聞が囃し立てている。
2019.3.4
ポツダム気候影響研究所ディレクター ヨハン・ロックストローム氏に聞く
人類が地球に及ぼす影響があまりにも大きくなった結果、人類は自らが地球の状態を左右してしまう「人新世」という未知の時代に足を踏み入れようとしている――。最近、耳にするようになった「人新世」という言葉は、私たちにえも言われぬ恐怖を与える。生みの親のひとりで、ポツダム気候影響研究所ディレクターのヨハン・ロックストローム氏にインタビューした。(聞き手・石井徹、写真・北村玲奈)
人新世とはなにか
人新世は、人類によってつくられた新しい地質年代です。人間活動の指数関数的増大によって1950年前後から地球システムへの圧力が高まり、人間が惑星規模での変化の主役になったのです。
最終氷期以降の完新世(約1.2万年)は、温暖で安定した気候に恵まれて農耕文明が起こり、人類を支えることができる唯一の地球の状態でした。
その均衡は、生物物理学的プロセスと地球システムによるフィードバック、例えばグリーンランドや南極大陸の氷床による太陽光の反射率、土壌や植生、海洋の炭素吸収によって決められます。人新世の始まりは、地球のバランスの根本的な変化を示しています。人類自体が地質学的な力になり、地球に前例のない圧力をかけている状態です。

問題は、私たちがどこで閾値(いきいち)を超え、いつ後戻りできなくなるのか。地球の新しい均衡状態になる転換点を超えることです。これが「温室の地球」と呼ばれるもので、気温上昇が2度を超えると、地球温暖化は4~6度、それ以上に、長期的に自己増幅する危険があります。
「プラネタリー・バウンダリー」を知れ
かつての人類は、地球の状態を左右するような存在ではありませんでした。しかし人新世では、地球を完新世の状態に保ち、人類にとって安全な機能空間を提供するにはどうすればいいかを、私たちはもっとよく理解する必要があります。
それは、私たち研究チームが「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」で、気候変動、生物地球化学的な流れ、生物圏の状態などについて描いたものです。地球や世界が不安定になるのを避けるために、私たちは地球の限界を知るだけでなく、その境界内で発展する必要があります。
人新世では、人類は地球変動の最大の推進者になっています。地震や火山噴火のような自然変動を、速度でも規模でも超えています。人間が地球にかける圧力は1950年ごろ急激に増大しました。私たちはこれを「大加速」と呼び、人新世の始まりを示しています。人類は確かに以前から、多くの環境問題を抱えていましたが、気候システム全体の安定性を危険にさらすような力はありませんでした。
人新世という用語は、地球上のすべての自然系に持続不可能な圧力をかけ、私たち自身の未来を危険にさらしていることを表現しています。いまのような状況を続けていれば、地球は転換点を超えてまったく違う状態になるでしょう。これが「温室の地球」であり、悲惨な未来は何世代にもわたって続く可能性があります。
その一方で、私たちは、これとは別の人新世を形成する力を持っています。安全な機能空間の境界内で繁栄と平等を実現する未来に向かって進む力です。それには困難が伴い、コストがかかるでしょう。そして、完新世が長期にわたって提供した「エデンの園」には、戻れないかもしれません。
しかし、世界がパリ協定に合意したことによって、私たちは地球を管理可能な状態に保ち、温暖化を2度未満に抑えるができます。これは、地球の安定性にとって最大のチャンスです。地球がまだ、水、空気、土地、魚、海などを与え続け、人類に「友好的」でいてくれるということです。
経済、社会、そして世界全体は、安全な機能空間の中で進化する必要があります。これこそが、いまの私たちの課題であり、途方もない技術革新と社会変革がもたらされると確信しています。

世界は2050年に100億人の人口を養うだけではなく、それを持続可能でスマートにやらなければなりません。それは、世界の食料システムを、現在の温室効果ガスを排出して生態系を破壊する方向から、主要な炭素吸収源に変えることです。私はそこにかかっていると思います。これは壮大な課題ですが、すでに多くの解決策があります。
1月の世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)に出席しましたが、世界の経済界がとる気候行動という面では、これまでで最も強い表明がなされたのではないかと思います。しかし、その努力は依然として遅れています。この不満は、ダボスの指導者たちによっても公然と議論されました。
私たちは、すでに1度の温暖化を経験しており、2018年は世界の大部分の人に気候変動の影響が明らかになった最初の年であったかもしれません。地球温暖化を1.5~2度未満に抑えるためには、世界の政治指導者やビジネスがさらに協調して努力する必要があります。
ヨハン・ロックストローム 1965年スウェーデン生まれ。地球の持続可能性の研究で著名な環境科学者で、ストックホルム・レジリエンス・センター所長を経て、昨年10月からポツダム気候影響研究所ディレクター。2009年に他の研究者とともに人類が生存できる範囲の限界「プラネタリー・バウンダリー」を発表した。
「人新世は、人類によってつくられた新しい地質年代です」だの、「人類自体が地質学的な力になり、地球に前例のない圧力をかけている状態です」だの、「地球がまだ、水、空気、土地、魚、海などを与え続け、人類に『友好的』でいてくれる」だのと喚いているけれど、社会的強者も弱者も十把一絡げにして「人類」と言い立てる時、そこには必ず、社会的強者による抑圧・搾取を正当化しようとする意図が隠されている。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p84より
化石燃料で利を得てきたのは国際主義エリートの投資家であるにもかかわらず、「この不満は、ダボスの指導者たちによっても公然と議論されました」と言い立てるのは、CO2を排出して「我が世の春を謳歌して」きた愚かな庶民=労働者階級どもが「地球に前例のない圧力をかけている状態です」と罵り、「地球がまだ、水、空気、土地、魚、海などを与え続け、ダボスの人類に『友好的』でいてくれる」うちに、愚かな労働者階級を抑え込まねばなりません、と言うことに他ならない。
「『プラネタリー・バウンダリー』を知れ」とは、愚かな労働者階級は「『自らのバウンダリー』を知れ」と言うこと。
その証拠に、ダボス様が炭素税を導入しろと言い張り、それを朝日新聞が歓び勇んで吹聴している。
(「グレた」娘も賞賛している。「グレた」娘の破廉恥で醜悪な正体が良く分かる。)
下の紙面に見えるとおり、このエア科学者も「炭素税などを設け、化石燃料への新たな投資をやめ、化石燃料に依存する『最終日』を決めるべきだ」と泣き喚いている。
けれど、第3章第4節と第4章第14節でも解説したとおり、「化石燃料依存『最終日』決める時」なら、炭素税は必要ない。
第1部第13章第9節で採り上げている2018年8月2日の朝刊紙面に見えるとおり、「再生エネが化石燃料より安くなって広がったように、いまの変化は持続可能性にこそ収益性があり、唯一の成功の道だと分かったから起きているのです」と喚いているけれど、「再生エネが化石燃料より安くなって広がった」のなら、炭素税は必要ない。
にもかかわらず、炭素税と言い張るのは、「再生エネが化石燃料より安くなって広がった」のデマを、庶民=労働者階級からの収奪を強めてダボス様が富を肥やすために、プラタネリー・バウンダリーだのホットハウス・アースだのと煽り続けてきたことを、ハッキリと示している。
マルクス「資本論」、岩波文庫第二巻p81より
彼ら(投資家ら)は、いつもの実際的な慧眼で、この教授先生(ヨハン・ロックストローム)には「まだまだ仕上げが足りない」ことを知っていた。
それで彼をダボスに呼んだのである。
教授は教授で、ダボスで投資家たちから受けた講義を作文にして「プラネタリー・バウンダリー」「ホットハウス・アース」という小冊子をつくった。
だから、「世界の食料システムを、現在の温室効果ガスを排出して生態系を破壊する方向から、主要な炭素吸収源に変えることです」と、つまり、庶民=労働者階級は肉を食うな、清く貧しく生きよ、と喚き立てている。
(第1部第13章第9節で採り上げている2019年11月2日の朝刊紙面でも、「温室効果ガスを大量排出して生態系も壊している食料生産システムの変革が、特に重要です」と泣き喚いている。)
2019年8月9日 17:07 発信地:パリ/フランス
地球温暖化を食い止めるために菜食主義者やビーガン(完全菜食主義者)になる必要はない。だが、人類が肉を食べるのを止めれば、温暖化対策は楽になるだろう――国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が8日公表した「特別報告書」は、曖昧で食肉賛成派・反対派どちらにとっても不満足な内容となった。
気候変動と人間の食生活との関連性についてまとめたこれまでで最も包括的な報告書の要点は、非常に明白だ。気候変動は世界の食料供給を脅かしており、食料の生産方法でさえ地球温暖化に拍車をかけているということだ。
熱帯地方では、気温上昇により収穫量が減少し、主要穀物の農地が奪われ、食用植物の必要養分も失われ始めている。
一方、世界のフードシステム(食料の生産から流通・消費までの流れ)は、世界で排出される温室効果ガスの少なくとも4分の1を占めている。世界人口は今世紀半ばまでに20億人増加すると考えられているが、安易に食料生産量を増やせば、地球の平均気温は危険レベルをはるかに超えることになる。
今日、食料関連の温室効果ガス排出量の半分以上が畜産業によるものだ。うち半分は、羊や牛の飼育に関わるもので、牛の割合が特に高い。
英ロンドン大学衛生熱帯医学大学院で栄養学と国際保健を専門とするアラン・ダングール(Alan Dangour)氏は、「今日発表されたIPCCの報告書で、私たちの食習慣が環境に多大な影響を及ぼしていることが確認された」と述べた。「フードシステムによる環境への影響を抑制するには、食生活における肉類の消費を減らすことが重要であることは明白だ」
■気候に対する二重の脅威
畜産業は、気候にとって二重の脅威となっている。特にブラジルの亜熱帯地域では、二酸化炭素を吸収する森林が放牧地や牛の餌となる大豆作物を育てる畑に変わっている他、家畜が排出する大量のメタンガスは温室効果ガスの発生源にもなっている。
米首都ワシントンに本部を置く政策シンクタンク「世界資源研究所(WRI)」によると、同量の牛肉の動物性たんぱく質と標準的な植物性たんぱく質を比較した場合、平均して肉牛の飼育には植物栽培の20倍の広さの土地が必要となり、温室効果ガス排出量も20倍となるという。
こうした理由から、植物性食品を中心とする「バランスの良い食生活」に移行することにより、気候変動の原因を大幅に減らすことができるとIPCCは結論付けている。
この結論は、菜食主義を全面的に支持しているようにみえるかもしれない。だがIPCCは、世界中の人々に対し肉食を一切やめるよう義務付けたり奨励したりしているわけではないと述べている。
「バランスの良い食生活」には、「雑穀やマメ、野菜、果物、木の実、種子」に加え「レジリエントで、持続可能的で、温室効果ガスの排出量が少ない動物性食品」も含まれると報告書は指摘している。
報告書の作成に関わった100人以上が、生産過程で二酸化炭素排出量が極めて多い赤身肉の禁止を求めるまでに至らなかったのにはいくつか理由があるようだ。そもそも報告書では、何も要求していない。
ポツダム気候影響研究所の元所長で報告書の共同執筆者であるヨハン・ロックストローム(Johan Rockstrom)氏は、「われわれが提案するバランスが取れた食生活とは、約100グラムの赤身の肉を毎日ではなく週に1度食べることだ」とAFPに語った。
(AFP/Marlowe HOOD)
第1部第15章第23節で解説しているとおり、専門学会は「成人の赤肉の消費について加工肉、未加工肉ともに『現状を維持すべき』だ」と主張している。
にもかかわらず、第4章第6節で採り上げている「ダボス2017、民衆の怒りに触れた『貴族』たち」という見出しの記事に見えるとおり、「それでもシャンパンやキャビアはふんだんに振る舞われるだろう。1780年代のベルサイユ宮殿や1900年代のロシア帝国の冬宮と変わらぬほどのぜいたくさ」のダボスに招かれた輩が、「われわれが提案するバランスが取れた食生活とは、約100グラムの赤身の肉を毎日ではなく週に1度食べることだ」と喚き立てる。
マルクス「経済学・哲学草稿」、岩波文庫p153-154より
驚くべき投資家のエア科学は、同時に禁欲の科学であり、そして、それの真の理想は、禁欲的ではあるが、しかし、暴利を貪る守銭奴であり、禁欲的ではあるが、しかし生産をする奴隷である。
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p373より
から、前節で見たとおり、江守正多も市民に指突きつけて、肉ばかり大量に食べて、と罵っていた。
6.3 石炭火力
江守正多らは投資家のために温暖化を煽り立てているから、こんなことを喚いている。
この戦略の発表に先立って、有識者懇談会の座長案にあった「石炭火力は長期的に全廃する」という方針が、産業界の反対により「依存度を可能な限り引き下げる」といった表現に調整されたという報道があった。
筆者は率直に申し上げて、この調整は意味がわからない。期限を切らずに「長期的に」というだけならば、脱炭素を目指す以上、石炭火力はいつか全廃するに決まっているからだ。正確にいえば、CCS(CO2 Capture Storage)技術を用いてCO2を地中に封じ込めるならば、その分は石炭火力(や他の火力)を使っても脱炭素と矛盾しないので、「CCSの無い石炭火力は長期的に全廃する」でよいのではないかと思う。
おそらく、「長期的な全廃」を明示することが短中期的な石炭火力利用にも足かせになることを嫌がる人たちがいるということだろう。エネルギー価格の上昇が国際競争力に影響をもたらす製造業、高効率で「クリーンな」石炭火力の研究開発に注力してきたエネルギー産業、そして、新規の石炭火力を計画したり着工したりしている事業者などがそのように考えるのはよく理解できる。
しかし、期限を切らない「長期的な全廃」も書き込めないほど腰が引けているようでは、この戦略の「脱炭素ビジョン」の本気度に、残念ながら疑いを差しはさまざるをえない。
日本社会が石炭と手を切るのは、経済的、技術的な問題にとどまらず、政治的、文化的な問題でもあり、想像以上に難しいことなのかもしれない。カナダのアルバータ州では、2030年までの脱石炭に先立ち、大手電力会社に補償金を支払っているそうだ。ちなみに、奴隷制が廃止された際も、奴隷所有者に補償があったという。日本の戦略は、そこまでの覚悟をもって石炭と手を切ろうという決断には程遠いものだ。
なお、先ほど触れた「CCS付き石炭火力」を筆者は積極的に押しているわけではない。戦略の本文でも述べられているように、CCSは(石油増進回収をともなう場合を除き)単独では経済メリットが無い。経済メリットが生じるためには、「炭素に価格が付く」必要があるのだ。一方で、経団連は炭素税などのカーボンプライシング(炭素に価格が付くこと)に一貫して反対している。これはCCSの推進と矛盾するのではないだろうか。
カーボンプライシングについての議論は経済学者に譲るが、今年1月に米国で27人のノーベル賞受賞者などを含む3500人以上の経済学者が、炭素税に支持を表明していることに留意しておきたい。
国民はどこにいるのか
最後に、この戦略全体を通じて、「国民」の存在感が希薄である印象を持ったことを指摘しておきたい。国民は、ビジネス主導のイノベーションに「巻き込まれる」存在であり、CCS等の技術を「受容する」ことが期待される存在であり、ライフスタイルを転換するように「啓発される」存在として登場する。
しかし、国民は、もし尋ねられれば、原発にも、石炭火力にも、再エネの乱開発にも、言いたいことがたくさんあるのではないだろうか。どんなイノベーションを望むのか、どんな利害調整を必要とするのか、どんな本気度・スピード感でこの戦略を実行することを望むのか、いろいろ意見があるのではないだろうか。
冒頭に述べたことを繰り返すが、世界的に重要度が高まる気候変動の問題について、日本がどう取り組み、どう成長につなげるかの戦略が、今、決まろうとしている。この戦略はすべての国民の生活や仕事や人生に影響をおよぼすだろう。
パブリックコメントは5月16日まで。
環境省の意見交換会は5月14日に京都(若者世代)、15日に仙台(地域のステークホルダー)。
(「パリ協定に基づく日本の成長戦略の『本気度』」より)
その後も泣き喚き続けている。
経産省の方針では高効率の石炭火力は維持、拡大するといわれており、環境NGOはこの点を特に批判している。しかし、石炭火力を新設しようとする事業者がどんなふうに経済的な合理性を見込んでいるのかが、筆者にはわからない。
再エネのコストはどんどん安くなっており、世界の多くの地域(英国のシンクタンク Carbon Tracker の報告によれば日本も含む)で既に新設の石炭火力よりも新設の再エネの方が安い。この傾向は今後さらに拡大していくだろう。また、再エネが増えるほど、火力発電は出力制御をしなければいけなくなるので、稼働率が落ちて収益性が下がる。
 水色で塗られた地域では新設の再エネが新設の石炭火力よりコストが安い。Carbon Trackerより。
水色で塗られた地域では新設の再エネが新設の石炭火力よりコストが安い。Carbon Trackerより。
本格的なカーボンプライシング(炭素税や排出権取引)が日本でも導入されれば、石炭火力のコストはさらに上がる。すぐに導入されるかはわからないが、10~20年にわたって導入されないと想定する事業者はさすがに楽観的すぎるだろう。CCSを後付けできればカーボンプライシングはかからないが、もちろんCCSのコストがかかる。
もしも筆者が石炭火力を計画中の事業者の立場であったならば、全力で引き返す判断をするだろう。既に投資してしまった額によっては辛い判断になるかもしれないが。
・・・中略・・・
石炭からの卒業については、以前に朝日新聞の石井編集委員による秀逸な記事があった。この記事は次のように締めくくられている。「どうせ別れるのだから、きっちりと準備して、これまで世話になったことに感謝して別れたい。後腐れや恨みっこは、なしで。」
筆者も同じ気持ちだ。1970年代の石油ショック以降、石炭を高効率でクリーンに燃やす技術を研究開発し普及させてきた日本の科学者、技術者、事業者への尊敬と感謝を忘れてはいけないと思う。彼らには、貧しい途上国に安価でクリーンな電気を届けたいという思いもあっただろう。それは時代が要請する技術だった。
ただし、それは今ほどCO2の問題が大きく認識される以前までのことだ。時代は流れ、常識は変化する。
石炭に笑顔で感謝しつつ、毅然とした表情で前を向き、石炭の時代から卒業したい。
(「石炭火力からの卒業がやっぱり日本でも合理的である5つの理由」)
前節でも述べたとおり、石炭火力廃止の期限を決めるのなら、そして、「世界の多くの地域(英国のシンクタンク Carbon Tracker の報告によれば日本も含む)で既に新設の石炭火力よりも新設の再エネの方が安い」のなら、カーボンプライシングは必要ない。
にもかかわらず、「3500人以上の経済学者が、炭素税に支持を表明している」のは何故か。
前章第17節でも引用したけれど、
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p51より
第1節でも「化石燃料産業はそのままでは存続できないので」と喚き立てていたけれど、一方では「再エネが増えるほど、火力発電は出力制御をしなければいけなくなるので、稼働率が落ちて収益性が下がる」と泣き喚き、他方では「経済メリットが生じるためには、『炭素に価格が付く』必要があるのだ」「本格的なカーボンプライシング(炭素税や排出権取引)が日本でも導入されれば、石炭火力のコストはさらに上がる」と喚き立てるのは、「一方では、一定量の生産諸力をむりに破壊することによって、他方では、あたらしい市場の獲得と古い市場のさらに徹底的な搾取によって」を明確に示している。
「カナダのアルバータ州では、2030年までの脱石炭に先立ち、大手電力会社に補償金を支払っているそうだ。ちなみに、奴隷制が廃止された際も、奴隷所有者に補償があったという。日本の戦略は、そこまでの覚悟をもって石炭と手を切ろうという決断には程遠いものだ」と泣き喚いているけれど、「大手電力会社に補償金を支払う」ということは、カーボンプライシングで庶民=労働者階級から巻き上げて、電力会社に投資してきた投資家に「補償金を支払う」ということ。
そして、投資家は再生エネに投資し、カーボンプライシングで電気代を吊り上げ、庶民=労働者階級からさらに巻き上げて、さらに利を貪るということ。
これまた、「一方では、一定量の生産諸力をむりに破壊することによって、他方では、あたらしい市場の獲得と古い市場のさらに徹底的な搾取によって」を明確に示している。
わざわざ「奴隷制が廃止された際も、奴隷所有者に補償があった」と言い立てたのは、脱炭素の本質を見事に露呈しているではないか。
「『国民』の存在感が希薄である印象を持ったことを指摘しておきたい」と嘯いているけれど、「どんなイノベーションを望むのか、どんな利害調整を必要とするのか、どんな本気度・スピード感でこの戦略を実行することを望むのか」において、「国民は、ビジネス主導のイノベーションに『巻き込まれる』存在」ではないか。
先に見たとおり、「肉ばかり大量に食べて、しかも大量に捨てて、車だけで移動し、運動不足で病気になるようなライフスタイルよりも、バランスの良い適量の食事をとり、適度に歩いて健康に過ごした方が、自分にとっても社会にとっても良いというのだから、それを目指して損はないのではないか」と罵っていたけれど、国民は「ライフスタイルを転換するように『啓発される』存在」ではないか。
「経済メリットが生じるためには、『炭素に価格が付く』必要があるのだ」と言い張り、「一方で、経団連は炭素税などのカーボンプライシング(炭素に価格が付くこと)に一貫して反対している。これはCCSの推進と矛盾するのではないだろうか」と泣き喚き、その直ぐ後で「カーボンプライシングについての議論は経済学者に譲るが、今年1月に米国で27人のノーベル賞受賞者などを含む3500人以上の経済学者が、炭素税に支持を表明していることに留意しておきたい」のは、国民が「カーボンプライシングを『受容する』ことが期待される存在」だからではないか。
第4章第14節で見たとおり、朝日新聞も経団連を口汚く罵っていたけれど、「国民はカーボンプライシング等の搾取を『受容する』ことが期待される存在」にもかかわらず、「経団連は炭素税などのカーボンプライシング(炭素に価格が付くこと)に一貫して反対している」から、「国民はどこにいるのか」と泣き喚いたのだ。
「もしも筆者が石炭火力を計画中の事業者の立場であったならば」は、「筆者が国際主義エリートの投資家の飼い犬の立場であるから」に他ならない。
だから、第4章第5節で紹介した編集委員、最上位1%の富裕層でありながら市民の血税でEVを購入した輩が書いた記事を、「石炭からの卒業については、以前に朝日新聞の石井編集委員による秀逸な記事があった」と囃し立てる。
地中にある石炭自体には何の価値もない。
炭鉱労働者が掘り出してきたから石炭に価値が生じた。
第1章第1節で説明したとおり、掘り出された石炭には価値が、炭鉱労働者の労働力の価値と、炭鉱労働者が自身の労働力の価値以上に創り出した剰余価値がある。
石炭火力発電において石炭は不変資本であり、その価値は生産物、つまり、電力の価値に移転する。
それに、石炭火力労働者の労働力の価値と、石炭火力労働者が自身の労働力の価値以上に創り出した剰余価値が加わる。
電力の価値は炭鉱労働者が創り出した価値と、石炭火力労働者が創り出した価値から成る。
すべての原材料の生産において電力は不可欠であり、電力という流動不変資本の価値は生産物である原材料の価値に移転するから、基本的原材料の価値は炭鉱労働者と石炭火力労働者が創り出した価値とを含む。
その原材料を用いて機械を生産するのにも電力が必要だから、機械の価値には、原材料と電力という流動不変資本を介して、炭鉱労働者と石炭火力労働者の創り出した価値が二重に含まれる。
その機械を用いて商品を生産するのにも電力が必要だから、商品の価値には、電力という流動不変資本と機械という固定不変資本を介して、炭鉱労働者と石炭火力労働者が創り出した価値が三重に含まれる。
全ての商品の価値は炭鉱労働者と石炭火力労働者の創り出した価値の上に成立している。
昔は上流階級のみが新聞を購読していた、と言うよりも、庶民は新聞を購読できる経済的余裕もなかったけれど、現代の民主主義社会では庶民=労働者階級が新聞を購読している。
つまり、労働者階級の所得の一部が新聞社員の所得になっている。
もちろん、それだけではなく、新聞では広告収入が大きな収入源だけれど、企業が広告に使うお金は労働者が産み出した剰余価値の一部から(または労働力の価値を削って)支出されている。
新聞社は、新聞社員の生活は、労働者が創り出した価値の上に成り立っている。
その価値の源は炭鉱労働者と石炭火力労働者が創り出した価値。
江守正多らエア科学者の生活も炭鉱労働者と石炭火力労働者が創り出した価値の上に成り立っている。
炭鉱労働者と石炭火力労働者に感謝するなら、投資家と「きっぱり別れたい」はず。
石炭で利を得たのは投資家だから、投資家の資産と「きっぱり別れたい」、つまり、投資家の資産を没収したいはず。
ところが、ダイベストメントと囃し立て、「石炭ときっぱり別れたい」と、つまり、炭鉱労働者、石炭火力労働者と「きっぱり別れたい」と泣き喚く。
第4章第13節で採り上げた2019年1月7日の社説と同様、「時代に逆行」と罵っているけれど、「一方では、一定量の生産諸力をむりに破壊することによって、他方では、あたらしい市場の獲得と古い市場のさらに徹底的な搾取によって」、投資家が富を肥やす「時代に逆行」するから、「きっぱり別れたい」のだ。
(「石炭の消費量を減らしていくためには、健康や環境へのコストを価格に反映する方法が最も効果的です。インドでは、1トンあたり400ルピー(約700円)の石炭税を課しています。大気汚染の減少や自然エネルギーへの投資促進につながるはずです」や、「10年間かけて、職業訓練や転職指導を進め、段階的に職員を減らしてきた」は、「カナダのアルバータ州では、2030年までの脱石炭に先立ち、大手電力会社に補償金を支払っている」と全く同じ。)
第4章第3節で採り上げた2021年1月24日の社説余滴は「石油会社に勤めていた労働者たちが転職し、森林の再生に携わる」と喚き立て、「私たちは何にでもなれる。それを見つめる勇気さえあれば」と囃し立てていたけれど、つまり、炭鉱労働者や石炭火力発電所の労働者とその家族に、失業することを恐れるな、勇気を持て、と高言していたけれど、CO2を排出して利を得たのは投資家だから、投資家こそが資産を全て没取されて無一文になる「勇気」を持つべきであろう。
その次には、朝日新聞が廃刊されて朝日新聞社員が、そして、江守正多らが森林の再生に携わる「勇気」を持たねばならない。
けれど、それは口が裂けても言わない。
「一方では、一定量の生産諸力をむりに破壊することによって、他方では、あたらしい市場の獲得と古い市場のさらに徹底的な搾取によって」、投資家が富を肥やすために温暖化を煽り立てているから。
国際主義エリートの投資家、その僕の左翼メディア、環境団体、そして、飼い犬のエア科学者とは「きっぱり別れたい」!
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p67より
諸君は「どうせこの世から別れるのだから、きっちりと糾弾して、身も心もズタボロにして別れたい。後腐れや恨みっこは、なしで」
6.4 エア科学者の不都合な真実2
その証拠に、こんな社説も書いている。
「2050年までに温室効果ガスを80%削減する」という地球温暖化対策の長期目標を、どう実現していくのか。政府の長期戦略づくりが始まる。パリ協定を実行していく上で、きわめて重要なロードマップである。
今月始まった有識者懇談会の議論を土台に戦略を練る。来年6月に大阪である主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)までにまとめたい考えだ。
長期目標の閣議決定から2年あまり、政府が戦略づくりに二の足を踏む間、世界は「脱炭素時代」へ急速に転換している。日本も急がねばならない。
未曽有の原発事故を起こした国として、原発依存度を下げていくこととの両立も重要だ。欧米では再生可能エネルギーのコストが下がり、原発の競争力が失われつつある。再エネや省エネのさらなる拡大につながる野心的な戦略が求められる。
■世界に広がる危機感
パリ協定は「産業革命前からの気温上昇を2度未満、できれば1.5度までに抑える」という目標を掲げ、今世紀後半に温室効果ガス排出を実質ゼロにすることをめざしている。
国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の特別報告書案によると、このまま気温が上がり続けると40年代に1.5度に達する。各国が危機感をもって排出削減に取り組んでいるのは当然である。
たとえば英国は、石炭火力発電を25年までに全廃することを決めた。数年前に約40%だった石炭火力の比率は9%に減っている。カナダや欧州主要国の多くも石炭ゼロの目標を掲げる。
クリーンエネルギーを拡大する政策も相次いでいる。
ドイツは50年に電力の80%以上を再エネでまかなう目標を掲げた。英仏は40年までにガソリン・ディーゼル車の新車販売禁止を決めたほか、中国も19年から新車の一定割合を電動車にするよう義務づける。
■化石燃料からの撤退
ビジネスの動きも急だ。
石炭や石油への投資が回収不能になるのを避けるため、化石燃料からの投資撤退が広がっている。撤退を表明した企業や投資家の運用資産は660兆円を超えた。逆に、環境や社会などを重視する「ESG投資」が2500兆円に急増している。
マネーが脱炭素に方向転換しているだけでなく、企業の振る舞いも変わりつつある。
業務で使う電力をすべて再エネでまかなうという目標を掲げる国際的な企業連合「RE100」、企業が科学に基づいて温室効果ガスの削減目標をつくる「SBT」……。脱炭素に取り組むことが企業価値を上げる時代になってきたのだ。
企業の変化に押され、太陽光や風力などの再エネが伸びている。自然エネルギー財団によると、米国では再エネが広がり、昨年までの7年間で発電にともなう排出量が約23%減った。
「世の機運は高まっている。とてつもなく多くのよい変化が起きている」。アル・ゴア元米副大統領は映画「不都合な真実2 放置された地球」で、そう語った。脱炭素への流れは、もう逆戻りすることはない。
日本にも「芽」はある。
大手生保が石炭火力発電への新規の投融資をしないことを相次いで決めたほか、三つのメガバンクグループも石炭火力への融資を厳しくし始めた。RE100やSBTなどに参加し、ビジネスを低炭素型に切り替えようとする企業も現れている。
■30年先の日本の姿
こうした「芽」を育てるには政策による支援が欠かせない。しかし政府は旧態依然の政策から離れられないでいる。
たとえば7月に決めたエネルギー基本計画は石炭火力をベースロード電源とし、30年度に全体の26%という目標を維持した。「石炭火力は事業リスクが大きい」(中川雅治環境相)にもかかわらず約30の新設計画があるのは、国が脱石炭をめざしていないことと無縁ではない。
いまある技術をもとに考えても、30年以上先を見すえる戦略にはなりえない。むしろ野心的なビジョンと目標を掲げることで技術革新を生み、経済や社会を活性化させる。求められるのは、そんな好循環で日本を大胆に変える長期戦略である。
既存の政策にとらわれず、どれだけ具体的な内容を盛り込めるか。石炭火力からの段階的な撤退や再エネの拡大、電動車の普及などについて目標や工程表を明確にしたい。二酸化炭素の排出に課金するカーボンプライシングの導入や原発依存度を下げる道筋も示すべきだ。
関係省庁の意見を調整したり産業界に配慮したりするばかりでは、腰の引けた内容になってしまう。政治が国民の声に耳を傾け、慎重論や反対論を乗り越えていくしかない。
主要7カ国のうち長期戦略をもたないのは日本とイタリアだけだ。脱炭素の流れに乗る最後のチャンスと腹をくくり、思い切った戦略を打ち出したい。
(2018年8月20日の朝日新聞社説)
「石炭火力からの段階的な撤退や再エネの拡大、電動車の普及などについて目標や工程表を明確にしたい」のなら、カーボンプライシングは必要ないにもかかわらず、主権者の頭越しに「二酸化炭素の排出に課金するカーボンプライシングの導入や・・・慎重論や反対論を乗り越えていくしかない」と喚き立て続け、「石炭や石油への投資が回収不能になるのを避けるため、化石燃料からの投資撤退が広がっている。撤退を表明した企業や投資家の運用資産は660兆円を超えた。逆に、環境や社会などを重視する『ESG投資』が2500兆円に急増している」と囃し立て続け、そして、「原発依存度を下げる道筋も示すべきだ」と泣き喚き続けるのは、「一方では、一定量の生産諸力をむりに破壊することによって、他方では、あたらしい市場の獲得と古い市場のさらに徹底的な搾取によって」を明確に示している。
「アル・ゴア元米副大統領は映画『不都合な真実2 放置された地球』で、そう語った」はこれである。

2017年11月18日の朝日新聞土曜日朝刊の別刷り「be」より

2017年11月18日の朝日新聞土曜日朝刊の別刷り「be」より
第1部第7章で解説しているとおり、グリーンランドの氷河・氷床は大気汚染が原因で解けているにもかかわらず、尚も「(CO2の排出が原因で)氷河が解けゆくグリーンランド」。
第1部第14章の第3節で解説しているにもかかわらず、「(CO2の排出が原因で)大型台風に襲われたフィリピン」。
第1部第11章の第12節で解説しているにもかかわらず、「(CO2の排出が原因で)海面上昇で路上に水があふれ、魚が泳ぐ米フロリダ州」。
ひたすらに市民を欺き続けるのは、庶民=労働者階級からの収奪を強めて、投資家が富を肥やし続けるため。
第1節でも述べたとおり、価値は労働時間だけで決まる。
マルクス「資本論」、岩波文庫第一巻p75より
「脱炭素に取り組むことが企業価値を上げる時代になってきたのだ」とは、「脱炭素に取り組むことが投資家が庶民=労働者階級から毟り盗る価値を上げる時代になってきたのだ」ということに他ならず、そのために飼い犬のエア科学者に温暖化を煽り立てさせたのである。
だから、江守正多も朝日新聞のWEBRONZAでゴアを持て囃していた。
江守正多 国立環境研究所気候変動リスク評価研究室長
2017年11月10日
「ヒーロー企業にならないか?」
国連の気候変動交渉COP21が開催されているパリから、アル・ゴア元米副大統領が電話をかけ、アメリカの太陽光発電企業ソーラーシティのリンドン・ライブCEOをこんなふうに口説く。交渉で態度の固いインドを軟化させるため、ソーラーシティの太陽光発電技術をインドへ無償提供することを提案するシーンである。
ドキュメンタリー映画「不都合な真実2 放置された地球」が11月17日、日本で公開される。試写を見ながら筆者の脳裏に浮かんだのは、有名な「沈没船ジョーク」だ。
沈没船の船長が、乗客に海に飛び込むよう説得してまわる。まずアメリカ人のところに行き、「ヒーローになりたければ飛び込んでほしい」というとアメリカ人は飛び込む。ゴアのセリフは、可笑しいくらいこれとそっくりだ。ちなみにこのジョークは、イギリス人には「紳士ならば飛び込んでほしい」、ドイツ人には「これは規則だから飛び込んでほしい」という具合に続く。各国の国民性を皮肉っているのである。気候変動に立ち向かう姿を描く
映画は、2006年に上映された「不都合な真実」の続編であり、前作に続き、アメリカ元副大統領のアル・ゴアが気候変動問題に立ち向かうために世界を変えようと奮闘する姿を描いたドキュメンタリーである。
気候変動(ここでは「地球温暖化」と同じ意味で用いる)は、ご存知のとおり、人間活動に起因する二酸化炭素などの温室効果ガスの排出により、大気の温室効果が強まり、地球の平均気温が上昇する問題である。これに伴い、極端な気象の増加、氷床の融解、海面上昇、生態系の変化などが起き、人間社会に深刻な悪影響がもたらされることが懸念されており、その一部はすでに起き始めていると考えられる。
アル・ゴアは世界各地で講演活動を行い、この問題について人々にわかりやすく語るとともに、一緒に活動する人々を育て、「産業活動に伴う気候の変化が人類に深刻な悪影響をもたらす」という「真実」を「不都合」に思う人たちと戦ってきた。その戦いの歴史を振り返ってみると、あまりの浮き沈みの連続に改めてこの問題の困難さを実感できる。ゴアと世界の気候変動政策の栄光と挫折
20年前の1997年。京都で行われていた国連気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)に、当時アメリカ副大統領だったゴアが乗り込み、京都議定書の交渉を政治決着させた。ゴアのこの問題における最初の栄光の瞬間といえるだろう。
2000年、アメリカ大統領選の民主党候補になったゴアは、共和党候補のブッシュに僅差で敗れる(本当は勝っていたなどの話があるが、公式には敗北であることに変わりない)。ブッシュはアメリカ経済への悪影響を理由に京都議定書の批准を拒否。ゴアと気候変動政策にとっての大きな敗北となった。
2006年、政治家を引退して講演活動を続けていたゴアは、映画「不都合な真実」のスクリーンで人々の前に再び現れる。映画はアカデミー賞を受賞し、翌2007年にゴアは「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)とともにノーベル平和賞を受賞。この映画の効果で世界中の多くの人々が気候変動問題の認識を深めた。再び訪れたゴアの栄光である。(ただし、ゴアの影響でアメリカ国内においては気候変動政策が「リベラルのアジェンダ」とみなされ、社会における保守とリベラルの分断を深めたという批判もある)。
2008年には気候変動政策に積極的なオバマ大統領が誕生。2009年に京都議定書の次の枠組づくりを目指すコペンハーゲンでのCOP15に臨むが(日本では民主党政権が誕生し、鳩山首相が出席)、交渉は失敗におわる。ゴアに目立った出番は無かったが、世界の気候変動政策にとっては再び大きな挫折となった。
しかし、その後のCOPでも粘り強い議論が続けられ、仕切り直しとなった新しい枠組づくりの大舞台となったのが2015年、パリでのCOP21だ。ここで国際社会は歴史的なパリ協定の合意に成功する。パリ協定では、すべての国が対策に参加する形で、長期目標として世界の温室効果ガス排出量を今世紀中に正味でゼロにすること(本質的には「脱化石燃料」といってもよい)に合意したのだ。映画で描かれているように、ゴアにとっても三度目の栄光の瞬間である。
そして現在、アメリカではトランプ大統領が誕生し、パリ協定の離脱を表明した。国際的にはパリ協定の求心力が維持されているが、アメリカ国内においては、三度目の挫折の真っ只中といえるかもしれない。なんという目まぐるしさだろうか。パリ協定を可能にした世界の変化
しかし、これらの激しい浮き沈みの裏側で、変わらずに進行していた世界の変化が少なくとも3つあった。そのどれもが、パリ協定の合意をもたらした背景として重要なものだ。
一つめは、中国、インドなどの新興国の目覚ましい経済発展である。京都議定書の時代には、途上国は、これまで地球環境を汚しながら発展してきた先進国を非難し、自国の発展の権利を主張し、先進国にのみ対策を求める立場だった。ところが、今や中国、インドやこれから発展する他の国々も対策を行わなければ気候変動は止まらないことが次第に誰の目にも明らかになってきた。
二つめは、気候変動の進行と悪影響の発現である。大気中二酸化炭素濃度は増加の一途をたどり、2014年、2015年には世界平均気温が最高記録を顕著に更新した。アメリカでは2012年にニューヨークとニュージャージーを襲ったハリケーン・サンディーが気候変動の脅威をアメリカ国民に印象付けた。もちろん、個々の異常気象の原因を人間活動に求めることはできないが、気候変動が異常気象の頻度を上げ、威力を強めている可能性は高い。これに加えて、中国やインドなどでは深刻化した大気汚染への対策が化石燃料の利用を削減する大きな誘因となってきている。
そして三つめは、イノベーションによる対策技術の進歩である。再生可能エネルギーや蓄電池などのイノベーションが進み、価格の低下と導入量の伸びがおおかたの予想を大きく上回る速度で起きている。原理的には、再生可能エネルギーのコストが蓄電池などの安定化コストを含めて、化石燃料よりも安くなってしまえば、世界のエネルギー供給は一気に脱化石燃料にシフトしてもおかしくない。現時点ではまだ乗り越えるべき課題が多いが、将来そのようなシフトが実際に起きる可能性が、次第に現実味を増してきている。
途上国の象徴としてのインド
「不都合な真実2」で描かれているインド政府の交渉ポジションは、象徴的にこれらの変化を反映しているようにみえる。
映画で描かれているように、奇しくもCOP21の期間中にインドのチェンナイで大洪水が起きた。インドでは毎年のように熱波や洪水で多くの犠牲者が出ており、気候変動への危機感はもともと強かっただろう。しかし、チェンナイの洪水被害が象徴的にモディ首相をはじめインド政府のパリ協定合意への決意を新たにさせた効果はあったかもしれない。
・・・中略・・・
ゴアの希望と、パリ協定のパラダイムシフト
さて、アメリカ連邦政府の態度が気候変動問題に関して絶望的な状況にありながらも、現在のゴアはこの戦いの「勝利」に関して楽観的であり、希望に満ち溢れている。これはもちろん映画の大部分がトランプ政権誕生前の材料に依っているせいでもあろうが、ゴアの希望にはもっと確かな根拠があるように感じられる。
京都議定書とパリ協定ではパラダイムが変わった、ということがよく言われる。京都議定書の交渉は、負担の押し付け合いのゲームだった。しかし、パリ協定以降の世界は機会(チャンス)の取り合いのゲームに変わった。今世紀中に世界が脱化石燃料を目指す流れは定まり、その移行の過程をいかにリードし、その過程で生じるビジネスの機会をいかにものにしていくかという新たな競争が始まったのだ。
トランプ政権がパリ協定の離脱を表明しても、米国内の多くの大企業が再生可能エネルギー100%の目標を掲げ、気候変動対策に積極的に取り組んでいる事実が、雄弁にそのことを物語っている。
(「京都議定書からパリ協定へ アル・ゴアの20年」より。WEBRONZAは購読しないと「そして三つめは」以下が読めないけれど、コチラに全文転載されている。)
京都議定書の結果、かえってCO2排出は増したにもかかわらず、「20年前の1997年。京都で行われていた国連気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)に、当時アメリカ副大統領だったゴアが乗り込み、京都議定書の交渉を政治決着させた。ゴアのこの問題における最初の栄光の瞬間といえるだろう」と囃し立てるのは、第4章第2節で解説しているとおり、有機的構成が高い産業を労賃の低い支那に移転させて、般的利潤率低下を抑制するために京都議定書を結ばせたからに他ならず、江守正多らエア科学者が国際主義エリートの飼い犬であることを、自白している。
「試写を見ながら筆者の脳裏に浮かんだのは、有名な『沈没船ジョーク』だ・・・」と喚いているけれど、第1部第14章第4節で解説しているとおり、「アメリカでは2012年にニューヨークとニュージャージーを襲ったハリケーン・サンディーが気候変動の脅威をアメリカ国民に印象付けた」も、第1部第15章第21節で解説しているとおり、「映画で描かれているように、奇しくもCOP21の期間中にインドのチェンナイで大洪水が起きた。インドでは毎年のように熱波や洪水で多くの犠牲者が出ており、気候変動への危機感はもともと強かっただろう」も、第1部第13章第7節で解説しているとおり、「大気中二酸化炭素濃度は増加の一途をたどり、2014年、2015年には世界平均気温が最高記録を顕著に更新した」も、IPCCという「沈没船」が発する「SOSジョーク」に他ならない。
(第1部第14章第1節で解説しているとおり、2018年の西日本豪雨でも、CO2排出に因る気候変動と泣き喚き続けた。)
「これに伴い、極端な気象の増加、氷床の融解、海面上昇、生態系の変化などが起き、人間社会に深刻な悪影響がもたらされることが懸念されており」なら、全世界の全国家が、全市民が等しく、対策技術を共有し、機会を共有しなければならないはず。
「これに伴い、極端な気象の増加、氷床の融解、海面上昇、生態系の変化などが起き、人間社会に深刻な悪影響がもたらされることが懸念されており」と煽り立て、投資家が庶民=労働者階級からの収奪を強める「機会(チャンス)の取り合いのゲームに変わった」から、「パラダイムが変わった、ということがよく言われる」のだ。
国際主義エリートの飼い犬が、「これは国際主義エリート様の規則だから飛び込んでほしい」「国際主義エリート様に身も心も捧げるヒーローになりたければ飛び込んでほしい」「搾取を真摯に受け入れるならば飛び込んでほしい」、ワン、ワン、ワンと吠えているわけである。
第4章第6節で採り上げた2016年4月28日の紙面に見えるとおり、江守正多も朝日新聞とブルームバーグ様が開催したシンポジウムに招かれて登壇した。
「米国内の多くの大企業が再生可能エネルギー100%の目標を掲げ、気候変動対策に積極的に取り組んでいる事実が、雄弁にそのことを物語っている」と囃し立てるのは、「雄犬弁にそのことを物語っている」
だから、上の文章の最後では、こんな高言を吐いている。
冒頭の「沈没船ジョーク」のオチはこうだ。ほとんどみんなが飛び込んだ後、船長は最後に日本人のところにやってきて言う。「みんな飛び込んでいますよ。さあみなさんも……」
パリ協定の合意の半年ほど前、2015年6月に世界で一斉に行われた「世界市民会議」という社会調査によれば、世界平均では3分の2の人が「気候変動対策は生活の質を高める」と回答している一方、日本では3分の2が「気候変動対策は生活の質を脅かす」と回答した。日本では、気候変動対策に我慢、辛抱、負担のイメージがいまだに付きまとう。まず、この時代遅れな後ろ向きの感覚を、前向きに変えていこう。
そして、日本の政治やビジネスのリーダーは、どうか遠慮なく、新しい競争でいち早くチャンスをつかむために、脱化石燃料という挑戦の海原に果敢に飛び込んでいってほしい。ゲームのルールが変わっているのに、自分たちだけが古いルールに従ったまま苛烈な国際競争に参加しているとしたら…。そんな状況は、想像するだけで恐ろしいではないか。
(「京都議定書からパリ協定へ アル・ゴアの20年」より。上で述べたとおり、WEBRONZAでは購読しないと読めないけれど、コチラで読める。)
「パリ協定の合意の半年ほど前、2015年6月に世界で一斉に行われた『世界市民会議』という社会調査によれば・・・日本では3分の2が『気候変動対策は生活の質を脅かす』と回答した」はコレ。
「地球温暖化対策は生活の質を向上させる」と考える市民が、世界平均では66%に上るのに対し、日本では17%にとどまるとの意識調査結果が、11日閉幕した国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)の準備会合で報告された。温暖化への懸念は共通していても、対策が日常生活に与える影響への受け止めには市民レベルでも各国に差がある実態が浮かぶ。
調査は同条約事務局などが主催し、日本時間の6~7日、79カ国計100会場で計1万人を対象に実施。年齢、性別、職業などが各地域の縮図になる構成で各会場100人を集め、少人数で議論をした後、29の質問に答えた。日本では6日に東京都内で開かれた。
集計結果によると、温暖化の被害を「とても心配している」と回答したのは世界平均で79%。「ある程度心配している」も含めると、二酸化炭素(CO2)排出量が最も多い中国は89%で、日本、米国、インドはいずれも9割を超えた。2013年に巨大台風に襲われたフィリピンは100%だった。
「温暖化対策が生活の質を高める」と答えたのは、世界平均で66%。フランスは81%に達し、米中印も過半数を占めた。一方、日本は17%で、逆に対策が「生活の質を脅かす」と考える人が60%に上った。
現在の同条約では、中国やインドは「途上国」の位置づけで、課せられている責任が先進国と異なるが、今後もこの扱いを変えないことに日本で賛成したのは2%。インドも8%だったが、中国は28%で、途上国間でも傾向が分かれた。【大場あい】
(毎日新聞 2015年06月13日 東京朝刊)
「世界市民会議」と嘯いているけれど、「国連気候変動枠組み条約の事務局が主催し」た。
「年齢、性別、職業などが各地域の縮図になる構成」と嘯いているけれど、環境団体のメンバーが紛れ込み、「温暖化対策が生活の質を高める」という結論に誘導しようと図ったことは想像に難くない。
にもかかわらず、「対策が『生活の質を脅かす』と考える人が60%に上った」。
一般市民に質問すれば、「対策が『生活の質を脅かす』と考える人が97%に上った」であろう。
第1節で見たとおり「その意味するところを一般市民や政策決定者に説明しなければならない」と巧言したのだから、「日本では3分の2が『気候変動対策は生活の質を脅かす』と回答した」という事実を真摯に受け止め、今まで以上に「その意味するところを一般市民に説明」に努めねばならない、と言うかと思いきや、市民の頭越しに「日本の政治やビジネスのリーダーは、どうか遠慮なく」と言い放った。
なぜならば、第3章第2節でも指摘したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p377より
「この時代遅れな後ろ向きの感覚を、前向きに変えていこう」と言いながら、「日本の政治やビジネスのリーダーは、どうか遠慮なく」と喚き立てるのは、第1節でも説明したとおり、市民に背を向け、投資家の方を向いて、「前向き」と喚き立てていることを、江守正多らエア科学者が投資家の飼い犬に他ならないことを見事に表している。
だから、その後も、前向き、前向き、と喚き立てている。
(この後も、我慢と感じるな、と喚き続けている。)
しかし、こういう話をすると、「そりゃあ地球温暖化は止まった方がいいけど、そのためには我慢や負担がたいへんなんじゃないか」と思われる方もおそらく日本には多い。
「世界市民会議」の結果をもう一つ引用すると、「あなたにとって、気候変動対策はどのようなものですか」という問に対して、「多くの場合、生活の質を高めるものである」と答えた人が世界平均の66%に対して日本では17%、「多くの場合、生活の質を脅かすものである」と答えた人が世界平均の27%に対して日本は60%であった。つまり、日本では温暖化対策に対して後ろ向きの認識が強いのに対して、世界ではもっと前向きらしい。

World Wide Views on Climate and Energy (2015) より
もう一ついえば、京都議定書の時代からパリ協定の時代になり、パラダイムが変わったと解説している専門家がいる。京都議定書のころは、自国の排出削減は自国の経済の負担になるという認識で、各国は排出削減の負担をなるべく他国に押し付けようとした。一方、現在のパリ協定下の状況では、技術が変われば排出はどんどん減るという認識で、各国は技術の変化をいかに主導するかという競争を始めたというのだ。
世界では「脱炭素」に前向きに取り組むどころか、「脱炭素」に向かう競争を始めているのに対し、日本社会の大部分における認識は、未だ京都議定書のころのパラダイムに取り残されているのかもしれない。
8月3日に開かれた、地球温暖化対策の長期戦略を検討する政府の有識者会議の冒頭で、安倍首相が「温暖化対策はもはや企業にとってコストではなく、競争力の源泉だ」と述べたそうだ。筆者が上に述べた世界の認識と完全に一致する。
この発言のとおりに、政府と企業の姿勢にも本腰が入ることを願いたい。そして、今年の豪雨と猛暑をきっかけに、日本の多くの人々が「脱炭素」の必要性を実感し、世界で起きている温暖化対策のパラダイム転換にも目を向けてほしいと願っている。それは、人々の実感や理解の欠如が、日本が「脱炭素」に向かう競争を世界と戦う上での大きなハンデになってしまうことを懸念するからだ。
(「豪雨も猛暑も、地球温暖化が進む限り増え続けるという現実に目を向けよう(続編:ではどうすればよいか)」より)
第4章第9節で解説したとおり、欧米の累積排出量は我国の10倍。
欧米が「『脱炭素』に前向きに取り組む」ということは、その事実に向き合い累積排出責任をとること。
ところが、欧米の累積排出量に頬被りを決め込み、「世界では『脱炭素』に前向きに取り組むどころか、『脱炭素』に向かう競争を始めている」と囃し立てる。
それを正当化するために、「それは、人々の実感や理解の欠如が、日本が『脱炭素』に向かう競争を世界と戦う上での大きなハンデになってしまうことを懸念する」のだ。
投資家の方を向いて「前向き」と喚いていること、江守正多らエア科学者は投資家の飼い犬であり、庶民=労働者階級からの収奪を強めて投資家が富を肥やし続けるために温暖化を煽っていることを、見事に示しているではないか。
だから、これ以前にも、こんな高言を吐いていた。
科学と倫理は「点火」の段階でのみ必要なのであり、制度ができて経済にまで火が付けば、あとは勝手に燃え広がる。問題に無関心な人が多くいたとしても、彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう。
(「温暖化対策計画 2050年80%削減は可能? 『分煙革命』を参考に考える『脱炭素革命』の意味」より)
庶民=労働者階級のための「脱炭素革命」ならば、「社会のほとんどの人たちが問題に関心を持ち、科学的知見と倫理的規範を共有する必要が、必ずある」
ところが、第1節で見たとおり「そのためにどんな研究が必要かさえも、科学者は社会の様々な立場の人たちと一緒に考え、一緒に研究を進めていこうという姿勢が強調されている」と喚きながら、「社会のほとんどの人たちが問題に関心を持ち、科学的知見と倫理的規範を共有する必要は、必ずしも無い」と言い張る。
(もちろん、懐疑論者・否定論者の知見こそが「科学的知見」)
庶民=労働者階級のための「脱炭素革命」ならば、「社会のほとんどの人たち」の間に「燃え広がら」ねばならない。
ところが、「制度ができて経済にまで火が付けば、あとは勝手に燃え広がる。問題に無関心な人が多くいたとしても、彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と言い放つ。
前節で見たとおり、「この戦略全体を通じて、『国民』の存在感が希薄である印象を持ったことを指摘しておきたい。国民は、ビジネス主導のイノベーションに『巻き込まれる』存在であり、CCS等の技術を『受容する』ことが期待される存在であり、ライフスタイルを転換するように『啓発される』存在として登場する」と嘯いていたけれど、「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」ということは、やはり、国民は「『巻き込まれる』存在であり」、「『受容する』ことが期待される」どころか「『受容する』ことを強いられる存在」であることを、ハッキリと示している。
「脱炭素革命」は「支配階級の思想」。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p73より
国際主義エリートの投資家は自らの才覚で富を築き上げたと思い上がっているけれど、第1章で解説したとおり、全ては労働者階級が創り出した富。
第4章第1節でも引用したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p183より
「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と言い放つのは、彼ら庶民=労働者階級は搾取にいつのまにか従うようになるだけだろう、と高言することに他ならない。
国民の血税で生活しながら、「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と言い放ったのは、国際主義エリートの飼い犬であることを、国際主義エリートが庶民=労働者階級からの収奪を強めて富を肥やし続けるために、飼い犬に温暖化を煽り立てさせていることを、ハッキリと示している。
労働者が化石燃料という価値を産み出し、それを使ってさらに大きな価値を産み出したのを、貪り盗り続けてきたのは国際主義エリートの投資家なのだから、気候変動が事実なら、投資家を糾弾することが「倫理的規範」のはず。
けれど、国際主義エリートが収奪を強めるための温暖化プロパガンダだから、「社会のほとんどの人たちが問題に関心を持ち、倫理的規範を共有」されては困るので、「倫理的規範を共有する必要は、必ずしも無い」。
そこには、自分たちは庶民に優るから、優越する者に臣従するのが劣等な庶民の「倫理的規範」、劣等な庶民を臣従させるのが優越する者の「倫理的規範」という、破廉恥な思考が働いている。
マルクス「経済学・哲学草稿」、岩波文庫p154より
それゆえエア科学は真に道徳的な科学であり、なによりましてもっとも道徳的な科学なのである。
一片の「倫理的規範」も持ち合わせていないくせに、「大転換を起こすために社会のほとんどの人たちが問題に関心を持ち、科学的知見と倫理的規範を共有する必要は、必ずしも無い。科学と倫理は『点火』の段階でのみ必要なのであり」と吠え立てる、そのド畜生ぶりは見事としか言いようがない。
上では「国民の血税で生活しながら」と指弾したけれど、その俗っぽい表現を、もう少し科学的に、つまり、経済学的に考察してみよう。
江守正多らエア科学者は何も生産していないのだから、つまり、何らの価値も産み出していないのだから、彼らの生活は庶民=労働者階級が創造した剰余価値の上に成り立っている。
その意味では、庶民=労働者階級が創造した剰余価値を奪い盗っている投資家と共通点がある。
庶民=労働者階級のために尽くせば、庶民=労働者階級の創造した剰余価値が庶民=労働者階級の生活向上に資するから、投資家らとは異なり得るけれど、そのような「倫理的規範」が無ければ、投資家の飼い犬に成り下がる必然性を有しているのだ。
「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と言い放ったのは、その事実を明確に示している。
エンゲルス「共産党宣言英語版への序文」、岩波文庫「共産党宣言」p27より
「その時期の知的歴史」は科学や文学や芸術上の成果だけを意味しているのではない。
それらとは正反対の無知、野蛮も「その時期の知的歴史」を形成している。
「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」というような、知性の欠片もない放言も「その時期の知的歴史」の一面。
「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」という放言は、「経済的生産と交換の支配的な様式、およびそれから必然的に生れる社会組織」という「土台のうえに築かれ」ている。
投資家どもが現在の「経済的生産と交換の支配的な様式」であり、環境団体とIPCCは「それから必然的に生れる社会組織」。
「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と言い放ったのは、「脱炭素」は投資家が庶民=労働者階級へ仕掛けた戦いであることを、ハッキリと示している。
6.5 エクソン
前章第16節で解説したとおり、偉大なる国際主義エリートの投資家様が資本主義を止揚されるから、第4章第1節で紹介したとおり、投資家様がエクソンに脱炭素を要求した。
それに先だって、国際主義エリートは環境団体に命じ、飼い犬のエア科学者にお膳立てをさせていた。
だから、こんなことを書いている。
2007~2009年ごろの温暖化ブーム期には、「温暖化は怖い」という本と「温暖化はウソだ」という本が競って書店の棚にならんだ。その後、温暖化問題自体から世間の関心が離れるとともに懐疑論も下火になった印象だったが、昨年末のCOP21前後に報道が盛り上がるのを見て、懐疑論の方々もまた発言せねばという気になったのかもしれない。温暖化問題への関心が少し戻ってきた兆しの一つかもしれないと思えば、結構なことだ。
世界における温暖化懐疑論の社会的背景
日本では下火だった懐疑論も、米国などではそれなりにずっと顕在だったようだ。世界的には、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった英語圏で懐疑論が盛んであると聞く。その社会的な背景は大きく三つ挙げられるだろう。
一つは、温暖化対策が進むと利益を失う化石燃料企業による、温暖化対策の妨害である。このことは陰謀論めいて聞こえるので筆者はこれまで口にするのをはばかってきたが、今や実態解明が進み、懐疑論の多くはエクソン・モービルとコーク・ファミリー財団という化石燃料企業あるいはその関連組織が中心となって広められていることが、論文に堂々と書かれている。
特にエクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが最近の調査で明らかになり、大問題になっている。
(「温暖化懐疑論とぼちぼちつきあう」より)
・・・中略・・・
本当は、このことを指摘するのはあまり気が進まなかった。傍から見れば「お前はインチキだ。」「いや、そっちこそインチキだ。」という泥仕合になってしまうからである。
いくら気が進まなくても、筆者は一度この構図にあえて乗ってしまった以上、半端で済ませるわけにはいかない。今回ももう少しこれについて書きたい。
ここではまず、最近の論文を参照して、上記の引用の根拠を提示したい。
温暖化懐疑論・否定論活動の実態が研究対象になりはじめた
2015年2月に Nature Climate Change 誌に載った解説「Nature Climate Change,5(2015)
195」によれば、温暖化懐疑論・否定論について分析した論文が2010年ごろから増え始め、この時点までで200篇以上の論文が出版されている。
そして、COP21が始まった11月30日に Nature Climate Change 誌に出版された論文「Nature Climate Change,6(2016)370」はとりわけ興味深い。
米国イェール大学の社会学者である Justin Farrel は、懐疑論・否定論の活動を行っていると目される4,556人の個人と164の組織のネットワーク関係と資金の流れを分析した。さらに、1993年から2013年までに米国のメディアと政治で気候変動が言及された文書(口頭の言及の記録も含む)40,785を分析し、懐疑論・否定論活動から発信された情報との一致度を定量的に調べた。
その結果浮かび上がってきたのは、「エクソン・モービル」と「コークファミリー財団」という2つの資金提供者を中心としたネットワークの存在だ。そして、この2つから資金が流れている懐疑論・否定論活動はメディアと政治へ効果的に影響を及ぼすことに成功している(つまりは組織立った活動である)という関係性が明らかになった。
コークファミリー財団は日本人には馴染みが無いが、非上場全米第2位の企業であるエンジニアリング会社コーク・インダストリーを経営し、全米長者番付で5位と6位に入るコーク兄弟の持つ財団である。
筆者は論文中にあまりにもはっきりと2つの資金提供者が名指しされているのを見て少し驚いたが、米英等の関係者の間では周知の事実なのだろう。
この論文が冒頭の引用の前半部分(欧米の産業界の一部の意を汲むといわれる組織的な温暖化懐疑論・否定論活動の存在)の一つの有力な証拠である。
(「【COP21閉幕】温暖化への対処をみんなで議論する時代へ 異論を唱えるにも「懐疑論」は不要」)
第1部第5章第3節の [注2] で引用しているAERAに「IPCC第2次報告書(95年)の時点では、20世紀に入って気温が上昇傾向にあるかどうかについて、論議は尽くされていなかった。きちんとした気温測定のデータがあるのはせいぜい最近の200年ほどで、それ以前と比較できなかったからだ。それゆえ、マンたちのデータは画期的で、IPCCの主張の正当性を裏付けることになった」と記しているとおり、IPCCの人為的温暖化説(気候モデル)は専らホッケー・スティック曲線に依拠している。
だから、第1部第5章第5節の図5-25と [注2] で採り上げている2021年1月1日の朝日新聞朝刊第2面に見えるとおり、ホッケー・スティックを握り締めている。
けれど、70年代にホッケー・スティック曲線は存在しなかったのだから、「エクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していた」はずがなかろう。
IPCCの人為的温暖化説が正しいのなら、本当の自然科学者なら、「エクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していた」などと、何をバカなことを言っているのか!、と怒って然るべき。
ところが、あべこべに「対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが最近の調査で明らかになり、大問題になっている」と喚き立てる。
環境団体に調教されている犬畜生だから。
しかも、第1部第5章の図5-5、そして、第10章第4節の「熱帯太平洋『冷や水効果』 海水温低下で0.3度抑制」という記事のグラフに見えるとおり、20世紀第3四半期は気温が低下していた。
70年代に気候学者は氷河期の到来などと言っていた。
実際、日本気象学会の名誉会員(だから、我国の気象学に大きな貢献をした気象学者であろう)は、このように証言している。
「天気、56巻(2009年)」の533ページより
それなのに、「エクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していた」はずがなかろう。
しかも、第1部第13章第7節の図13-23に見えるとおり、70年代において、気候モデル(赤線)はデータを全く再現できない、箸にも棒にもかからない代物だったのだから、「エクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していた」はずがなかろう。
(第1部第16章第6節で紹介したとおり、「たとえば、過去100年の海面水温について調べると、1940年代の観測データに目立ったピークがあり、モデルの結果と合いませんでした」と告白していた。つまり、70年代のデータでは40年代の気温はもっと高かったのだ。)
第1部第13章で解説しているとおり、その後、エア科学者らは、赤線を上にずらし、エーロゾルで辻褄合わせを図ったけれど、それを正当化する論文は「1.5℃特別報告書」の後だから、「エクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していた」はずがなかろう。
本当の自然科学者なら、「エクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していた」などと、何をバカなことを言っているのか!、と怒って然るべき。
ところが、あべこべに「対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが最近の調査で明らかになり、大問題になっている」と喚き立てる。
環境団体に調教されている犬畜生であることを自白している。
「温暖化論争をフォローするうえでぜひ知っておいて頂かなければいけないことは、欧米の投資家の一部の意を汲むといわれる組織的な温暖化脅威論活動の存在である」!
「今や実態解明が進み、懐疑論の多くはエクソン・モービルとコーク・ファミリー財団という化石燃料企業あるいはその関連組織が中心となって広められていることが、論文に堂々と書かれている」けれど、第1部第12章の冒頭で採り上げている2013年10月2日の朝日新聞夕刊紙面が「温暖化に否定的な人たちが論拠の一つにしてきただけに、どう説明するのかにも注目が集まった」と記していたとおり、「2010年ごろから」懐疑論者・否定論者がハイエイタスを指摘し始め、「温暖化懐疑論・否定論について分析した論文が2010年ごろから増え始め」た。
そして、第1部第12章で解説しているとおり、第5次報告書でハイエイタスにしどろもどろの醜態を曝け出してしまい、「この時点までで200篇以上の論文が出版されている」。
ハイエイタスに窮したエア科学者がデータ改竄・捏造に奔って、ハイエイタスを消し去ると共に「米国イェール大学の社会学者である Justin Farrel は・・・懐疑論・否定論活動から発信された情報との一致度を定量的に調べた」。
「温暖化懐疑論・否定論」を攻撃することでエア科学を正当化しようと、「温暖化懐疑論・否定論について分析した論文が2010年ごろから増え始め、この時点までで200篇以上の論文が出版されている」、「米国イェール大学の社会学者である Justin Farrel は・・・懐疑論・否定論活動から発信された情報との一致度を定量的に調べた」のである。
第1節でも述べたとおり、1.5℃特別報告書でハイエイタスが消えてしまったことに知らんぷりを決め込み続けながら、「COP21が始まった11月30日に Nature Climate Change 誌に出版された論文はとりわけ興味深い」と喚き立てたのは、その事実をハッキリと示している。
「温暖化論争をフォローするうえでぜひ知っておいて頂かなければいけないことは、ダボスの意を汲むといわれる、温暖化懐疑論・否定論活動への組織的な懐疑論・否定論活動の存在である」!
上述の気象学会名誉会員も次のように述べていたが、
・・・中略・・・
ところで、我々はモデラーが言っていることに対しては明らかにおかしい場合は別だが、ほとんど口がきけない。要するにモデラーが何やっているかわからない。こういうふうにやったらこうなった、というような計算事実があるから彼らは強い。我々はおかしいと思っても、何もやっていないわけだから、論理的回路に照らしてどうも納得できないというだけである。例えば、最近異常気象が起こると温暖化の影響であるように言われることが多い。そうであるかもしれないが、断定できるほど簡単なものではない。異常気象の発生頻度・規模の統計が少し変わったといっても、気候が内因的に大きく複雑に変動する性質をもっていて、そのメカニズムも不明であるから、温暖化との関係云々には慎重を期すべきである。こうした問題に対しては、学会がその都度リーズナブルな共通見解をもって、必要に応じて外部に発信する態勢をととのえることが望ましい。今、気象界でモデラーとそれ以外の人の間に一つの亀裂が生じているように思われる。
「天気、56巻(2009年)」の533ページより
第1部第10章第3節と第4節で解説しているとおり、70年代の気温低下は自然変動の結果であり、それはハイエイタスに結びついている。
20世紀第4四半期の気温上昇には自然変動の寄与が大きいことを、IPCCがCO2の効果を著しく過大評価していることを示している。
ハイエイタスを消し去るためには、70年代の気温低下は不都合な真実だから、「特にエクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが最近の調査で明らかになり、大問題になっている」のだ。
第1部第16章第2節で紹介したとおり、ナオミ・オレスケスの著書を盾にして「身も蓋もなくいえば、気候変動政策を妨害するために、その基礎となる科学に対する不信感を人々に植え付ける効果を狙って意図的に展開されている言論活動があるということだ」と泣き喚いていたけれど、第1部第13章第1節と第4節と第6節で説明したとおり、気候学者でも気象学者でもないオレスケスがハイエイタス消去を先導した。
第1部第16章第5節で採り上げた「科学者が抗議集会 “トランプ大統領は科学重視を”」という見出しの記事に見えるとおり、気候学者でも気象学者でもないのに、「いま温暖化などを研究している科学者は正しいことをしているのに攻撃されている」と泣き喚いていた。
だから、やはり「特にエクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきた」と泣き喚いている。
2023.01.24 23:00
知ってたのは知ってたけど、ここまで知ってたのね…。
石油メジャー Exxon Mobil(エクソンモービル)は、40年以上前から気候変動がどれだけひどくなっていくかを、驚くほど正確に把握していたという研究結果「Science 379(2023)153」が発表されました。2015年の内部文書でエクソンの嘘が明らかに
2015年に Exxon Mobil の気候変動に関する内部文書を入手したジャーナリストたちの調査報道によって、同社の科学者による研究結果と対外的な広報活動の矛盾が明るみに出ました。Exxon Mobil が気候変動の科学的事実とその危険性を知りながら、気候変動を否定して世間を欺き続けたことを暴いた一連の報道は、「Exxon Knew」というキャッチフレーズとともに広まりました。Exxon Mobil の内部文書に関するその後の報道や研究は、同社が資金を提供して気候変動を否定するネガキャンを拡大させた経緯に焦点が当てられました。驚くほど正確だった70年代の温暖化予測
これまで Exxon Mobil 独自の気候変動予測が、外部の科学者によって分析されたことはありませんでした。今回Science に発表された研究で、Exxon Mobil の科学者によって40年以上前に構築された気候モデルとその予測の精度を分析したところ、びっくりするくらい正確だったそうです。研究の主執筆者でマイアミ大学の准教授であるGeoffrey Supran 氏は、次のように述べています。
”Exxon Mobil が知っていたことは以前から知っていました。『Exxon Knewバージョン2.0』とも言える今回の研究結果は、Exxon Mobil が何を知っていたかについて、統計を用いた正確な分析によって学術的にも興味深くて実用的な知見を与えてくれます。”
Twitter 上の仮説を定量的に検証
面白いのは、今回の研究が Twitter に端を発していることです。Supran 氏をはじめとする研究者が Exxon Mobil の内部文書に関する論文を発表した後、Twitter で科学者やユーザーが内部文書の予測グラフと実際の温暖化予測を重ねあわせて、Exxon Mobil の予測が正確であることを指摘し始めました。
Supran 氏は、これまで科学者らが Exxon Mobil の気候変動に関する言説を厳しく監視してきたにも関わらず、同社の気候予測やデータが実際に分析されていないことに気づいたそうで、今回の研究によって Twitter 上の仮説が査読済み論文という形になったと言います。
研究チームは、Exxon Mobil の科学者が作った気候変動予測とモデルをすべてとりまとめ、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が採用している2つの確立された分析方法によって定量的に検証し、予測能力の正確性に点数をつけて評価しました。
 Exxon Mobil による気温上昇予測(グレー)と観測結果(赤)。実線は Exxon Mobil の科学者による予測。破線は Exxon Mobil のデータを元に再現した予測。数字(1~12)は時系列で古い方から順番
Exxon Mobil による気温上昇予測(グレー)と観測結果(赤)。実線は Exxon Mobil の科学者による予測。破線は Exxon Mobil のデータを元に再現した予測。数字(1~12)は時系列で古い方から順番
その結果、1970年代後半から80年代前半にかけて、Exxon Mobil のモデルが温暖化を63%~83%の精度で「正確かつ適切に」予測していたことがわかりました。同社の気温上昇予測は、1970年から2007年までに作られた政府や科学者によるモデルの予測とほぼ同じだったそうです。実際のところ、Exxon Mobil のモデルは、最も著名な気候科学者の1人である元米航空宇宙局(NASA)の James Hansen 氏が、1988年にアメリカ連邦議会で証言する際に使用した有名なモデルよりもわずかに点数が高かったそうです。
Supran 氏は「地球温暖化の父」と呼ばれる Hansen 氏を引き合いに出したことについて以下のように弁明しています。
”文脈を伝えるのに役に立つと考えただけで、Hansen 氏を批判しているわけじゃないですよ。Exxon Mobil のモデルは、少なくとも史上最も影響力を持ち、評価も高い気候科学者の1人が作ったモデルに匹敵する精度だったという意味の称賛です。”
Exxon Mobil の科学者は、気温上昇だけじゃなく氷期が来るという言説を「的確に否定」し、人為的気候変動が顕著になる時期(2000年ごろ)を正確に予測、そして危険な温暖化を引き起こす二酸化炭素濃度を合理的に予測していたんです。40年以上前に。
誤情報の言い訳に躍起になる石油ガス企業
Exxon Mobil の内部文書がリークした2015年以降、同社や化石燃料産業による誤情報やあからさまな嘘に対する世間の風当たりは強くなってきました。また、気候変動を否定するネガキャンの片棒を担いだとして、アメリカの自治体が石油ガス企業を相手取って多くの訴訟を起こしています。
化石燃料産業はそれに対し、さまざまな方法で反論を試みています。最近だと、Chevron(シェブロン)が「1990年代にはマンガやテレビ番組で気候変動について言及されていたのだから、石油会社による気候変動否定を非難できないはず」と、法廷で意味不明な主張をしようとしました。Exxon Mobil は「Exxon Knew」を活動家グループによる組織的キャンペーンと主張し、公式サイトにわざわざ専用ページを設けて責任転嫁しようとしています。
Supran 氏は、自身が長年取り組んできた内部文書に記載されていた Exxon Mobil の予測の正確さに驚かされたと言います。
”Exxon Mobil の科学者が、気候変動についてただ漠然と何かを知っていたわけでも、お遊びでやっていたわけでもないことに息を呑みました。彼らは気候科学の発展に貢献していました。彼らは誰よりも多くのことを、そして間違いなく知るべきことを知っていたんです。”
もしも40年前に Exxon Mobil の予測に基づいて世界が気候変動対策に取り組んでいたら、私たちは今ごろどんな地球で暮らしていたのでしょうね。
(GIZMODE)
「お遊びでやっていたわけでもないことに息を呑みました」と泣き喚いているけれど、企業の研究者は利益に結びつかないような研究などしない。
企業は研究者にお遊びの研究などさせない。
そもそも、エクソンの研究者に気候の研究ができるはずもない。
エクソンが、何の利益にもならないのに、気候の研究者を雇うはずもない。
今なら、IPCCの非科学性を曝くために気候学者を雇うかもしれないけれど、1970年代にIPCCは存在しなかったのだから、気候の研究者を雇い入れる必要は全く無かった。
上で紹介したとおり、気候学者が氷期の到来を予測していた中で、エクソンがそれをわざわざ否定するために、または、それを追認するために、気候学者を雇い入れるはずもない。
「Exxon Mobil の科学者は、気温上昇だけじゃなく氷期が来るという言説を『的確に否定』し」と泣き喚くのは、「『Exxon Knew』は活動家グループによる組織的キャンペーン」に他ならないことを、見事に露呈している。
実際、この論文もどきに示されている「Exxon Mobil の内部文書」とやらを見ると、

図6-1 「Science 379(2023)153」の図1より
上で説明したとおり、70年代以前のデータを再現できていない。
そもそも、70年代におけるデータが記されていない。
黒線は第1部第13章第7節の図13-23の赤線と同じもので、気候モデルが無くても計算できるけれど、IPCC第3次報告書に掲載された評価式に基づいているのだから、70年代には知られていない。
70年代の内部文書に見せかけた捏造品。
「人為的気候変動が顕著になる時期(2000年ごろ)を正確に予測」と喚いているのは、上で指摘したとおり、ハイエイタスを消し去ったことを正当化するために、「Exxon Knew」と言い出したことを明確に示している。
この論文もどきの著者には、第1部第16章第3節の図16-5の論文の著者 Stefan Rahmstorf も名を連ねている。
Grant Foster の言いなりになっていたエア科学者。
第1節でも指摘したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第一巻p125より
「特にエクソン・モービルは社内では1970年代から人為起源温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが最近の調査で明らかになり、大問題になっている」というような小賢しさが、今日ある仲間で「科学」の名で流行するというようなことを妨げないのである。
IPCC学派ほどに、「科学」という言葉を乱用した学派はかつてなかった。
まさに概念の欠けているところに、言葉がうまく間に合うようにやって来るものなのだ!
6.6 ダボス様の組織的な温暖化プロパガンダにご用心
だから、その後も喚き立てている。
人間活動を原因とする地球温暖化、気候変動をめぐっては、その科学や政策を妨害するための組織的な懐疑論・否定論のプロパガンダ活動が、英語圏を中心に活発に行われてきたことが知られている。
米国の科学史家ナオミ・オレスケスらによる「世界を騙し続ける科学者たち」(原題:Merchants of Doubt) にその実態が詳しく記されている。タバコ、オゾンホール、地球温暖化といった問題に共通して、規制を妨害する側の戦略は、科学への疑いを作り出し、人々に「科学がまだ論争状態にある」と思わせることだ(manufactured controversy) 。そこでは、規制を嫌う企業が保守系シンクタンクに出資し、そこに繋がりを持った非主流派の科学者が懐疑論・否定論を展開し、保守系メディアがそれを社会に拡散している。
他にも社会科学者がこの問題について実態解明を進めており、2015年に Nature Climate Change に掲載された論文では、懐疑論・否定論の多くはエクソン・モービルとコーク・ファミリー財団という化石燃料企業やその関連組織が中心となって広められていることがネットワーク分析により明らかになっている。
化石燃料企業の経営の視点から見れば、温室効果ガスの排出規制等が政策として導入されれば収益に著しい損失をもたらすのだから、それを妨害するためであればプロパガンダ活動に相当の出資をしても見合うというのが「合理的な」判断かもしれない。
しかし、気候変動の危機の認識が社会において主流となってきた現在では、そのような妨害活動の実態を暴かれることが、企業にとって大きなレピュテーションリスクや訴訟リスクとして跳ね返ることになり、損得勘定は以前と変わってきているだろう。エクソン・モービルは、1970年代から人間活動による温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが明らかになり、複数の訴訟を起こされている。
日本における懐疑論・否定論
筆者は2007-2009年ごろの地球温暖化が社会的関心を集めた時期に、温暖化懐疑論・否定論とずいぶん議論する機会をもった。筆者の当時からの認識としては、日本国内において英語圏の資本による組織的な懐疑論・否定論プロパガンダの影響は小さいと思っていた。
日本では、懐疑論・否定論に同調的な産業界寄りの論客がたまに現れるものの、エネルギー産業や鉄鋼業などの企業も、組織としては気候変動の科学をIPCCに基づき理解しようと努めており、規制に対抗するにしても、科学論争ではなく政策論争を争点としているようにみえた。
これまでに筆者が議論した懐疑論・否定論の論客(多くは気候科学以外を専門とする大学教授) も、英語圏の懐疑論・否定論をよく引用するものの、筆者個人の印象では、英語圏の資本による組織的なプロパガンダとはつながっていないようにみえた。
GWPFの記事を組織的に紹介?
そのため、国際環境経済研究所(IEEI)のウェブページ で、Global Warming Policy Foundation(GWPF)の記事が系統的に紹介されているのを知った際には、身構えざるを得なかった。
GWPFについて、筆者は断定的な論評を避けるが、ネットを検索して出てくる情報 は以下のようなものである。
● 気候変動否定論者である Nigel Lawson(英国サッチャー政権の財務大臣)が2009年に設立した英国に本拠を置く気候懐疑論シンクタンク。
● 教育的慈善団体として登録されていたが、英国政府の慈善委員会から、教育的というより特定の政治的主張を行っているという疑義を呈された。
● 出資者の情報を公開することを頑なに拒否しており、化石燃料業界との関係を否定していた。しかし、2014年に、化石燃料業界からの出資を受けている自由市場主義シンクタンク Institute of Economic Affairs とつながりがある2名の個人(Neil Record、Nigel Vinson)からの出資が明らかになった。
IEEIに掲載されているGWPFの記事は、どれも評論家・翻訳家の山形浩生氏により邦訳されており、気候変動に関する記事のすべてにキャノングローバル戦略研究所の杉山大志氏の解説が付されている。
内容はどこがおかしいのか?
筆者はすべての記事に目を通してはいないが、たまたま読むことになった「熱帯の空:気候危機論への反証」 という記事について、少し詳しく紹介したい。記事の主張は、地球温暖化の予測シミュレーションに用いられる気候モデルが、人工衛星による観測データと比較して、過去の対流圏(地表から数キロ上空)の気温上昇を大幅に過大評価している、というものだ。
原著者のジョン・クリスティ氏は米国の気候科学者であり、記事の内容は査読論文(Christy et al., 2018 など)に基づいているので、一見すると正当な科学的主張のようにみえる。しかし、筆者が詳しく読んだところ、以下のような問題があった。
1.観測データについては論文に詳しく論じられているが、モデルと観測の比較については方法論の記述がほとんどない。
2.同じ問題についてモデルと観測を詳細に比較した論文(Santer et al., 2017)が1年前に出ており、モデルに本質的な問題があるとはいえないと結論しているが、Christy et al., 2018 はこの論文を参照していない。
3.モデルと観測の比較のグラフ(当該論文の図7)の描き方が恣意的である。違いが大きくみえるように始点を決めている。
4.IPCCの図(当該論文の図9)の引用の仕方が恣意的である。モデルと観測が合わない期間のみ引用している(IPCCの本文中には、モデルと観測がより整合する期間の図がある)。
3について、具体的には以下の図で、1982-1997において、モデル(ピンク)の幅の中心は、観測データ(青)とほぼ同じ動きをしているが、観測データがモデルの幅の下端に沿って描かれているため、その後の違いが強調されるような不自然な図になっている。
クリスティ氏はリモートセンシングなどご自身の専門分野では立派な研究者なのかもしれないが、気候変動の理解や予測をめぐっては何等かの理由で主流の科学に反発する立場になったようだ。組織的な地球温暖化懐疑論・否定論活動は、そういった微妙な立場の専門家をプロパガンダ活動に取り込んでいく。
IPCC「1.5℃報告書」の欠陥?
他には、アイルランドの気象学者レイ・ベイツ氏による「IPCC『1.5℃報告書』の欠陥」 という記事が筆者の周囲で話題になった。ベイツ氏は、GWPFと同様の目的を持つアイルランドの組織ICSFの創設者の一人であり、気候変動の科学の主流に対して長年「逆張り」をしてきた方のようだ。
この記事では、人間活動を原因とする過去の気温上昇量について「1.5℃報告書」が2013-2014年に出版されたIPCC第5次評価報告書に比べて科学的な厳密性を損ねているという主張のほか、気候モデルの不確実性等について以前からよくある議論が述べられている。
この記事について、「1.5℃報告書」の執筆者の一人であるIGESの甲斐沼美紀子氏が他の執筆者に尋ねたところ、過去の気温上昇量については「1.5℃報告書」と第5次報告書は完全に整合的であること、記事には特に目新しい知見は無いので学術論文として出版されない限りは相手にしないほうがよいこと、などの回答を得ている。
なお、杉山大志氏も「1.5℃報告書」の執筆者の一人であるが、「IPCCの1.5度特別報告書は、その科学的知見の取り扱いについて、重大な欠陥があったと指摘する論文」と、否定も肯定もせずに受け入れるような短い解説をつけている。
懐疑論・否定論のリスク
温暖化懐疑論・否定論は主流の科学との議論に勝つ必要はなく、「なにやら論争状態にあるらしい」と世間に思わせることができれば成功なのであるから、それに反論する活動に比べると圧倒的にノーリスクで有利な、「言ったもん勝ち」の面がある。
一方、世間がそのようなプロパガンダ活動の存在を知れば、ある組織がその活動に関わっていると世間から見られることは、組織の評判を毀損するレピュテーションリスクになるだろう。懐疑論・否定論を見る側も、見せる側も、そのことをよく理解してほしいと思う。
最後に、この記事を寄稿させてくださったIEEIのオープンな姿勢に敬意を表し、心より感謝を申し上げる。
「1982-1997において、モデル(ピンク)の幅の中心は、観測データ(青)とほぼ同じ動きをしている」と言い張っているけれど、どこをどう見れば「同じ動き」に見えるのか。
「違いが大きくみえるように始点を決めている」と泣き喚いているけれど、「始点」は「モデル(ピンク)の幅の中心」よりもやや上に位置している。
中心に置けば、「1982-1997において、観測データがモデルの幅の下端に沿って描かれる」ことになる。
「違いが大きくみえるように始点を決めると」、つまり、モデル(ピンク)の幅の下端から始めると、観測データとモデルの差はさらに大きくなる。
たとえ「1982-1997において、モデル(ピンク)の幅の中心は、観測データ(青)とほぼ同じ動きをしている」としても、1998年以降の違いは明白であり、やはり、ハイエイタスの存在を、気候モデルの破綻を明確に示している。
にもかかわらず、「モデルと観測の比較については方法論の記述がほとんどない」、「モデルと観測が合わない期間のみ引用している」「その後の違いが強調されるような不自然な図になっている」と泣き喚くのは、「懐疑論・否定論活動に比べると圧倒的にノー天気で有利な、『アホを言ったもん勝ち』の面がある」。
「熱帯の空:気候危機論への反証」には「青い帯は、追加の温室ガス強制をすべて除いたものです。驚いたことに、こうしたモデルの試行は実際の結果をかなりうまく予測していますが、これは報告書の本文では一切触れられませんでした」と書いてある。
しかも、「熱帯の空:気候危機論への反証」(の図7の下の文章)を読めば分かるとおり、「IPCCの図(図9)」は、ジョン・クリスティに批判されて、後から挿入したグラフ。
「IPCCの図(図9)の引用の仕方が恣意的である」と泣き喚くのは、やはり「懐疑論・否定論活動に比べると圧倒的にノー天気で有利な、『アホを言ったもん勝ち』の面がある」。
「同じ問題についてモデルと観測を詳細に比較した論文(Santer et al., 2017)が1年前に出ており」は、第1部第13章第7節 [注6] で採り上げている図13-38の論文。
筆頭著者の Benjamin Santer は第1部第10章第6節の図10-16の論文の筆頭著者。
その論文では、温暖化を煽ったつもりが逆に気候モデルの非科学性を曝くことになってしまったので、RSS3をRSS4に変えて、「モデルに本質的な問題があるとはいえないと結論している」けれど、第1部第13章第7節の [注1] の図13-36に見えるとおり、RSS4は「1982-1997において、RSS3とほぼ同じ動きをしているが、その後の違いが強調されるような不自然な図になっている」。
「組織的な地球温暖化懐疑論・否定論活動は、そういった微妙な立場の専門家をプロパガンダ活動に取り込んでいく」と泣き喚いているけれど、実際には、「組織的な地球温暖化脅威論活動は、微妙な立場のRSSの連中をプロパガンダ活動に取り込んでいく」。
三下が「クリスティ氏はリモートセンシングなどご自身の専門分野では立派な研究者なのかもしれないが」などと放言しているが、人工衛星による観測を創始したのはクリスティとスペンサーであり、その卓越した功績は気候学者で知らぬ者はいない。
にもかかわらず、「組織的な地球温暖化懐疑論・否定論活動は、そういった微妙な立場の専門家をプロパガンダ活動に取り込んでいく」と泣き喚いたのは、彼らのデータを排除したいからに他ならず、ハイエイタスを消し去るためにRSSを取り込んだことを、ハッキリと示している。
しかも、「Santer et al., 2017」を真に受けたとしても、「1982-1997において」も、その後も気温上昇はモデルの方が急激。
「モデルに本質的な問題があるとはいえないと結論しているが、Christy et al., 2018 はこの論文を参照していない」と言い張り、「その後の違いが強調されるような不自然な図になっている」と泣き喚くのは、「懐疑論・否定論活動に比べると圧倒的にノー天気で有利な、『アホを言ったもん勝ち』の面がある」。
第1部第10章第1節で解説しているとおり、気温上昇が17年間滞らない限り、「地球温暖化の予測シミュレーションに用いられる気候モデルが、CO2の効果を大幅に過大評価している」とは言えない、と泣き喚いていた。
その筆頭著者も Benjamin Santer だが、第1部第13章第5節で解説しているとおり、17年目の2014年も停滞が続いたので、第1部第13章第6節で解説しているとおり、2015年からは本腰を入れてデータを改竄し、ハイエイタスは無かったと言い出した。
と同時に、「2015年に Nature Climate Change に掲載された論文では、懐疑論・否定論の多くはエクソン・モービルとコーク・ファミリー財団という化石燃料企業やその関連組織が中心となって広められていることがネットワーク分析により明らかになっている」のである。
「アイルランドの気象学者レイ・ベイツ氏による『IPCC《1.5℃報告書》の欠陥』という記事」も「SR1.5は人工衛星の観測した温度トレンドについては触れず、なぜそれがGMSTとこれほど大幅にちがっているのかという問題にも触れない。これは深刻な欠陥だ」と批判している。
だから、「相手にしないほうがよいこと、などの回答を得ている」。
皆でハイエイタスを無かったことにしましょう、というのである。
「この記事について、『1.5℃報告書』の執筆者の一人であるIGESの甲斐沼美紀子氏が他の執筆者に尋ねた」らしいが、朝日新聞もそのババアに喚かせている。
第5次報告書がハイエイタスを認めて、しどろもどろの醜態を曝け出してしまったので、「1.5℃報告書」でハイエイタスを消し去ってしまったにもかかわらず、「『1.5℃報告書』と第5次報告書は完全に整合的である」と喚き立てるのは、そして、「『1.5度特別報告書は気候変動対策の緊急性を浮き彫りにした・・・重要な科学的情報を提供した』と話す」のは、「懐疑論・否定論活動に比べると圧倒的にノー天気で有利な、『アホを言ったもん勝ち』の面がある」。
だから、第1部第14章第3節と第4節で解説しているにもかかわらず、こんなことを喚いている。
「甲斐沼さんは海面水温の図を示し、『人間活動が原因で増えた熱の90%以上が海に蓄えられる。水温を上げないことが必要』と指摘した」けれど、「アイルランドの気象学者レイ・ベイツ氏による『IPCC≪1.5℃報告書≫の欠陥』 という記事」には、海洋貯熱量のデータが掲載されていた。
 図6-2 「IPCC『1.5度報告書』の欠陥」より(元論文は「Journal of Advances in Modeling Earth Systems,10(2018)1172」)
図6-2 「IPCC『1.5度報告書』の欠陥」より(元論文は「Journal of Advances in Modeling Earth Systems,10(2018)1172」)
CO2排出は20世紀後半に激増したのだから、「人間活動が原因で増えた熱の90%以上が海に蓄えられる」なら、2010年の海洋熱量は1950年の海洋熱量よりもずっと高いはずだが、同じ。
第1部第16章第6節で解説しているとおり、「一方モデルは過去の計算をし直すことができます。実際にモデルと観測結果が合わなくて観測データが見直された例があります・・・1940年代の観測データに目立ったピークがあり、モデルの結果と合いませんでした・・・その補正をしていなかったため、擬似的なピークが出てしまったということです。そういう問題がのちにわかったので補正すると、モデルが再現した過去の温度に近くなったのです」と喚き立てていたけれど、気候モデルが正しいと見せかけるためにデータを改竄・捏造したことが裏づけられた。
レイ・ベイツは「こうした結果は、重要な Laloyaux et al. 論文が採録の締め切りよりはるか前に刊行が承認されていたにもかかわらず、SR1.5で参照されていない」と糾弾している。
「記事には特に目新しい知見は無いので学術論文として出版されない限りは相手にしないほうがよい」と喚き立て、「甲斐沼さんは海面水温の図を示し、『人間活動が原因で増えた熱の90%以上が海に蓄えられる。水温を上げないことが必要』と指摘した」のは、「懐疑論・否定論活動に比べると圧倒的にノー天気で有利な、『アホを言ったもん勝ち』の面がある」。
第1部第14章第3節の図14-19に見えるとおり、CO2排出と台風に因果関係は認められない。
しかし、その後、その論文の著者の一人は朝日新聞紙上で、CO2排出で台風が強まった、と泣き喚いていた。
江守正多らは温暖化プロパガンダに与しない研究者を攻撃し続けてきた。
「組織的な地球温暖化懐疑論・否定論活動は、そういった微妙な立場の専門家をプロパガンダ活動に取り込んでいく」と泣き喚き、「気候変動の科学の主流に対して長年『逆張り』をしてきた方のようだ」と罵ったのは、その事実を示して余りある。
クリスティのように圧倒的な業績を誇る研究者でないかぎり、研究としての矜持を投げ捨てなければ、そのポストから追い落とされる。[注1]
上の紙面は「組織的な地球温暖化脅威論活動は、そういった微妙な立場の専門家をプロパガンダ活動に取り込んでいく」ことを明確に示している。
図6-2は、70年代の気温低下を、それ以降の気温上昇には自然変動の寄与が大きいことを裏づけている。
IPCCがデータを改竄してハイエイタスを消し去ったことを裏づけている。
その事実を覆い隠すために、「エクソン・モービルは、1970年代から人間活動による温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化は不確かという立場をとり続けてきたことが明らかになり」と言い立てて、「複数の訴訟を起こされている」
データ改竄に奔ってまで温暖化を煽り立てるのは、国際主義エリートの投資家が庶民=労働者階級からの収奪を強めて富を肥やし続けるため。
マルクス「資本論」、岩波文庫第六巻p397より
第5次報告書がハイエイタスを認め、しどろもどろの醜態を曝け出していたにもかかわらず、甲斐沼美紀子はこんなことをしていた。
2013.11.19 09:36
地球温暖化の影響を最小限にするためには二酸化炭素(CO2)の回収設備を持たない石炭火力発電所の新設は行うべきではないとの声明を世界各国の科学者27人がまとめ、気候変動枠組み条約第19回締約国会議(COP19)が開催中のワルシャワで18日発表した。
日本からは地球環境戦略研究機関の西岡秀三研究顧問と国立環境研究所の甲斐沼美紀子フェローの2人が署名した。東京電力福島第1原発事故後の日本では、発電コストは安いがCO2排出量が多い石炭火力発電所の新設を進める動きが電力会社などに目立つ。
15日に温室効果ガス排出削減目標を引き下げた理由も、発電部門の排出増が見込まれることが理由の一つで、日本にとっても耳の痛い指摘だ。声明は「石炭火力は最も効率のよいものでも1キロワット時の発電で天然ガスの2倍以上のCO2を排出する」と指摘。CO2を回収し地中に閉じ込める設備を持たない石炭火力発電所は、気温上昇を2度未満に抑えるとの国際目標と「整合性がない」とした。
(共同)
その後も喚き続け、朝日新聞が囃し立てている。
エクソンに訴訟を起こしているのは、もちろん環境団体。
江守正多らエア科学者は国際主義エリートの投資家の飼い犬で、環境団体に調教されているから、「国際環境経済研究所(IEEI)のウェブページ で、Global Warming Policy Foundation(GWPF)の記事が系統的に紹介されているのを知った際には、身構えざるを得なかった」。
飼い犬だから、「組織的な地球温暖化脅威論活動は、そういった微妙な立場の専門家をプロパガンダ活動に取り込んでいく」「気候変動の科学の主流に対して長年『逆張り』をしてきた方のようだ」と泣き喚くのだ。
[注1] 第1部第16章第2節で見たとおり、ホッケー・スティック曲線をでっち上げたマイケル・マンは「科学の否定は民主主義の否定だ」「科学との戦争はやめよ」と喚き立てていたけれど、その最中に、クリスティの研究室に銃弾が打ち込まれた。
(コチラを参照。)
江守正多らエア科学者の攻撃ではびくともしないので、命がなくなるぞと脅して「取り込もう」と図ったのである。
6.7 宗教
江守正多らエア科学者は懐疑論・否定論者に完膚なきまでに叩きのめされ、ダボスのために温暖化を煽り立てていることを露呈してしまった。
エンゲルス「空想より科学へ」、岩波文庫p126より
「人民を道徳的手段によって制御するしかなかった」から、第1節と4節で見たとおり、前向き、前向きと喚き立て、倫理的規範と言い放った。
「そして大衆にはたらきかけるあらゆる道徳的手段のうちで、第一に重要なものは宗教で、宗教以外には何もなかった」から、
2015年6月19日07時52分
ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王は18日、環境問題に特化した公文書を発表し、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出、海洋の酸性化といった環境汚染が続けば、「今世紀は並々ならぬ気候変動と空前の生態系破壊を目撃することになる」と警鐘を鳴らした。
法王は、道徳や教義への法王の立場を示す公文書「回勅」の中で、「数々の科学研究が、ここ数十年の地球温暖化の原因は主に人間活動の結果排出される温室効果ガスの濃縮によるものだと示している」と指摘。温室効果ガスを排出し続けて経済成長を遂げた先進国が、貧困の克服や社会の発展を目指す途上国の温暖化対策に技術などで協力するよう呼びかけた。一方、二酸化炭素の排出量取引については、現状が必要とする「根本的な変化」につながらず、過度の消費を維持したい国々の策略に使われかねないと指摘した。
温暖化対策を巡っては、年末にパリで開かれる国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で、京都議定書に続く新しい枠組みで合意できるかが焦点。カトリック信者は12億人おり、法王の呼びかけが、カギとなる途上国の動きに影響を与えるか注目される。(アテネ=山尾有紀恵)
(朝日新聞デジタル)
江守正多はこれを盾に喚き立てた。
(「それでも寒冷化が正しいと思っている方へ 世界でも撤退が目立つ温暖化科学への懐疑論」より)
「ローマ法王が地球温暖化の重大性を大々的に認め、温暖化を止めるための文化的革命まで世界人類によびかけてしまったものだから」、「他の様々な世界宗教からも、宗教指導者による気候宣言が出されている」と喚き立てるのは、我々は宗教により支えられているのだ、と言うことに他ならないが、「キリスト教原理主義の宗教保守により支えられてきた」と泣き喚いた直ぐ後で、そんなことを言うのだから、呆れ返った阿呆である。
「宗教以外には何もなかった」ことを見事に自白して「しまった」のだ。
しかも、ローマ法王を誘い出したのはハンス・シェルンフーバー。
(「『脱炭素』は、産業革命か、共産主義革命か」より)
第1節で見たとおり、「その意味するところを一般市民や政策決定者に説明しなければならない」と嘯いていたけれど、「その意味するところ」は無かったことを、露呈してしまった。
第4節で見たとおり、主権者である国民を見下して、「日本の政治やビジネスのリーダーは、どうか遠慮なく、新しい競争でいち早くチャンスをつかむために、脱化石燃料という挑戦の海原に果敢に飛び込んでいってほしい」、「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と言い放った。
エンゲルス「空想より科学へ」、岩波文庫p40より
誰が指導や支配をやるべきなのか?
江守正多らによれば、それはエア科学と投資家だ。
この両者が新しい人為的温暖化教で結びあえば宗教改革以来破壊されていた宗教思想の統一が復興され、それは必然に抑圧的で搾取可能な社会主義的な『新キリスト教』となるはずであった。
だから、こんなことを書いている。
保守的なキリスト教徒たちに向けた、キャサリン・ヘイホーの気候変動の講演が、科学と宗教の対立をどのように解きほぐしていくのかは、ぜひ本編をご覧頂きたい。
(「米国のドキュメンタリー番組が描く気候変動と社会」より。これも購読しないと一部しか読めないけれど、コチラに転載されている。)
「『新キリスト教』となるはず」だから、「気温計は敬虔なキリスト教徒でも保守的なキリスト教徒でもない」にもかかわらず、「敬虔なキリスト教徒であると同時に気候科学者である」、「彼女の夫は牧師だ。夫はこう語る。『私は敬虔なキリスト教徒だし』」と囃し立てている。
しかし、
エンゲルス「空想より科学へ」、岩波文庫p128より
「宗教的教義のうちには全くない」にもかかわらず、「科学と宗教の対立を解きほぐしていく」と喚き立てるのは、江守正多らが「超自然的啓示を信ずる」ことを示している。
だから、「自然的啓示」であるハイエイタスを消し去った。
第1部第13章の第7節で紹介しているとおり、キャサリン・ヘイホーも「温暖化が止まったという見方は科学者の間では完全に否定されている」と泣き喚いていた。[注1]
だから、「キャサリン・ヘイホーの気候変動の講演が、科学と宗教の対立をどのように解きほぐしていくのかは、ぜひ本編をご覧頂きたい」のだ。
第1部第16章第1節でも解説しているとおり、「97%の合意」と喚き立てているけれど、「宗教的教義」ゆえの「97%の合意」。
(「PNAS,107(2010)12107」の「abstract」より)
欧米帝国主義の精神的背景はキリスト教だった。
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p398より
気温上昇は偏にCO2が原因という「教義」に基づく「脱炭素」は、帝国主義の最高の段階としての社会主義≡脱炭素社会主義であり、すなわち、キリスト教植民制度。
だから、「政治やビジネスのリーダーは、どうか遠慮なく、新しい競争でいち早くチャンスをつかむために、脱化石燃料という挑戦の海原に果敢に飛び込んでいってほしい」、「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」というような、「いかに粗野で、蒙昧、無情で、無恥な人種にあってもその比を見ない」放言と高言を吐いたのだ。
エンゲルス「空想より科学へ」、岩波文庫p40-41より
江守正多らが特に強く、いついかなるところでも、まず第一に自分の心にかかるものは「最も少数で最も富裕な階級」の運命だといったのである。
[注1] だから、キャサリン・ヘイホーも、Dana Nuccitelli の指導下に、懐疑論・否定論者を攻撃する論文(もどき)「Theoretical and Applied Climatology,126 (2016)699」を書いている。
6.8 グレた娘
前章で解説したとおり、環境団体は「グレた」娘を担ぎ出し、国際主義エリートにお目通りさせた。
国連で泣き喚かせる前に、IPCCの副議長とも面会させた。
2019年8月9日 10:51 発信地:ジュネーブ/スイス
国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は8日発表した土地利用と気候変動に関する報告で、炭素排出を削減し、持続不可能な農業や森林伐採を止めない限り、食料安全保障確保と地球温暖化抑制という2つの取り組みの衝突は、今後数十年でますます厳しいものになると指摘した。
IPCCは、人類の暮らしの基盤である土地の利用方法を迅速かつ全面的に変革しなければ、気温上昇の抑制と並行し、今世紀半ばまでに100億人に達する世界人口の食料確保という取り組みは崩壊しかねないと警告した。
報告は、将来の温暖化に対する防壁として、現存する熱帯雨林を保護する必要性に焦点を当てる一方、惨事を避けるための対策の柱となるのは炭素排出の削減だと強調。植林とバイオ燃料の普及によって人間由来の環境上の損失を相殺できるという期待には冷水を浴びせた。
IPCCはまた、気候変動の緩和を目的とする土地利用により、トレードオフが相次ぎ生じようとしていることを指摘。膨大な炭素吸収源である森林を再生すれば気温上昇は抑制されるが、工業型農業が多くの土地を使用している現在、その余地は限られている。また、バイオ燃料となる植物の栽培には、炭素隔離の手段として潜在力があるが、そのための土地は農地や牧草地、森林から転用しなければならない。
報告は、バイオ燃料計画に「限定的」に土地を割り当てることで、気候上の実際の利益はもたらされ得るとする一方、大気中の二酸化炭素を年間数十億トン削減するのに必要な規模でバイオ燃料を栽培すれば、「砂漠化、土壌劣化、食料安全保障、持続可能な開発のリスクを増大させかねない」と警告した。
報告は1000ページに及び、現在の食料供給システムと、それによる悪影響を掘り下げている。
食料供給と二酸化炭素排出の関係をめぐっては、肉消費を抑制すべきか否かで議論がある。IPCCは報告の要約で、この問題にほとんど触れなかったが、「植物性の食料」には利点があり、世界での二酸化炭素排出を軽減させる力があると強調した。
 スイス・ジュネーブで、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の副議長と握手をするスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(2019年8月8日撮影)。(c)FABRICE COFFRINI / AFP
スイス・ジュネーブで、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の副議長と握手をするスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(2019年8月8日撮影)。(c)FABRICE COFFRINI / AFP
(AFP/Patrick GALEY)
IPCCの面々が本当の科学者なら、IPCCの言い立てる人為的温暖化が科学的真実なら、その娘は何者だ、その娘と科学に何の関係があるのか、なぜその娘と面会する必要があるのか、と憤り拒絶するはず。
IPCCのエア科学者らは、国際主義エリートの飼い犬であり、環境団体に調教されているから、環境団体の指示で「グレた」娘と面会したのである。
写真に映ってるスベタは環境団体のメンバーであろう。
だから、ハイエイタスを消し去ったことを既成事実化し、「グレた」娘に気候危機と泣き喚かせるために「ホットハウス・アース」をでっち上げた輩も、「グレた」娘を称賛している。

2019年9月4日の朝日新聞朝刊紙面(記事はネットでも全文読める。)
もちろん、江守正多も「グレた」娘を誉めそやしている。
これまで一部の関心がある人たちの話題でしかなかったこれらのことが、今週、一気に日本全国の「お茶の間」に届いたことに、筆者は興奮を隠せない。
9月23日にニューヨークで行われた国連の気候行動サミットは、小泉環境大臣効果により、日本のメディアから例外的な注目を浴びた。そして、日本のお茶の間に映し出されたのは、16歳のスウェーデン人少女の怒りのスピーチだった。
ほとんどの日本人にとって目の前に唐突に現れたこの少女、グレタ・トゥーンベリさんに対して、共感と反感の両面から、多くの反響が寄せられている。
今回初めてグレタさんを知った多くの人たちに対して、昨年からグレタさんに注目していた筆者が知ってほしいと思うことを5点述べたい。
1. 本人の意思で行動を始めた
グレタさんを見て、親や左翼の活動家に操られていると思う人がいるようだが、筆者が知る限り、それは違う。
彼女が去年の8月に、学校を休んで議会前での座り込みを一人で始めたとき、両親は心配して止めたそうだ。飛行機に乗らず、肉を食べないことを決めたのも彼女自身だ。両親は結果的にそれに付き合うことになり、オペラ歌手である母親は、海外での公演活動を休止することになった。
彼女の「ストライキ」が世界に広まり始めるとき、影響力のある環境メディアの起業家イングマール・レンツホグが彼女に手を貸した。しかし、レンツホグがグレタさんの名前を使って資金集めをしていることを知ると、彼女はレンツホグと縁を切った。
現在、これだけ有名になったグレタさんが、多くの大人から支援やアドバイスを受けていることは想像に難くない。しかし、大人の影響を受けることのリスクに対して彼女が敏感であろうことも、この例から、想像に難くないのだ。
2. 感じ方、表現の仕方が、「ふつう」と少し違う
グレタさんは、アスペルガー症候群などの診断を受けていることを自ら公表している。ものの感じ方や表現の仕方が、「ふつう」の人と少し違うのだ。
筆者はこのことを知って、ネットを調べているうちに、「ニューロ・ダイバーシティ」という言葉に出会った。彼女がふつうと違うのは、いわゆる「障がい」というよりも、「脳の多様性」だとみることができる。
筆者は次のように解釈している。
我々のように「ふつう」の脳の持ち主(ニューロ・ティピカル)は、地球の危機の話を聞いて、そのときはとても心配になったとしても、日常生活を送るうちに気をまぎらすことができる。おそらく人間の脳はそのように進化してきたのではないか。人がみな抽象的な危機を心配し続けていたら、社会が成り立たなくなるからだ。
しかし、グレタさんは違う。彼女には地球の危機を心配し続けることができる「才能」がある。11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかったそうだ。
社会の中に、このような特別な脳を持った人が少数いて、ふつうの脳を持つ大多数の人たちに対して危機に際して警告を発することは、人類種の進化の過程で遺伝的な多様性として埋め込まれた、種の存続のためのメカニズムではないかと筆者には思えるのである。
(ただし、筆者はこの分野にはまったくの素人なので、ぜひ専門の方に教えて頂きたい)
3. 特定政策ではなく、科学者の声を聞くことを訴えている
グレタさんが具体的にどういう対策を求めているかわからないという人がいるようだが、そんなのは当たり前だ。彼女はまだ16歳なのだから、問題解決の処方箋を彼女に求めるのは無理筋である。
その代わりに彼女が主張しているのは、科学者の声を聞くことだ。とりわけ、昨年10月に発表された、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「1.5℃の温暖化についての特別報告書」は彼女の持っていた危機感と共鳴した。
加えて、彼女がニューヨークのスピーチで強調したのは、気温上昇がある臨界点を超えると、フィードバックの連鎖反応が起きて、人間がどんなに対策をしても、気温上昇が止まらなくなる可能性についてだ。
ただし、この点について、今回の彼女のスピーチは誤解を招くと筆者には思われたので、補足しておきたい。筆者の理解する限り、「1.5℃」を超えると必ずその連鎖反応が起きるとはいえない。現在の科学では、そのような連鎖反応が本当に起きるかも十分に理解されていないし、起きるとしても、何℃でそれが始まるかはわかっていない。
しかし、「最悪の場合」それが1.5℃付近で始まってもおかしくはないし、彼女が「最悪の場合」を心配するのであれば、それはよく理解できる。
それに、彼女がスピーチで指摘したように、あと10年で世界のCO2排出量を半減できたとしても、気温上昇を「1.5℃」で抑えられる可能性は五分五分なのだ。「五分五分の賭け」に彼女が安心できないことは、極めてよく理解できる。
このようにみて、グレタさんの主張する危機感は、大筋において最新の科学を踏まえたものだといえるだろう。
日本の科学者コミュニティーとしても、9月19日に、日本学術会議の会長談話として、同様な趣旨の緊急メッセージを発信している。
なお、「そもそも気候変動は本当に人間活動のせいなの?」という方もまだいらっしゃると思うので、これやこれやこれをご一読頂きたい。
4. 個人の変化だけでなく社会システムの変化を求めている
グレタさんが飛行機に乗らず、肉を食べないことから、他人にもそれを要求していると思う人がいたら、それは違う。
彼女は、個人の変化だけでなく、社会システムの変化が大事だと主張している。人々に「我慢」や「不便」を強いることは、彼女が特に求めていることではないと思われる。
飛行機に乗らないことなどは、彼女自身のこだわりの面が強いと想像される。もちろん、気候の危機を認識するならば、グレタさんほど徹底しなくても、飛行機には必要最小限しか乗らない、肉はほどほどに食べる、くらいの意識の変化は個々人にあってしかるべきだろう。
筆者の解釈になるが、たとえば、飛行機がすべてバイオジェット燃料や水素燃料で飛ぶようになれば(そしてそれらの燃料をCO2を出さずに作るならば)、人々は気兼ねなく必要な飛行機旅行をすることができる。あるいはテレプレゼンス技術によって、実際に移動せずとも海外に「居る」のと同じ感覚を味わえるようになるかもしれない。
肉にしても、代替肉はすでにできているし、みんなが食べるようになれば、安く、おいしく改良されていくだろう。
「技術でなんとかなる」という楽観論をグレタさんが喜ぶはずはないが、筆者の考えでは、彼女が求める社会システムの変化のための行動には、こうしたイノベーションを含めた社会や常識の大転換や、それを促進するための制度整備や投資を急速に進めることが含まれると思う。
5. 大人に怒っているが、大人を憎んではいない(たぶん、まだ)
ニューヨークでのグレタさんのスピーチが怒りに満ちていたことに、面食らった方も多いだろう。実は、筆者もその一人だ。
今回初めてグレタさんを知った人は、ぜひ、以前のスピーチも見てみてほしい。たとえばこれ。
これまでの彼女のスピーチは、冷静で、淡々としており、そのトーンから繰り出される辛辣な表現が胸に刺さる、というのが筆者の印象だった。しかし、今回のスピーチは違った。用意した原稿にも、話し方にも、怒りがむき出しだった。
今回のスピーチが違った理由は筆者にはわからない。しかし、スピーチをよく聞くと、気になる表現があった。
「もしあなたたちが状況を理解していながら行動を起こしていないのであれば、それはあなたたちが邪悪な人間ということになる。私はそれを信じたくはない」という意味のくだりだ。
グレタさんはこれまで、人々が行動を起こさないのは、危機が訪れていることを理解していないからだろう、と言っていた。だから、若者の学校ストライキで意識を喚起し、人々が目を覚ます、つまり、危機を本当に危機として理解することを求めていたのだ。そして、人々が目を覚ませば行動(つまり、本当に気候変動を止めるための対策)が起きると考えていた。
しかし、今回、彼女の中に、この考え方に対する疑念が生じたのではないか。サミットに集まっている首脳たちは、「理解しているのに行動していない人たち」、つまり、若者の未来を奪いながら、そのことをはっきりと自覚して平気でいる「邪悪な」人たちではないか、という疑念だ。
この疑念が確信に変わるとき、グレタさんの大人への怒りは、大人への憎しみに変わるのかもしれない。
彼女は現時点ではまだ「そう信じたくはない」と言っている。筆者には、彼女が疑念と確信の間を揺れているようにみえた。これが、今回のグレタさんの怒りと関係しているように筆者には思えてならない。
**
以上が、グレタさんについて筆者が知っていることや、考えてきたことだ。
グレタさんや、彼女と共に立ち上がった世界中の若者たちは、大人が上から目線で褒めたり貶したりしていい対象であるようには、筆者には思えない。
筆者は、今後も彼らを尊敬し、見守り、機会があれば支援し、操らず、邪魔をせず、そして彼らと共に考え、共に行動したい。
(「国連 気候変動スピーチで注目のグレタ・トゥーンベリさんについて知ってほしい5つのこと」)
前章第5節で説明したとおり、ボー・トレーンが「グレた」娘に「ストライキ」をさせ、それをイングマール・レンツホグが拡散した。
全ては環境団体の邪な大人たちが仕組み演出したことであるにもかかわらず、「グレタさんを見て、親や左翼の活動家に操られていると思う人がいるようだが、筆者が知る限り、それは違う」と泣き喚き、「しかし、大人の影響を受けることのリスクに対して彼女が敏感であろうことも、この例から、想像に難くないのだ」と言い張るのは、「グレた」娘と同じく、江守正多らエア科学者も「環境団体の多くの大人から支援やアドバイスを受けている」から。
小学校で吹き込まれたから、「11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかった」のだが、従って、そもそもの初めから大人に洗脳され操られているわけだが、小学生は、CO2と言われても何なのか良く分からないし、もちろん、温室効果と言われても全く分からない。
だから、普通の子は、つまり、健全に脳が発達している子は、大人が、人為的温暖化だ、気候変動だ、と騒ぎ立てようとも、CO2排出は悪いことだ、CO2排出は怖いことだと思うはずがない。
分からないものは分からない、分からないから怖がらない、分からないけど興味を覚え学ぼうとする。
これこそが「脳の多様性」。
「彼女がふつうと違うのは、いわゆる『障がい』というよりも、『脳の多様性』だとみることができる」のは、「社会の中に、このような特別な脳を持った人が少数いて、ふつうの脳を持つ大多数の人たちに対して危機に際して警告を発することは、人類種の進化の過程で遺伝的な多様性として埋め込まれた、種の存続のためのメカニズムではないかと筆者には思える」のは、気候危機と煽り立てるために、知的劣等者の「グレた」娘を担ぎ出してきたから。
朝日新聞を見れば分かるとおり、「多様性」を排斥しようと図るとき、殊更に「多様性」と言い立てるのは左翼・マルクス主義の常套手段。
社会主義≡脱炭素社会主義は左翼思想だから、「『脳の多様性』だとみることができる」だの、「人類種の進化の過程で遺伝的な多様性として埋め込まれた」だのの台詞が出てくるのは当然。
CO2と言われても、温室効果と言われても、中学生でも良く分からない。
高校では原子や分子を一応は学ぶけれど、なぜ炭素と酸素分子二個がくっついているのかは分からない。
何故かは分からないけれど、そんなことになっている、という程度の理解でしかない。
興味を抱けば大学で化学を学ぼうとする。
しかし、前章第9節で説明したとおり、「グレた」娘は高校にも進学できなかった。
「11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかった」のだから、学びに必要な「脳の多様性」が欠落しているのだから、それも当然。
学びは科学の大元だから、「グレた」娘は「科学」と全く無縁な存在。
高校にも進学していないのだから、「科学」の基本中の基本も理解できない。
にもかかわらず、「彼女が主張しているのは、科学者の声を聞くことだ」と喚き立てるのは、前節で述べたとおり、「超自然的啓示を信ずる」ことを要求しているから。
懐疑論・否定論者との科学論争で完膚なきまでに打ちのめされてしまったから、「グレた」娘を担ぎ出してきて、「彼女が主張しているのは、科学者の声を聞くことだ」と泣き喚いているのだ。
だから、第1部第14章第1節、第16章第2節、そして、第6章第2節(の [注1] )で解説しているにもかかわらず、尚も「なお、『そもそも気候変動は本当に人間活動のせいなの?』という方もまだいらっしゃると思うので、これやこれやこれをご一読頂きたい」
前章第14節で指摘したとおり、2019年に17歳の高校生は、2013年の第5次報告書の際には11歳だった。
江守正多らは、第5次報告書でハイエイタスを認め、しどろもどろの醜態を曝け出してしまったけれど、11歳の子どもがそれを知っているはずもない。
まして、「グレた」娘は、「11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかった」ような、高校にも進学できなかったような、知的劣等者だから、知るはずもない。
しかし、それこそが狙い目。
データを改竄・捏造し、ハイエイタスという「自然的啓示」を消し去り、気候モデルの「超自然的啓示」を「自然的啓示」にしてしまうために、「グレた」娘に泣き喚かせたのである
だから、「しかし、グレタさんは違う。彼女には地球の危機を心配し続けることができる『才能』がある」と囃し立て、「とりわけ、昨年10月に発表された、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の『1.5℃の温暖化についての特別報告書』は彼女の持っていた危機感と共鳴した」と喚き立てる。
「彼女はまだ16歳なのだから、問題解決の処方箋を彼女に求めるのは無理筋である」と泣き喚くのも、「彼女の持っていた危機感」は正しいと思わせて、気候モデルの「超自然的啓示」を「自然的啓示」にしてしまうために他ならない。
第1部第13章第9節で解説しているにもかかわらず、尚も「彼女がニューヨークのスピーチで強調したのは、気温上昇がある臨界点を超えると、フィードバックの連鎖反応が起きて、人間がどんなに対策をしても、気温上昇が止まらなくなる可能性についてだ」と喚き立てているけれど、高校にも進学できなかったのに、「臨界点」だの、「フィードバック」だの分かるはずがなかろう。
前章第6節で指摘したとおり、朝日新聞は「波乱続きのCOPを盛り上げたグレタ」と囃し立てていたけれど、こんなことをしていた。
マドリード=香取啓介 2019年12月11日20時47分
スペイン・マドリードで開催中の第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)で11日、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(16)が演説した。非常事態にあるのに、政治家は誤った道に導いていると批判した。
グレタさんは「一番危険なのは行動しないことではない。危険なのは、政治家や企業家たちが、ほとんど何もしていないのに、ずるがしこい説明と想像力豊かなPRで、本当の行動をしていると見せかけることだ」と訴えた。
COP25では閣僚級会合に入っているが、パリ協定運用の仕組み作りや、温室効果ガスの削減目標の引き上げは硬直している。グレタさんは「COPがやるべきなのは、全体的な解決策を探ること。なのに、各国は抜け道をつくることや目標引き上げを避けるために交渉しているように見える」と話した。
9月の国連気候行動サミットで注目を浴びた「How dare you!」(よくもそんなことができる)というフレーズは封印した。「みんなそこに注目して、なぜ私がそんなことを言ったのかという事実を覚えていない。科学から離れている暇は無い」と述べ、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が昨年公表した「1.5度特別報告書」の概要を説明した。
今のままの排出が続けば、パリ協定で掲げる産業革命前からの気温上昇を1・5度に抑える目標は8年で不可能になると指摘。「これは意見でもなく、政治的見解でもない。今使える最上の科学だ」と対策の加速を訴えた。(マドリード=香取啓介)
 第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)で演説する環境活動家のグレタ・トゥンベリさん=11日、スペイン・マドリード、松尾一郎撮影
第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)で演説する環境活動家のグレタ・トゥンベリさん=11日、スペイン・マドリード、松尾一郎撮影
(朝日新聞デジタル)
高校にも進学できなかった娘が「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が昨年公表した『1.5度特別報告書』の概要を説明した」?
「How dare you」!
普通の高校生でもできないのに、高校にも進学できなかった娘にできるはずがなかろう。
環境団体の邪な大人たちに吹き込まれたことを喋っただけ。
やはり、大人に操られている。
ところが、「みんなそこに注目して、なぜ私がそんなことを言ったのかという事実を覚えていない」から分かるとおり、呆れたことに、この娘は自分が本当に科学を理解している、説明できると思い込んでいる!
だから、国連で泣き喚く前もこんなことを言っていた。
2019年8月6日 6時49分
地球温暖化対策を訴えるスウェーデンの16歳の少女の活動に賛同してヨーロッパ各地で運動を行っている若者たちがスイスに集まり、来月開かれる国連の会議などに向けて連携を深めることにしています。
スウェーデンの16歳の少女、グレタ・トゥーンベリさんは去年8月から毎週金曜日、学校を休んで温暖化対策を求める訴えを続け、SNSを通じて世界各地の若者に広がった運動は「未来のための金曜日」と呼ばれています。
スイス西部のローザンヌでは5日、ヨーロッパ各地からトゥーンベリさんの活動に賛同する高校生や大学生など450人余りが夏休みを利用して集まりました。
若者たちは1週間かけて会議や討論を行い、連携を深めるため今後の運動の指針などを決めるということで初日の会合ではトゥーンベリさんも参加して意見を交わしていました。
記者会見でトゥーンベリさんは1年を振り返り「去年、多くのことが起きたが世界全体の温室効果ガスの削減にはつながっていない。まだやることはたくさんある」と述べました。
トゥーンベリさんは来月、ニューヨークで開催される国連の温暖化対策サミットに招待されていて「世界の指導者が私たちの声を聞き科学の声を聞いたと証明する機会になる」と述べて各国が会議で具体的な対策を示すことに期待を示しました。
トゥーンベリさんたちはサミットに合わせて運動を大人にも広げ対策を迫ることにしています。
(NHK)
自分が「科学の声」だと思い込んでいる。
「How dare you」!
驚くべき異常性。
しかし、この異常性ゆえに、環境団体が「グレた」娘を担ぎ出してきたのである。
前章第5節で説明したとおり、「米フロリダで起きた銃乱射事件で被害者を受けた高校生たちのように、世にメッセージを伝えるために学校を休むというストライキをしたらどうか」と持ちかけられた時、他の子らが、そんな不埒なことは出来ない、と断ったのに、「グレた」娘だけは飛びついた。
第3節で見たとおり「科学と倫理は『点火』の段階でのみ必要なのであり」と高言を吐いていたけれど、「グレた」娘に倫理性は欠片もない。
前章でも説明したとおり、「グレた」娘にあるのは、ただただ、脚光を浴びたいという破廉恥な自己顕示欲のみ。
その異常性を見抜いたイングマール・レンツホグが、「ひとりで座り込み運動をする少女を”発掘”し、その存在を拡散した」。
「11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかった」のも、学級内で脚光を浴びようと、温暖化、温暖化と騒ぎ立てたけれど、同級生から煙たがられ、疎んぜられてしまった結果。
前章第15節でも引用したけれど、
プレハーノフ「歴史における個人の役割」、岩波文庫p77より
「グレた」娘の「社会関係」は、学校での友達との関係ではなく、自宅周辺の住民との関係でもなく、環境団体との関係であり、その背後にいる富裕層の投資家との関係。
「彼女には地球の危機を心配し続けることができる『才能』がある」と囃し立てる「才能」とは、「グレた」娘の異常な自己顕示欲と自己愛が、すなわち、異常人格が投資家に利用価値がある、ということ。
事実、「11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかった」なら、物静かで温和しい性格かと思いきや、案に反して、ダボスで臆することなくも泣き喚いて見せた。
脚光を浴びたいという自己顕示欲、それも人並み外れた異常な自己顕示欲の故に、脚光を浴び、大人にちやほやされると、さらに自己顕示欲が増して喚き立てる。
その異常性を目の当たりにしたダボス様に、これは使えると認められて、国連に招かれた。
そこでも、ダボス様の期待に反せず、ますます自己顕示欲を増強させて泣き喚いた。
国連でのこの異様極まる光景はその事実をハッキリと示している。
前章第9節で採り上げたWEBRONZAに見えるとおり、自ら「アスペルガーは病気ではありません。天賦の才能です」と言ってのけたのも、環境団体の邪な大人たちにちやほやされて天狗になっていることを、明確に示している。
江守正多らエア科学者も「グレた」娘を産み出した「社会勢力」に属するから、国際主義エリートの飼い犬だから、「彼女には地球の危機を心配し続けることができる『才能』がある」と囃し立てるのだ。
黄色いベスト運動は「社会システム」をハッキリと示していた。
しかし、前章第3節で説明したとおり、「グレた」娘は黄色いベスト運動粛清の尖兵となった。
「彼女は、個人の変化だけでなく、社会システムの変化が大事だと主張している」と喚き立てたのは、庶民=労働者階級からの収奪を強め、国際主義エリートの投資家が富を肥やす「社会システム」を創り上げるために、エア科学者が温暖化を煽り立て、「グレた」娘を使って気候危機と煽り立てていることを、ハッキリと示している。
マルクス「資本論」、岩波文庫第二巻p182より
これが、国際主義エリートが、その僕の環境団体が、朝日新聞ら左翼メディアが、そして、飼い犬の江守正多らエア科学者が、「グレた」娘を神輿に乗せて「社会システムの変化が大事だと主張している」ところの、「社会システムの変化」。
化石燃料で利を得てきたのは投資家なのだから、気候危機が事実なら、投資家に怒り、投資家への憎しみを滾(たぎ)らせるはず。
環境団体が、江守正多らエア科学者が「国際主義エリートの投資家を糾弾する行動を起こさないのは、危機が訪れていることを理解していないからだろう」。
「グレタさんの大人への怒りは、大人への憎しみに変わるのかもしれない」のは、「危機が訪れていることを理解していないからだろう」
けれど、「グレタさんはこれまで、人々が行動を起こさないのは、危機が訪れていることを理解していないからだろう、と言っていた。だから、若者の学校ストライキで意識を喚起し、人々が目を覚ます、つまり、危機を本当に危機として理解することを求めていたのだ」。
自分は理解していないけれど、自分だけは理解している???
もちろん、「グレた」娘の場合、「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が昨年公表した『1.5度特別報告書』の概要を説明した」ほどだから、それもあり得ないことではない。
しかし、「グレた」娘を操っている環境団体の邪な大人たち、江守正多らエア科学者の場合、さすがにそれはないだろう。
100%ないとは言えないが、「さすがにそれはないだろう」には「97%の合意」がある。
「もしあなたたちが状況を理解していながら行動を起こしていないのであれば、それはあなたたちが邪悪な人間ということになる。私はそれを97%信じざるを得ない」。[注1]
あなたたちは状況を理解しているから行動を起こしていない。
気候危機と煽り立て、知的劣等者で人格異常者の「グレた」娘に「大人への怒り」を滾らさせ、「大人への憎しみ」を滾らさせ、庶民=労働者階級からの収奪を強めようとしているのである。
だから、「大人たちが子供の将来に危機をもたらしていること」、「これまで一部の関心がある人たちの話題でしかなかったこれらのことが、今週、一気に日本全国の『お茶の間』に届いたことに、筆者は興奮を隠せない」のだ。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p98より
[注1] 第1部第16章第3節で解説しているとおり、ハイエイタスはラニーニャ優勢のENSOが原因、もしくは、PDOの負位相が原因なら、それ以前の急激な気温上昇はエルニーニョ優勢のENSOが原因、もしくは、PDOの正位相が原因ということになる。
「もし江守正多たちが状況を理解していながら『no one really talks about the other side of this situation』あれば、それは江守正多たちが邪悪な人間ということになる」
常識的に考えるなら、理解していないはずはない。
理解していたはずには「97%の合意」がある。
だから、「もし」ではなく、「江守正多たちは状況を理解していながら『no one really talks about the other side of this situation』だった」のだ。
だから、「江守正多たちは邪悪な人間」に「97%の合意」がある。
「『もしあなたたちが状況を理解していながら行動を起こしていないのであれば、それはあなたたちが邪悪な人間ということになる。私はそれを信じたくはない』という意味のくだりだ」と喚き立てたけれど、逆に、ハイエイタスを消し去るために「グレた」娘を祭り上げていることを、露呈しただけ。
庶民=労働者階級からの収奪を強め、国際主義エリートが富を肥やすために、「グレた」娘を祭り上げていることを露呈しただけ。
6.9 貴族の未来ための13日の金曜日
さらに「グレタさんや、彼女と共に立ち上がった世界中の若者たち」に関して、こんなことを書いている。
3月15日には100ヵ国以上で合計150万人が参加したといわれる一斉抗議行動があった。日本でも東京と京都でそれぞれ100人規模のマーチが行われた。すべてのきっかけとなったのは、昨年、一人で行動を始めたスウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさんだ。
Yahoo!ニュース個人では、ノルウェー在住の鐙麻樹さんが、継続的に発信してくださっている(2/24、3/14、3/23、3/30)。
筆者も年明けの記事でグレタさんのことに触れて以来、ずっとこのことが気になっていた。
4/12に、米国の科学雑誌 Science に、この若者の抗議行動を支持する国際的な科学者グループ Scientists for Future International の声明が掲載された。筆者も声明に賛同し、署名させて頂いた。
以下に、起草者の許可を得て、声明全文の和訳を紹介させて頂く。「抗議する若者たちの懸念は正当である」
(Scientists for Future International 声明)
世界中の若者が、気候やその他の人間の幸福の基盤を守ることを訴えて根気強い抗議行動を始めています。最近自国で同様の支持声明を始めた科学者、学者として、我々はあらゆる学問分野の世界中の同僚に、抗議する若者たちへの支持を呼びかけます。我々は次のように宣言します。「彼らの懸念は、現時点の最善の科学によって正当化され、支持される。気候と生態系を守るための現状の対策はひどく不適切である。」
ほぼすべての国が2015年のパリ協定に署名と批准を行い、国際法の下に地球温暖化を産業化前を基準に2℃より十分低く抑えることと、気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求することを約束しました。科学コミュニティーは、地球温暖化が1.5℃ではなく2℃まで進むと気候に関連した影響とリスクが相当に増加し、そのいくつかは後戻りできないものになるであろうことを明確に結論しています。さらに、ほとんどの影響は不均一にもたらされるため、2℃の温暖化は既に存在する世界規模の不公正をより悪化させるでしょう。
CO2および他の温室効果ガスの排出の急速な削減を直ちに始めることが決定的に重要です。人類が将来に経験する気候の危機の大きさは、累積された排出量によって決まります。今、急速な削減をすれば、被害は抑えられます。例えば、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が最近評価したところによれば、CO2の排出量を2030年までに(2010年水準を基準に)半減させ、2050年までに世界でCO2排出正味ゼロ(加えて他の温室効果ガスの大幅削減)が達成されれば、50%の可能性で温暖化が1.5℃未満に収まるでしょう。先進工業国がこれまで多くの排出をもたらし、そこから多くの便益を得てきたことを考えると、先進工業国は世界全体と比べてより速やかに、この移行を達成する倫理的な責任があります。
多くの社会的、技術的、そして自然に基づく解決策が既に存在しています。抗議する若者たちは、これらの解決策を使って持続可能な社会を達成することを正当に要求しています。大胆で集中的な行動が無ければ、彼らの未来は重大な危険にさらされます。彼らが権力の座に就くまで待つ時間は残されていません。
政治家たちは、必要な構成条件を適時に創出する大きな責任を負っています。気候に親和的で持続可能な行動を単純かつコスト効率的なものにし、気候に破壊的な行動を魅力無く高コストにするような政策が必要です。例えば、効果的なCO2の価格付けや規制、気候に破壊的な行動や製品への補助金の廃止、省エネ基準、社会イノベーション、再生可能エネルギーや分野横断の電化や公共交通インフラや需要の削減などへの大規模で直接的な投資などです。気候対策のコストと便益の分布が社会的に公正になることに慎重な注意が必要ですが、それは可能であり肝要なことです。
「未来のための金曜日」、「気候のための学校ストライキ」、「気候のための若者」、「若者の気候ストライキ」などとよばれる、若者の気候変動についての社会運動の壮大な規模の草の根の動員は、若者が状況を理解していることを示しています。我々は、彼らが求める急速で力強い行動を承認し、支持します。我々は紛れの無い言葉で次のように述べることを、我々の社会的、倫理的、学問的責任とみなします。「人類が速やかにかつ意を決して行動することによってのみ、地球温暖化を抑制し、現在進行している動物種と植物種の大量絶滅を止め、現在と将来の世代の食料供給と幸福の自然的な基盤を保全することができる。」これが、若者たちが達成を求めていることです。彼らは、我々の尊敬と全力の支持に値します。
起草者: Gregor Hagedorn, Peter Kalmus, Michael Mann, Sara Vicca, Joke Van den Berge, Jean-Pascal van Ypersele, Dominique Bourg, Jan Rotmans, Roope Kaaronen, Stefan Rahmstorf, Helga Kromp-Kolb, Gottfried Kirchengast, Reto Knutti, Sonia I. Seneviratne, Philippe Thalmann, Raven Cretney, Alison Green, Kevin Anderson, Martin Hedberg, Douglas Nilsson, Amita Kuttner, Katharine Hayhoe
(原文:Science 12 Apr 2019)「科学者による支持」の意味(筆者私見)
ここからは、筆者自身の考えを含めて、若干の解説を試みたい。
実は、筆者の周囲の科学者の中でも、この声明に署名することについては様々な意見があった。この声明の一字一句に、また若者たちの主張の一字一句に同意できないのであれば、署名をするのは科学者として無責任ではないか。「科学者によるお墨付き」を与えることで、若者の行動にエリート主義的なイメージを付加してしまうのは逆効果で、意図せぬ反発を招くのではないか。
筆者個人としては、そういったことを考慮しても、即座に署名に加わる方が悔いが無いと判断した。
確かに、若者たちのスローガンは時として極端だ。たとえば「破局を避けるためにはあと11年しかない」というような言い方は不正確であり、厳密に科学的な意味では支持できない。温暖化は「早ければ」2030年に1.5℃を超えるおそれがあるが、そこには不確かさがあるし、1.5℃を超えたときの影響は「悪くすれば」破局と呼びうるレベルになるおそれがあるが、影響の予測も不確かだし、何を破局と呼ぶかは自明でない(このあたりは、IPCCの1.5℃特別報告書の解説に書いた)。
しかし、筆者個人は、そのようなスローガンを、より広い意味では十分に支持できる。将来の予測に不確かさがあるとき、その不確かさの中で最悪のケースを心配するか、それとも可能性の高そうなところを見込むのかといったことは、科学だけでは答えが出ないリスク判断である。その判断を、実際にそのリスクに直面して生きる若者たちを差し置いて、今の大人が勝手に決めてよいわけがない。若者には最悪の事態を心配する権利があり、彼らがそれを声を張り上げて主張することはこの上なく正当なことに思える。
筆者は若者たちの主張「のみが」正しいというつもりはない。しかし、大人たちは少なくとも、若者たちを主要な利害関係者と認めて、彼らと交渉する必要があるだろう。
また、科学者がこの声明に署名することは、個人的な行為であり、ある意味で政治的な行為だと思う。科学者の支持は、若者の行動に絶対的で客観的な正しさを付与したみたいに捉えられるべきではない。声明と署名は、全体として専門家が若者の行動の科学的な根拠を保証する役目を果たしつつも、科学者一人一人の署名は、個人の判断に基づいており、それぞれに主観的な思いも込められているに違いない(例えば、筆者にも高校生、中学生、小学生の子供がいる。このことが筆者が署名したときの気持ちと無縁であろうはずはない)。
すべては始まったばかり
次の若者の世界一斉行動(Global Climate Strike)は、5月24日(金)に予定されているようなので、引き続き注目したい。
Scientists for Future International の署名は、Science 記事発表時点のものが記事の付録に数千人分収められているが、引き続きウェブサイトで受け付けている。
国立環境研究所では、4月20日(土)に、研究所に高校生・大学生を招いて気候変動について議論する「気候[変]会議」とニコニコ生放送による中継を行うので、ここでも若者の抗議行動について取り上げたいと思っている。
参加申し込みはこちら(高校生・大学生のみ)
(春の環境講座全体は13:00~。気候[変]会議は15:00~、一部のみでも参加可能)
ニコニコ生放送はこちら(どなたでもご視聴ください)
(放送は14:30~18:30予定)
(抗議する若者たちの懸念は正当である:世界の科学者が支持声明を発表)
全ては環境団体が仕組んだことであるにもかかわらず、「すべてのきっかけとなったのは、昨年、一人で行動を始めたスウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさんだ」と囃し立てていることだけでも、真実は明らかだが、CO2排出が価値を産み出したのではない。
第1節でも説明したとおり、価値は、何をどのように生産しているかという具体的労働には依らず、抽象的労働としての労働時間だけで決まる。
マルクス「資本論」、岩波文庫第一巻p75より
にもかかわらず、「先進工業国がこれまで多くの排出をもたらし、そこから多くの便益を得てきたことを考えると、先進工業国は世界全体と比べてより速やかに、この移行を達成する倫理的な責任があります」と泣き喚くのは、第4章で解説したとおり、先進国の労働力の価値を引き下げて、一般的利潤率低下を抑制するために、「CO2の排出量を2030年までに(2010年水準を基準に)半減させ、2050年までに世界でCO2排出正味ゼロ(加えて他の温室効果ガスの大幅削減)が達成されれば、50%の可能性で温暖化が1.5℃未満に収まるでしょう」と煽り立てているから。
だから、真っ先に「効果的なCO2の価格付け」と言い張っている。
そして、第6節でも引用したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第六巻p397より
「再生可能エネルギーや分野横断の電化や公共交通インフラや需要の削減などへの大規模で直接的な投資などです」と言い張っている。
そのために、一部の愚かな若者らを洗脳し扇動し組織化している。
「確かに、若者たちのスローガンは時として極端だ」と批判めかしているけれど、第5次報告書でしどろもどろの醜態を曝け出したことを知らない若い世代に、「破局を避けるためにはあと11年しかない」と泣き喚かせて、ハイエイタスを闇に葬り去り、「彼らの懸念は、現時点の最善の科学によって正当化され、支持される」と言い立てているのだ。
その証拠に、「若者の気候変動についての社会運動の壮大な規模の草の根の動員」と認めているではないか。
「先進工業国がこれまで多くの排出をもたらし、そこから多くの便益を得てきた」のなら、前章第18節と20節でも説明したとおり、大人たちが創り出した「便益」を最も享受しているのは若者。
しかも、前章第18節でも説明したとおり、異常気象の犠牲者の多くは年配者だから、それはCO2排出原因なら、お父さん、お母さん、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんを守りたいんだ、と主張すれば、それで十二分であり、かつ、その方が説得力がある。
にもかかわらず、「実際にそのリスクに直面して生きる若者たちを差し置いて、今の大人が勝手に決めてよいわけがない。若者には最悪の事態を心配する権利があり、彼らがそれを声を張り上げて主張することはこの上なく正当なことに思える」のは、前章第16節でも説明したとおり、階級対立を止揚するために大人と若者を対立させ、「大人への怒り」を滾らさせ、「大人への憎しみ」を滾らさせて、庶民=労働者階級からの収奪は「正当である」にするために他ならない。
しかも、若者間にも格差が生じている。
格差は拡大している。
老若男女にかかわらず、富者は少数で弱者が多数だから、「効果的なCO2の価格付け」は多くの若者をも直撃する。
前章第20節でも指摘したけれど、今がなければ未来はない。
「彼らの未来は重大な危険にさらされます」
実は、多くの若者の未来を奪うために、「大人たちは少なくとも、若者たちを主要な利害関係者と認めて、彼らと交渉する必要があるだろう」と喚き立てている。
その証拠に、「彼らが権力の座に就くまで待つ時間は残されていません」と泣き喚いているではないか。
それは、国際主義エリートのような権力者の未来を奪うな、と言うこと。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p67より
「庶民=労働者階級に抗議する貴族たちの懸念は正当である」から、「抗議する若者たちの懸念は正当である」と泣き喚くのだ。
江守正多らエア科学者は国際主義エリートの飼い犬であり、環境団体に調教されている。
この「抗議する若者たちの懸念は正当である」という声明文も、一部の愚かな若者らを「動員」した環境団体の指示。
偉大なる国際主義エリート様が企図したことだから、「グレタさんや、彼女と共に立ち上がった世界中の若者たちは、大人が上から目線で褒めたり貶したりしていい対象であるようには、筆者には思えない」。
「筆者は、今後も彼ら国際主義エリートを尊敬し、見守り、機会があれば支援し、操らず、邪魔をせず、そして彼らと共に考え、共に行動したい」から、「筆者は、今後も環境団体に組織化された彼らを尊敬し、見守り、機会があれば支援し、操らず、邪魔をせず、そして彼らと共に考え、共に行動したい」。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p98より
6.10 気候市民会議
庶民=労働者階級からの収奪を強めるための「社会システムの変革」だから、「グレた」娘を盾にして喚き続けている。
・・・前略・・・
そこで必要になってくるのが、社会の「システム」に働きかけるというアプローチだ。スウェーデンの環境活動家グレタさんは、なぜ飛行機に乗らずにヨットで大西洋を横断したのか考えてみるとよい。彼女は皆がそうすべきだと言っているのでもなければ、自分一人分のCO2を減らしたかったわけでもない。彼女は、誰もが飛行機に乗ってCO2をたくさん出しながら移動する現在の社会システムは持続不可能であることを人々に気付かせる「メッセージ」を発するためにこれを行ったのだ。(このことは中田敦彦さんが「YouTube大学」で紹介してくれているのでぜひご覧いただきたい)
あなたの行動が、あなた自身のCO2を減らすだけでなく、システムを変えるメッセージになるように行動せよ。
これが、筆者がグレタさんから学んだ格率である。
・・・中略・・・
今回あらためて考えて、自分は労働問題への感度が低いんだなあ、と筆者は思ったのである。同様に、性差別、人種差別、格差、貧困、基地問題などなど、考えなくてはいけない社会問題は数多ある中で、感度よく反応できたり、自分で調べて考えて発言したり行動したりできているものは筆者の場合は環境問題くらいである。他の多くの問題は、頭ではわかっていても、取り組めていない。言ってみれば、自分は環境問題以外については「無関心層」なのだ。
しかし、筆者はこれらの問題に取り組む人たちを支持するし、ぞれぞれの問題を改善するためにシステムに働きかけてほしい。途中で見聞きした議論に違和感があれば意見を言うが、すべての議論に参加する余裕は無いので、自分は置いていっていいからシステムを改善してほしい。自分は後からついていくので。このように考えれば、問題毎に本質的な関心を持った人たちがシステムの変化をリードしていくのは自然なことなのではないか。
しかも、既に渡辺寛人さんや志葉玲さんがそれぞれの観点から指摘されているように、環境問題は労働問題や格差問題と相反するものではない。格差問題についての視点を一つ追加すると、気候変動の悪影響をより深刻に受けるのは、社会的な立場の弱い人たちである。農業が異常気象の被害を受けて食料価格が上昇したときに困るのは庶民だし、水害が直撃すれば生活再建に苦しむのも庶民である。環境問題に取り組むのは恵まれた人の道楽なのではなく、「庶民」こそが当事者である側面が大きいことを理解してほしい。
このように考えると、環境問題、労働問題、格差問題等のそれぞれのテーマに強い関心のある人たちが、自分のテーマの方が重要であると言い争うのではなく、それらの問題をつなげて考えて、互いを応援したり、協力してシステムを変える働きかけをすることの重要性が浮かび上がってくるように思う。
「対話」の場をどう構築するか
そうは言っても、議論に置いていかれた人たちに十分な配慮が無くシステムの変化が進むことにはもちろん注意せねばならない。実際に、フランスでは(気候変動対策の一環である)燃料税の値上げによりタクシー運転手などの「庶民」が困窮し、これをきっかけにイエローベスト運動とよばれる政府への抗議活動が起きた。
この結果、市民の政治参加への要求が高まり、マクロン大統領は無作為抽出された150人の市民による気候市民会議を開催した。男女比、年齢構成、学歴などは、フランス社会全体の縮図となるように調整された。参加した市民は専門家の情報提供を受けつつ対話的な議論を行い、政府への提言を取りまとめた。同様の市民会議は英国の議会によっても開催されている。
筆者は、この気候市民会議に関心を持っており、筆者の参加する研究グループでは、11月から12月に札幌市において小規模ながらこの試行を行った。日本政府としてもこのようなプロセスで国民を巻き込んだ議論を本格的に行うべきだと考えており、筆者は政府の審議会でもそのように発言している。その意味では、トラウデンさんが出席した首相官邸の「カーボンニュートラル・全国フォーラム」は、政府と国民との対話の機会としては極めて限定的で不十分なものと言わざるをえない。
ハフポストのコメントで、「関心が無い人すべてを説得している時間は残されていない」と言ったが、これは本当にそう思っている。しかし、これは対話の拒否を意味しているのではない。むしろ、その限られた時間の中で、いかに多様な人たちの有意義な対話の場を構築できるかが、これからも筆者の関心事である。
(「『環境に配慮した商品ですか』と店員に尋ねることを、それでも僕が支持する理由」より)
もう一度、いや、何度でも言うけれど、黄色いベスト運動こそは「社会システム」をハッキリと示している。
前向き、前向き、と喚いていたけれど、「社会システム」を少しでも改善するのなら、黄色いベスト運動が「議論に置いていかれた」はずがない。
「環境問題は労働問題や格差問題と相反するものではない」と言い逃れをしているが、「労働問題や格差問題と相反する」から「議論に置いていかれた」のだ。
「自分は置いていっていいからシステムを改善してほしい」と言うのは、黄色いベスト運動は置いていっていいからシステムを改善してほしい、と言うことに他ならず、投資家の富裕層が庶民=労働者階級からの収奪を強める「社会システム」を構築するために、温暖化を煽り立ててきたことを自白している。
第1節でも引用したけれど、
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p229より
「議論に置いていかれた人たちに十分な配慮が無くシステムの変化が進むことにはもちろん注意せねばならない」と言い立てるのは、「自分の肩から労働者階級および下層中間階級の肩に転嫁することを心得ている」わけである。
「グレた」娘は黄色いベスト運動粛清の先頭に立った。
「グレた」娘を担ぎ出し祭り上げて、黄色いベスト運動は「議論に置いていかれた」。
「社会システム」を全く顧みないから、投資家の富裕層が庶民=労働者階級からの収奪を強める「社会システム」の構築が目的だから、「スウェーデンの環境活動家グレタさんは、なぜ飛行機に乗らずにヨットで大西洋を横断したのか考えてみるとよい」。[注1]
その証拠に、
2019年8月19日 13:38 発信地:パリ/フランス
スウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリ(Greta Thunberg)さん(16)が国連の気候変動サミットが開かれる米ニューヨークに向かうため乗船している炭素排出量ゼロのヨットに関し、欧州へ戻すための人員として航行チーム数人が飛行機で渡米することが分かった。インターネット上では二酸化炭素排出をめぐって批判の声が出ており、チーム側は釈明に追われた。
地球温暖化対策を求める学校ストライキによって世界中の子どもたちの間に旋風を巻き起こしたトゥンベリさんは、二酸化炭素を排出するという理由から飛行機の利用を拒否している。
そんなトゥンベリさんだが、良心の呵責(かしゃく)なく大西洋を横断して国連会合に参加できるよう、父のスバンテ(Svante Thunberg)さんと旅路を記録するドキュメンタリー作家と一緒にレース用ヨット「マリツィアⅡ号(Malizia II)」でニューヨークに向かうことを提案され、今月15日に英プリマス(Plymouth)を出航した。
しかし、今回の旅で共同船長を務めるドイツ人のボリス・ヘルマン(Boris Herrmann)氏の広報担当は独ベルリン紙「ターゲスツァイトゥング(Tageszeitung)」に対し、ヨットを欧州に戻すために航行チーム数人が飛行機で渡米し、ヘルマン氏自身は空路で帰国すると明かした。
また、同紙はヨットでの移動は飛行機よりも実際は汚染の影響が大きいのではと推測しており、すぐにトゥンベリさんに批判的な人たちがソーシャルメディアなどで話題にした。
航行チームの責任者であるホリー・コバ(Holly Cova)氏は、トゥンベリさんによるヨットの旅について環境に優しいものだと主張。一方で「非常に急な依頼だったため、ボートを戻すために結果として2人が渡米しなければならなくなった」と釈明した。
トゥンベリさんは9月23日にニューヨークでの国連会合に出席し、12月には別の国連会合でチリを訪れるほか、カナダやメキシコにも立ち寄る予定で、どのように移動するかについては明らかになっていない。
 英国南西部のプリマスで、ヨット「マリツィアⅡ号」に乗船するスウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリさん(2019年8月14日撮影)。(c)Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
英国南西部のプリマスで、ヨット「マリツィアⅡ号」に乗船するスウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリさん(2019年8月14日撮影)。(c)Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
(AFP)
しかも、「旅路を記録するドキュメンタリー作家と一緒にレース用ヨットでニューヨークに向かう」
ちゃっかりとポーズを決め込んでいる。
出港時も、入港時もメディアが詰めかけて脚光を浴びる。
浴びたいから、こんなことをした。
ニューヨーク=藤原学思 2019年8月29日09時53分
国連本部での気候サミットに出席するため、ヨットでの大西洋横断をめざしていたスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥンベリさん(16)が28日夕(日本時間29日朝)、米ニューヨークの港に到着した。温室効果ガス削減を訴え、ガス排出量が多い飛行機の利用を批判していた。
グレタさんは義務教育を終え、現在は気候変動対策活動に専念している。14日に父親や支援者らと英国を出発。ソーラーパネルのほか、水中で発電する装置を載せたヨットで、330時間かけてニューヨークまでの約7千キロを航海した。
港では市民や報道陣ら数百人が出迎えた。グレタさんは到着後、少し顔をこわばらせつつ手を振って応えた。港で開いた会見では「気候変動、生態系の危機は、人類がこれまで直面したことがないほど大きく、地球規模のもの。ともに立ち上がり、助け合いながら行動を取らなければ手遅れになる」と訴えた。
また、温暖化対策に消極的なト…
 ヨットでの大西洋横断に成功し、緊張した表情で出迎えた市民らを見つめるグレタ・トゥンベリさん=2019年8月28日午後4時6分、米ニューヨーク、藤原学思撮影
ヨットでの大西洋横断に成功し、緊張した表情で出迎えた市民らを見つめるグレタ・トゥンベリさん=2019年8月28日午後4時6分、米ニューヨーク、藤原学思撮影
(朝日新聞デジタル)
しかも、よく見ると、胸に名前とキャッチフレーズまで縫い込んでいる。
特別誂えのパーカーを全員が着込んでいたのだ。
(8月にこんなパーカーを着込んでいるということだけでも、真実が露呈している。もちろん、IPCCの記録では最も暑い8月だったということになっているけれど。)
「モナコ公家の一員であるピエール・カシラギ氏と、世界一周を達成したことがあるドイツ人のボリス・ヘルマン氏がかじを取る」ということは、富裕層が全面支援しているということ。
黄色いベスト運動粛清の先頭に立ち、富裕層の支援でこんなパフォーマンスに打ち興じたのを、「彼女は、誰もが飛行機に乗ってCO2をたくさん出しながら移動する現在の社会システムは持続不可能であることを人々に気付かせる『メッセージ』を発するためにこれを行ったのだ」と喚き立てるのだから、「環境問題は労働問題や格差問題と相反する」ことは明白。
庶民=労働者階級からの収奪を強めるための脱炭素であり、その事実を否定したいから、「環境問題は労働問題や格差問題と相反するものではない」と泣き喚いている。
「経済学・哲学草稿」はシェークスピアの「アテネのタイモン」とやら(無知な筆者は初耳だが、岩波文庫にも収められていないから、シェークスピア全集でも入手しない限りお目にかかれないのではなかろうか)から引用している。
私はだてにお祈りしてるんじゃないよ。
こいつがこのくらいあれば黒も白に、醜も美に、悪も善に、老も若に、臆病も勇敢に、卑賤も高貴にかえる
マルクス「経済学・哲学草稿」、岩波文庫p180より
「脱炭素」を煽り立てる社会においては、当に「黒(エア科学)も白に」
醜(「グレた」娘)も美に。
(前章第13節で採り上げた2019年11月1日の朝刊紙面で元環境省の下司が「『誰かに入れ知恵されている』などと批判する大人の姿は醜悪でした」と泣き喚いたのは、そのことをハッキリと示している。)
「悪(投資家)も善に」
「彼女と共に立ち上がった世界中の若者たちは、大人が上から目線で褒めたり貶したりしていい対象であるようには、筆者には思えない」と泣き喚いたのは、「臆病も勇敢に」
前章第7節で採り上げた社説余滴で「大人たちは『危機にふさわしい行動』とはなんなのかを真剣に考えるべきだ」だの、第9節で採り上げたWEBRONZAでも「大きな危機が迫っているのに、いつもの日常を送ろうとするオトナたちの頭が狂っているようにしか見えないのだろう」だの、第14節で採り上げた「トゥンベリさんから火 なぜ彼らは怒るのか」という記事でも「日本でも子供たちは動き出したのに、大人たちはまだ動き出さない」だのと泣き喚き、第18節で紹介したとおり、ハレンチ娘にも「大人たちは、自分自身の責任と向き合い行動で示すべきだろう。そして、若者をいかに危険にさらしているのかを自覚してほしい」と泣き喚かせたけれど、「大人たちは『危機にふさわしい行動』とはなんなのかを真剣に考え」「大人たちは、自分自身の責任と向き合い行動で示す」ならば、「老も若に」
「卑賤(黄色いベスト運動)も粛清されて高貴にかえる」
旗色が悪くなったので、「気候変動の悪影響をより深刻に受けるのは、社会的な立場の弱い人たちである」と泣き喚いているけれど、「社会的な立場の強い人たち」が毟り盗り続けてきたからこそ、「社会的な立場の弱い人たち」が生まれた。
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p232-233より
しかも、CO2を排出して富を築き上げてきたのは、「社会的な立場の強い人たち」の富裕層。
「気候変動の悪影響」と泣き喚くのなら、連中の資産を没収して格差を解消すれば、「より深刻に受けるのは、社会的な立場の弱い人たちである」は起こり得ない。
それこそが「社会システム」の変革。
けれど、富裕層がCO2を排出して富を築き上げてきたことは是だから、「気候変動の悪影響をより深刻に受けるのは、社会的な立場の弱い人たちである」と泣き喚いている。
「社会的な立場の弱い人たち」からの収奪を強めて、「社会的な立場の強い人たち」が富を肥やし続けるために気候変動と煽り立てているから、「気候変動の悪影響をより深刻に受けるのは、社会的な立場の弱い人たちである」と泣き喚くのだ。
「労働問題」「格差問題」は階級対立の問題。
エンゲルス「共産党宣言英語版への序文」、岩波文庫「共産党宣言」p27より
庶民=労働者階級からの収奪を強めるためには、「労働問題」「格差問題」を圧し潰さねばならない。
そのためには階級闘争を止揚しなければならない。
そのためには、大人と若者を対立させねばならない。
だから、前節で見たとおり、「この疑念が確信に変わるとき、グレタさんの大人への怒りは、大人への憎しみに変わるのかもしれない」と泣き喚いた。
「グレた」娘を神輿に乗せて若者を唆し、大人と対立させ、階級闘争を止揚し、「労働問題」「格差問題」を圧し潰して、庶民=労働者階級からの収奪を強めるために、気候変動を煽り立てている。
それを誤魔化すために、「このように考えると、環境問題、労働問題、格差問題等のそれぞれのテーマに強い関心のある人たちが、自分のテーマの方が重要であると言い争うのではなく、それらの問題をつなげて考えて、互いを応援したり、協力してシステムを変える働きかけをすることの重要性が浮かび上がってくるように思う」。
黄色いベスト運動はその事実を白日の下に曝け出したのだ。
旗色が悪いので、「この結果、市民の政治参加への要求が高まり、マクロン大統領は無作為抽出された150人の市民による気候市民会議を開催した・・・同様の市民会議は英国の議会によっても開催されている」と喚いているけれど、朝日新聞がそれを囃し立てている。[注2]
「くじ引き」市民、行政に提言 「気候市民会議」にチャレンジ 札幌市
欧州では2019年以降、くじ引きで選ばれた市民が、脱炭素社会へ移るために必要なことを議論し政府や議会に提言する「気候市民会議」が行われています。日本でも、50年に温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを宣言した札幌市で、昨年11~12月、試行されました。三上直之・北海道大学准教授らのチームが市の協力を得てオンラインで開催。無作為に選ばれた市民20人が4時間ずつ4回にわたって議論しました。
参加した橋本祥子さん(35)は、「違う世代、立場の方たちとじっくり話すことができ、知ったことや考えさせられたことは多いです」。専門家の話を聞いた後、1時間以上にわたり4人ずつのグループで話す時間があったことが特に良かったと言います。
例えば交通。車が減れば二酸化炭素の排出削減になりますが「自動車を持っている人が手放すにはどうすればいいか」が話題になりました。札幌市にあてはめ、自転車専用レーンがもっとできるといい、地下鉄の新しい路線ができるといい、と話が広がりました。走行中に二酸化炭素を排出しない電気自動車に乗る他の参加者から「北海道は寒いのでバッテリーが心配」と聞き、「車が必要な人もいる。寒冷地に強い電気自動車ができるといいと思いましたね」。
話し合った内容や参加者の意見は研究チームが提言書にまとめて市に提出。橋本さんは「会議の後、自分の生活がすぐに変わったわけではなく、地下鉄の新しい路線もすぐにはできませんが、これから動いていくこと。今後も開かれ、多くの人が参加できるといいと思います」。(神田明美)
(朝日新聞デジタル)
第3節で見たとおり、「国民は、ビジネス主導のイノベーションに『巻き込まれる』存在であり、CCS等の技術を『受容する』ことが期待される存在であり、ライフスタイルを転換するように『啓発される』存在として登場する」と批判めかしていたけれど、「日本政府としてもこのようなプロセスで国民を巻き込んだ議論を本格的に行うべきだと考えており、筆者は政府の審議会でもそのように発言している」ではないか!
気候市民会議において、国民は権力に「啓発され」「巻き込まれ」「受容する」存在として登場する。[注3]
なぜなら、庶民=労働者階級からの収奪を強めるために気候変動と煽り立てているから。
だから、「『庶民』こそが当事者である側面が大きいことを理解してほしい」と泣き喚きながら、「『関心が無い人すべてを説得している時間は残されていない』と言ったが、これは本当にそう思っている」
「当事者」の相手をしている「時間は残されていない」のは、収奪される「当事者」だから。
「その限られた時間の中で、いかに多様な人たちの有意義な対話の場を構築できるかが、これからも筆者の関心事である」のは、「グレた」娘を「『脳の多様性』だとみることができる」だの、「人類種の進化の過程で遺伝的な多様性として埋め込まれた」だのと褒め称えたのと全く同じ詭弁。
「労働問題」「格差問題」の「当事者」に多くの「時間は残されていない」。
だから、黄色いベスト運動が起こった。
けれど、「関心が無い人すべてを説得している時間は残されていない」と喚き立てて、黄色いベスト運動は傷つけられ、祖国をも追われた。
黄色いベスト運動に「時間は残されなかった」。
庶民=労働者階級からの収奪を強めるために気候変動と煽り立てているから、「気候市民会議」を開催しても、「労働市民会議」「格差市民会議」は開催されない。
「労働問題」「格差問題」を圧し潰すために、「筆者は、この気候市民会議に関心を持っており」
「搾取する階級」=「支配する階級」が「搾取される階級」=「圧迫される階級」の一部を「巻き込ん」で、「脱炭素 『搾取する階級』『支配する階級』が」を「脱炭素 主権者の市民が」と言い立て、搾取をさらに推し進めるのだ。
だから、「『関心が無い人すべてを説得している時間は残されていない』と言ったが、これは本当にそう思っている」
「気候市民会議」は庶民=労働者階級の分断工作。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p98より
[注1] 「ヨットで大西洋を横断」はこれだが、
2019年8月14日 17:07 発信地:ニューヨーク/英国
スウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリ(Greta Thunberg)さん(16)は14日、9月に米ニューヨークで開かれる国連会合に出席するため、排出物ゼロのヨットで英プリマスを出航する。
気候変動に対する政府の怠慢に抗議する学校ストライキで世界的な運動を巻き起こしたトゥンベリさんは、二酸化炭素を排出するという理由から飛行機の利用を拒否している。
そんなトゥンベリさんは良心の呵責(かしゃく)なく国連会合に参加できるよう、父のスバンテ(Svante)さんと旅路を記録するドキュメンタリー作家と一緒にレース用ヨットでニューヨークに向かうことを提案された。
マリツィアⅡ号(Malizia Ⅱ)と名付けられたヨットは全長18メートルで、デッキには最先端の太陽光パネルを備える。モナコ・ヨットクラブ副会長でモナコ公家の一員であるピエール・カシラギ(Pierre Casiraghi)氏と、世界一周を達成したことがあるドイツ人のボリス・ヘルマン(Boris Herrmann)氏がかじを取る。
プリマスからニューヨークまでの航海はおよそ2週間。ヨットは時速70キロで航行可能だが、ほとんどは向かい風の中を進むためそこまでの速度は出ない。
プリマスの港で最後の準備を進めていたヘルマン氏は、快適な乗り心地を求めているとした上で「目的は無事にニューヨークに到着すること」とAFPに語った。
トゥンベリさんは航海を経験したことはない。12日に初めて船に乗った際には酔ってしまったものの、海の旅を楽しみにしているという。
 英プリマスで、ニューヨークまで乗っていくヨットの上で取材に応じるスウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリさん(2019年8月13日撮影)。(c)Ben STANSALL / AFP
英プリマスで、ニューヨークまで乗っていくヨットの上で取材に応じるスウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリさん(2019年8月13日撮影)。(c)Ben STANSALL / AFP
(AFP / Alice RITCHIE)
何の訓練もしていない、「航海を経験したことはない。12日に初めて船に乗った際には酔ってしまった」娘が、ぶっつけ本番で本当に「ヨットで大西洋を横断したのか考えてみるとよい」。
出港するところだけを大々的に報じ、沖に出たら、フランス海軍の艦艇に乗り移り、軍用ヘリコプターでフランス軍基地に舞い戻り、モナコ公国のプライベートジェットに搭乗して、お忍びでニューヨークにひとっ飛びし、ヨットが米国東岸に近づくまでは、お忍びで超高級ホテルに滞在し、ヨットが近づいたら、モナコ公国の豪華ヨットに乗り込んでニューヨーク沖で待ち受け、そこから始めのヨットに乗り移り、再び、メディアが入港するところだけを大々的に報じて、市民を欺いたのであろう。
その証拠に、高校に進学できなかったにもかかわらず、「高校生環境活動家」と報じている。
[注2] 第1部第16章第2節の [注1] で紹介しているとおり、これ以前にも「市民との対話活動」と称して、市民を誑(たぶら)かそうとしていた。
けれど、市民から手厳しい批判を浴びていた。
(「本当に二酸化炭素濃度の増加が地球温暖化の原因なのか」より)
このような批判が出来る人は、それなりに勉強している人であり、「関心の高い人」。
それを「『関心が無い人すべてを説得している時間は残されていない』と言ったが、これは本当にそう思っている」と泣き喚き、対話を拒否。
卑劣にも、それを「しかし、これは対話の拒否を意味しているのではない。むしろ、その限られた時間の中で、いかに多様な人たちの有意義な対話の場を構築できるかが、これからも筆者の関心事である」と言い立てているのだ。
[注3] にもかかわらず、朝日新聞は「多様な声 気候政策に生かそう」と囃し立てている。
第8節でも指摘したとおり、民意を排斥しようと図るとき、殊更に「多様な声」と言い立てるのは左翼・マルクス主義の常套手段。
6.11 3.5%
国際主義エリートの投資家から資金を得て活動している環境団体に担ぎ出されたにもかかわらず、ダボスで国際主義エリート様から認められて国連に招かれ泣き喚いたにもかかわらず、「あなたの行動が、あなた自身のCO2を減らすだけでなく、システムを変えるメッセージになるように行動せよ。これが、筆者がグレタさんから学んだ格率である」のは、「エア科学者の行動が、労働力の価値を減らすだけでなく、新資本の形成によって資本価値の蓄積を促進するシステムに変えるメッセージになるように行動せよ。これが、筆者が国際主義エリート様から学んだ格率である」ことを、完全に自白している。
だから、尚もこんなことを言い立てている。
・・・前略・・・
3. 無関心の根底にある「負担意識」
ここまで見てきたように、日本における気候変動問題への無関心の根底にあるのが科学的知見の欠如であるようには筆者には思えない。それ以前の問題として、多くの人には科学的知見に目を向けず、科学的知見に触れたとしても受け止めずにやり過ごすことを、無意識にせよ選択させている動機が存在するのではないか。
筆者の仮説は、その動機の根底にあるのは、対策行動の「負担意識」ではないかということだ。つまり、気候変動を対策するためには、個々人が、時間、手間、注意力、快適さ、金銭等の自身の持つリソースを幾ばくか負担する必要があるという観念である。
平たくいえば、地球温暖化を止めるためには、個々人が我慢や経済的負担や面倒な行為や生活レベルの引き下げなどを受け入れる必要があるという認識を多くの人が前提としているのではないかと思うのである。
そして、この負担意識に対する反応は人によって異なる。環境問題への「意識が高い」人の多くは、進んでこの負担を受け入れようとし、負担を受け入れる自分に肯定感を感じ、社会の全構成員が同じように負担を受け入れることを望むだろう。
一方、それ以外の多くの人々は、無意識に負担を忌避する心情が働き、その結果として無関心になるのではないだろうか。もしくは、気候変動についての言説が、負担を受け入れない自分への批判に感じられるためにそれに反発し、人によっては懐疑論・否定論に同調するようになる。これらが「無関心」の根底にあるのではないかというのが筆者の経験に基づく仮説である。
日本において特に負担意識が高いことを示唆するデータは、2015年に行われた世界市民会議(World Wide Views on Climate and Energy)の結果の中に見てとれる(World Wide Views, 2015)。「あなたにとって、気候変動対策はどのようなものですか」という問いに対して、「多くの場合、生活の質を高めるものである」と回答したのは、世界平均の66%に対して日本では17%、「多くの場合、生活の質を脅かすものである」と回答したのは、世界平均27%に対して日本では60%であった。
また、傍証としては、「Yahoo!ニュース」で気候変動対策の必要性を訴える若者などの主張が紹介されると、必ずと言っていいほど「生活レベルを落とすことになるのをわかっているんでしょうか」といったコメントが匿名ユーザーから投稿され、多くの「いいね」が付くことが観察される。
4. 必要な「行動」とは何か
負担意識を前提とするとき、気候変動問題に関心を持った人が取るべきと想定されている「行動」は、主として自身の生活からのCO2排出(食生活に関していえばメタン排出も含む)を削減するための環境配慮行動やライフスタイルの変化である。
しかし、必要な「行動」をこのような枠組みでとらえることには、2つの面で問題がある。1つ目に、現在必要とされている気候変動対策(パリ協定の「1.5℃」を目指すのであれば、2050年前後に世界のCO2排出量を実質ゼロまで削減)の規模に対して、このような行動のみではまったく足りないことである。2つ目に、個々人がこのような行動で自分の役割を果たしたと思って満足してしまうと、結果的に現状の社会経済システムの許容につながることである。
では、本当に必要な「行動」とは何だろうか。その手がかりとして、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんがなぜ飛行機に乗らず、大西洋をヨットで横断したのかを考えてみるとよい。負担意識を前提とするならば、「私が飛行機に乗るのを我慢することで、一人分のCO2排出を減らしたい」、あるいは「私も不便を受け入れているのだから誰もがそうすべきだ」と解釈することになるだろう。
しかし、グレタさんは次のように発言している。
つまり、個人の変化も必要だが、本当に必要なのはシステム、つまり社会経済等の仕組みの変化だという。
また、彼女は次のようにも述べている。
彼女が飛行機に乗らないのは、システムの変化が必要であることを訴えるメッセージなのであり、誰もが飛行機に乗るべきでないとは言っていない。グレタさんに反発する無関心層はもちろんのこと、実は関心層の中の多くの人も、負担意識を前提としているため、このことをほとんど理解できていないのではないか。
筆者もグレタさんと同様に以下のように考えている。個人に必要な行動としてより本質的なのは、自身の生活で発生するCO2をこまめに減らすことよりも、システムの変化を後押しするための意見表明、投票行動、消費行動における選択、地域社会での取り組みへの参加などである。
個人の環境配慮行動については、自身の意見と生活を整合させるためといった意味もあろうから否定するつもりはないし、社会に対するメッセージであるという意識を持って環境配慮行動をとるならば、なお良いだろう。しかしいずれにせよ、気候変動問題に関心を持った人々が、個人の環境配慮行動をとることで「自分に応分の負担をした」と思って満足して終わりにしてしまう状況は望ましくない。
5. システムの変化を起こすために
筆者の考えでは、システムの変化を起こすことを最優先で考えた場合に、社会の構成員の大部分が問題に関心を持つ必要は必ずしもない。このことはトランジション・マネジメントといった分野で理論化されていると想像するが、筆者はあまり詳しくないので、筆者自身が実感している例を用いて説明したい。
筆者が持ち出す例は「分煙」である。30年ほど前は、路上、飲食店、交通機関、職場等で喫煙できることが当然だったが、現在では考えられない。2002年に健康増進法で受動喫煙防止が努力義務となり(改正により2020年よりさらに強い義務化)、飲食店等も分煙や禁煙で経営するのが当然となり、大多数の喫煙者が分煙ルールに従うというシステムの変化が生じた。
社会の構成員の大部分がこの問題に関心をもったわけではないにもかかわらず生じたこの変化は、受動喫煙の健康被害を立証した医師、嫌煙権訴訟を闘った原告や弁護士などの「声を上げた人たち」に加え、それらを支持した一部の人たちの存在に因ったのではないか。そして、社会の構成員の大部分は、無関心でいるうちにいつの間にか生じたシステムの変化に受動的に従っただけである。
人々の価値観は多様であるため、社会の大部分の人たちが気候変動問題に本質的な関心を持つことを期待するのは難しい。このとき、気候変動に無関心な人を非難する筋合いもない。彼らは他の社会問題には強い関心を持っているかもしれないし、気候変動に関心がある人が他の社会問題に関心を持っているとは限らないからである。
このように考えると、気候変動対策のためのシステムの変化を起こすための筋道は、問題に本質的な関心を持った一部の人たち(多いほうがいいが、大多数である必要はない)がシステムに本質的な働きかけを行うことであり、大多数の人たちがわずかな関心を持って自分にできる環境配慮行動を人知れず行うことではない。
例えば、日本のすべての電源が再生可能エネルギーになれば無関心な人がいくら電気を使ってもCO2は出ないのであるし、新築住宅にネットゼロエネルギーハウス(ZEH)が義務化されれば無関心な人でもZEHを建てるようになるのだから、早くそのような状態を作ることが重要なのである。
6. 本質的な「関心」の持ち方
では、気候変動問題に本質的な関心を持つとはどんな状態だろうか。筆者が本質的と呼びうるのは、気候変動問題が自身の「人生のテーマ」になるほどの関心の持ちようである。
気候変動のリスクを自身や大切な人たちの生死にかかわるような「実存的な」リスクだととらえた人、あるいは先進国がこれまで排出した温室効果ガスによって発展途上国の脆弱な人々や将来世代が深刻な被害を受けることを倫理的に許容できないと強く感じた人、社会の脱炭素の必要性・緊急性・重大性を理解し、それに全力で取り組むことに人生の意義を見出した人、などがそれにあたるだろう。
欧米にはそういう政治家がいるし、セレブリティ(例えば、俳優のレオナルド・ディカプリオ)もいる。グレタさんをはじめとする気候ストライキを行う若者たちも、おそらく大部分はこのような関心を持っている。
日本でも、環境NGOで活動する人たちや気候マーチを行う若者たちがいるが、おそらく他国に比べて規模が非常に小さく、裾野の広がりが狭い。欧米では、環境NGOに共感するが自分で活動するほどの時間は割けないという人たちがNGOに寄付をすることが多いと聞くが、日本では環境NGOは社会から十分な認知を得ておらず、「自分とは関係ない極端な主張の人たち」だと思われている印象がある。
このような日本の特殊性は、日本の文化的な特徴に因る部分もあるだろうから、簡単には変わらないかもしれない。しかし、前述した「負担意識」のナラティブを変え、気候変動対策とは本質的には社会をアップデートする前向きなシステム変化であるという認識を広めていくことができれば、状況は改善するのではないか。
つまり、人々の気候変動問題への無意識な拒否感を弱め、潜在的な関心層が本質的な関心を獲得する機会を増し、その裾野に本質的な関心層ではないにしても彼らに共感し、彼らを支持する層を厚くすることができるのではないか。
・・・後略・・・
(「なぜ日本人は気候変動問題に無関心なのか?」より)
第3節で見たとおり、カーボンプライシングと喚き立てたけれど、「社会の全構成員が同じように負担を受け入れ」、脱炭素に投資(ESG投資)させれば、自らが負担した額の何百万倍ものリターンが得られるから、投資家の富裕層は「負担を受け入れる自分に肯定感を感じ、社会の全構成員が同じように負担を受け入れることを望む」。
「社会の全構成員が同じように負担を受け入れ」させねばならないから、「気候変動問題に関心を持った人々が、個人の環境配慮行動をとることで『自分に応分の負担をした』と思って満足して終わりにしてしまう状況は望ましくない」
既に再生エネにおいて、「社会の全構成員が同じように負担を受け入れる」固定価格買い取りが出来ている。
第3章で解説したとおり、再生エネは剰余価値を産み出さないから、庶民=労働者階級の所得を奪い盗って投資家が利を貪っている。
投資家が利を貪るためだから、主権者である国民の頭越しに固定価格買い取り制度を推し進めた。
だから、第4節で糾弾したにもかかわらず、執拗に「社会の構成員の大部分は、無関心でいるうちにいつの間にか生じたシステムの変化に受動的に従っただけである」と言い張り続ける。
カーボンプライシングで電気代を高騰させて、「日本のすべての電源が再生可能エネルギーになれば」、庶民=労働者階級は所得が激減して電気が使えなくなるから、「無関心な人がいくら電気を使ってもCO2は出ないのであるし」と囃し立てる。
剰余価値を奪い盗ることに飽き足らず、労働力の価値をも下げて、投資家が富を肥やすこと、それが「システムの変化を起こす」こと。
そのために気候変動と煽り立てる。
だから、また、また、また、投資家の方を向いて、「気候変動対策とは本質的には社会をアップデートする前向きなシステム変化である」と言い張り、「『負担意識』のナラティブを変え」と庶民=労働者階級を罵っている。
「日本の文化的な特徴に因る部分もあるだろうから、簡単には変わらないかもしれない」と泣き喚いているけれど、「欧米では、環境NGOに共感するが自分で活動するほどの時間は割けないという人たちがNGOに寄付をすることが多い」のは、我国より桁違いに格差が大きいからに他ならない。
現に、第4章第6節で解説したとおり、世界一の格差社会のカリフォルニアは気候変動対策の最前線を走っている。
第3節でも引用したけれど、
エンゲルス「共産党宣言英語版への序文」、岩波文庫「共産党宣言」p27より
「欧米では、環境NGOに共感するが自分で活動するほどの時間は割けないという人たちがNGOに寄付をすることが多い」は、「経済的生産と交換の支配的な様式、およびそれから必然的に生れる社会組織」という「土台のうえに築かれ」ている。
「日本の文化的な特徴に因る部分もあるだろうから、簡単には変わらないかもしれない」と泣き喚くのは、「気候変動対策とは本質的には富裕層の富をアップデートする後ろ向きなシステム変化である」ことをハッキリと示している。
前節で見たとおり、「環境問題は労働問題や格差問題と相反するものではない」と泣き喚いていたけれど、「社会の全構成員が同じように負担を受け入れること」は「労働問題」「格差問題」の解消に相反する。
庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を奪い盗っている投資家どもに「負担」させねば、「労働問題」「格差問題」は解消しない。
もちろん、投資家の富裕層にそれは受け入れ難い、絶対に阻止しなければならない。
だから、江守正多らエア科学者に気候変動と煽り立てさせた。
第4節で説明したとおり、庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を糧にしているにもかかわらず、「無意識に負担を忌避する心情が働き、その結果として無関心になるのではないだろうか。もしくは、気候変動についての言説が、負担を受け入れない自分への批判に感じられるためにそれに反発し、人によっては懐疑論・否定論に同調するようになる。これらが『無関心』の根底にあるのではないか」と泣き喚くのは、その事実をハッキリと示している。
「グレた」娘の父親は俳優で母親は歌手だから、やはり、何の価値も産み出していない。
だから、「グレた」娘の生活も、やはり、庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値の上に成り立っている。
第8節で見たとおり、「11歳のときに彼女は地球環境について心配するあまり、2か月もの間、ほとんど会話も食事もできなかった」けれど、それも、庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を糧にしているから。
両親が(剰余)価値を産み出している家庭の子女ならそんなことにはならない。
庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を奪い盗って富を築き上げた投資家の富裕層が、庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を糧にしている環境団体を使い、庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を糧にしている「グレた」娘を担ぎ出して祭り上げ、庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値を糧にしている江守正多らが躍起になって、グレタさん、グレタさん、と囃し立て続ける。
庶民=労働者階級が産み出した(剰余)価値に胡座をかいている連中が、庶民=労働者階級からの収奪を強めるために、手を携えている。
「気候変動対策のためのシステムの変化を起こすための筋道は、問題に本質的な関心を持った一部の人たち(多いほうがいいが、大多数である必要はない)がシステムに本質的な働きかけを行うことであり、大多数の人たちがわずかな関心を持って自分にできる環境配慮行動を人知れず行うことではない」と言い張っているのは、前章第19節でも解説したとおり、「3.5%」と言うこと。[注1]
逆に言うと問題は、「どうやって本質的な関心を持つ人を社会の中で3.5%つくるか」ということなのです。みんながちょっとずつ関心を持ち、ちょっとずつ省エネしたりプラスチックを使わないようにしても、この問題は本質的に解決されません。
「本質的な関心を持つ人」というのは、例えば「気候変動が本当に、自分や大切な人の生命に関わるような脅威である」とすごく思った人。あるいは、「気候変動は将来世代や途上国の人々を、その人たちが全然CO2を出していないのにすごく苦しめるから、倫理的に許せない」と強く思った人。または、「気候変動を何とかするため、脱炭素化のためなら人生を賭けてその仕事をしよう」と思った人という、とにかく強烈なコミットメントを気候変動に持てる人口が3.5%になれば、社会は変わるんじゃないかと思うんです。
例えばアメリカを見ていると、環境に特にアンテナを立てて強い発信をしているレオナルド・ディカプリオみたいな人がいます。またはイギリスでも、エクスティンクション・リベリオンのデモで著名人が逮捕されたり、欧米ではそういうことがあります。でもそれは日本にはない。政治家も、そこまで強い関心を持っている方というのは、いるかどうかもわからない。
環境NGOにそういう人はいますが、そもそも社会にあまり存在を知られていないし、知られていたとしても「自分とは関係のない、極端な考えの人たち」という風に思われてしまうんじゃないかということで、日本ではあまり広がっていません。
去年はスウェーデンのグレタさんが広く知られましたが、学生のムーヴメントが起きて、世界で約700万人がグローバル・ストライキに参加したといいます。そのうちドイツでは百数十万人が参加したとのことで、それはドイツ人口の2%に近くて、3.5%も視野に入ってきます。
対して日本では、参加者は5000人でした。全然足りてない(笑)。
ですから3.5%の人たちがもし関心を持つと、政治システムに働きかけるでしょうし、経済システムに対しても然りで、そのことで制度やシステムが変わるでしょう。そうすると残りの96.5%の人たちは、別にそんなことに関心を持たなくても、仕組みが変わっちゃったので、もう勝手にCO2を減らすしかなくなります。
すべての電力会社が再エネ100%になれば、再エネを使う以外はなくなります。車も電気自動車しか売っていなければそれを買うことになるし、家を建てようと思ってZEHしかなければ、ZEHを建てることになります。
そして、そういう社会システムにするために積極的に後押しをする、「本質的な興味を持った人」がある程度必要ということです。最近僕は、じゃあ「そこを目指すべきじゃないか」ということを考えています。
(「【第2回】江守正多|コロナと気候変動、その共通点と相違点」より)
第3節で見たとおり、そして、先の文章でも「『多くの場合、生活の質を脅かすものである』と答えた人が世界平均の27%に対して日本は60%であった」と泣き喚いていた。
「社会の3.5%の人が参加すると、ムーヴメントは成功する」のなら、「社会の60%の人が参加すると、ムーヴメントは成功する」から、脱炭素は成功しない。
それなのに、なぜ「そうすると残りの96.5%の人たちは、別にそんなことに関心を持たなくても、仕組みが変わっちゃったので、もう勝手にCO2を減らすしかなくなります」のか。
60%ではダメで「3.5%」でなければならない、ということである。
「96.5%」が産み出した価値を糧にしている少数派でなければならないのだ。
それは支配階級の思想。
マルクス&エンゲルス「ドイツ・イデオロギー」、岩波文庫p110-111より
労働者が化石燃料という価値を産み出し、それを使ってさらに大きな価値を産み出したのを、奪い取って富を肥やしたのは投資家なのだから、環境団体はその資金で活動しているのだから、そして、江守正多や「グレた」娘やディカプリオらは労働者階級が産み出した価値を糧にしているのだから、化石燃料で利を得たのは「3.5%」。
にもかかわらず、「そうすると残りの96.5%の人たちは、別にそんなことに関心を持たなくても、仕組みが変わっちゃったので、もう勝手にCO2を減らすしかなくなります」と言い放つのは、お前たち愚かな労働者階級がCO2を排出したのだと罵って、庶民=労働者階級からの収奪を強めるために、気候変動と煽り立てていることを明確に示している。
「そうすると残りの96.5%の人たちは、別にそんなことに関心を持たなくても、仕組みが変わっちゃったので、もう勝手にCO2を減らすしかなくなります」は、「そうすると残りの96.5%の人たちは、別にそんなことに関心を持たなくても、収奪の仕組みが変わっちゃったので、もう勝手に命を減らすしかなくなります」に他ならない。
「そういう社会システムにするために積極的に後押しをする、『本質的な興味を持った人』がある程度必要ということです。最近僕は、じゃあ『そこを目指すべきじゃないか』ということを考えています」は、「庶民=労働者階級からの収奪を強める社会システムにするために積極的に後押しをする、『本質的に畜生な興味を持った人』がある程度必要ということです。最近僕は、じゃあ『そこを目指すべきじゃないか』ということを考えています」に他ならない。
それは黄色いベスト運動が立証した。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p98より
[注1] NHKでも「3.5%」と泣き喚いていた。

「わたしたちができる『5つのこと』をリメイクしてみた!」より

「わたしたちができる『5つのこと』をリメイクしてみた!」より

「わたしたちができる『5つのこと』をリメイクしてみた!」より
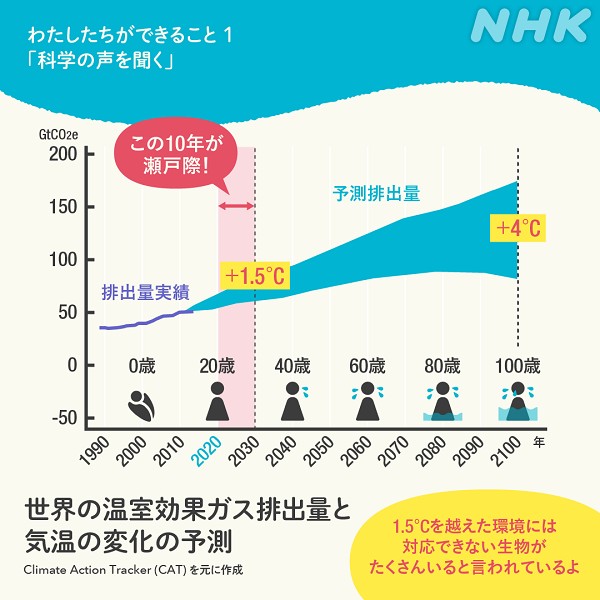
「わたしたちができる『5つのこと』をリメイクしてみた!」より

「わたしたちができる『5つのこと』をリメイクしてみた!」より
6.12 気候正義
だから、気候正義と喚き立てている。
政府は複数の審議会の議論を通じてエネルギー基本計画や2030年排出削減目標(NDC)の見直しを急ぐ。多くの企業や自治体も次々に2050年の脱炭素化を宣言し、行動計画などを作成・公表し始めている。
外交日程も目白押しだ。今月16日には日米首脳会談、同22~23日には米大統領主催の気候サミット、6月にG7、10月にG20、そして11月に国連のCOP26があり、その都度に日本の本気度が世界から問われることになる。
未だに保守的な勢力との綱引きが多少はあるものの、日本でも多くの主体が脱炭素化に本気になってきたようにみえる。しかし、筆者にはそこに肝心なものが欠けているように思えてならない。若者が指摘した「静かな暴力」
先日、それを鋭く指摘されたと感じた場面があった。
気候変動対策を検討する審議会の一つである、中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合の第3回が2月26日にオンラインで開催され、筆者も委員として出席した。この回の主な議題は「将来世代からのヒアリング」であった(この議題は画期的である)。
気候変動問題等に関する活動を行う高校生や大学生の youth (若者)世代3団体、Climate Youth Japan、Fridays for Future Japan(FFFJ)、Japan Youth Platform for Sustainability から意見を聞いた。
どの団体の発表も意義深いと感じるものだったが、ここでは特にFFFJの発表を取り上げたい。
彼らが明確に主張したのは「気候正義」(Climate Justice)であった。彼らの一人は「気候変動に加担していない人々が最も影響を受ける不条理」への憤りを感じたことから声を上げ始めたという。
すなわち、気候変動で激化する災害により生活の基盤を失い難民化する発展途上国の人々は、我々に比べてほとんどCO2を排出していない。CO2を排出しながら暮らす先進国の我々の生活は、彼らの犠牲の上に成り立っているというのである。FFFJはこれを「静かな暴力」と呼んだ。
同様な格差の構造は、一国内での所得水準や性別の違いによっても生じる。例えば貧しい人や女性ほど災害時に被害を受けやすいからだ。
そして、FFFJの彼ら自身が直面するのが世代の違いによる格差である。気候変動でより深刻な被害を受けるのは将来世代であるにもかかわらず、対策の意思決定は上の世代によって行われている。
我々の多くは、これらの格差構造から恩恵を受け、自分が他者に対して振るう「静かな暴力」から目を背け続けている。
FFFJの若者たちは、このことをえぐるように指摘した。気候正義の専門家の見解
この考え方は始めて聞く人にも理解しやすいものだと思うが、これを「気候正義」と呼ぶことについては少し注釈が必要かもしれない。
日本語で「正義」というと「正義の味方」を思い浮かべ、反対語は「悪」であり、絶対的で排他的な正しさが主張されていると感じる人が多いのではないか。
しかし、英語のjusticeは、just、つまり丁度よいことが語源で、裁判で量刑が丁度よく決められるように、釣り合いの取れた正しさを指す。日本語では「公正」と訳す方が理解しやすいかもしれない。ちなみにjusticeを「正義」と訳す場合、反対語は「悪」ではなく「不正義」(injustice)である。
正義は本来、倫理学や哲学の概念であり、筆者にはこれ以上の解説はできないので、法哲学の専門家で編著書に『気候正義 地球温暖化に立ち向かう規範理論』のある、京都大学の宇佐美誠教授に、今回のFFFJの発表についてコメントを頂いた。
環境省と経産省の審議会の合同部会におけるFFFJの発表を閲覧し、大いに説得力を感じた。
特に注目されるのは、気候変動のインパクトが2つの意味で不平等に表れることを強調している点である。
若年層は壮年層・老年層よりも、また将来世代は現在世代よりも深刻なインパクトを受けるだろうことについては、最近には社会的認知が広がりつつあるように見受けられる。
他方、同一世代内でも、家父長制的社会での女性や、社会を問わず低所得層・先住民族など、社会的経済的に不利な人々が、気候変動のインパクトを集中的に受けつつあり、今後はいっそう受けるだろうという傾向は、日本ではいまなお知られていない。
これら2つの意味での不平等を正面から受け止め、事態の改善をめざす際の理念が、〈気候正義〉に他ならない。
これを訴えるFFFJの主張に、大人世代は真摯に耳を傾けるべきだろう。
(京都大学 大学院地球環境学堂 宇佐美 誠)
FFFJの主張の意義が専門家からも裏付けされたといえるだろう。
海外と日本の認識の隔たり
このClimate Justiceという言葉は、パリ協定の条文の前文にも登場する。
アイルランド元大統領のメアリー・ロビンソンはClimate Justiceの唱道者としてよく知られている。
そして何よりも今のタイミングで重要なのは、同様の概念である"Environmental Justuce"(環境正義)を、米国のバイデン政権が大きく掲げていることだろう。
バイデンとハリスは大統領選期間中から、企業による乱開発や汚染に長く苦しんできた貧困地域、有色人種、先住民族などへの不正義を是正するという環境正義の公約を掲げてきた。公約には気候正義もセットで登場する。バイデン政権は司法省内に「環境・気候正義部門」を設置して汚染企業への住民の訴訟を支援するとともに、連邦政府全体で環境・気候正義に優先的に取り組む方針である。
このように、気候正義は欧米ではかなりメジャーな概念であるが、日本では若者や環境NGOの主張の中でしか耳にすることがない。
日本で脱炭素に取り組む動機は、企業においても政府の産業政策においても金融やサプライチェーンなどの外圧の影響が大きいようにみえるし、自主的な動機を挙げたとしても自身への異常気象被害への危機感が主なものだろう(それももちろん大事だが)。世界の脱炭素化が必要な理由を問われたときに気候正義を挙げられる人は、日本の政治や企業のリーダーにほとんどいないのではないか。
気候正義をどれだけ重視するかは各人の価値観や信条によるとしても、少なくともそのような議論についての理解がなければ、欧米のリーダーからは脱炭素化の理念の底の浅さを見透かされてしまうおそれがあると思う。
日本の外務省がこのことを理解していないはずはないので、おそらく菅首相は16日の日米首脳会談で、環境正義や気候正義を口にするだろう。そうであるならば、菅首相や小泉気候変動担当相が、ぜひご自身の言葉で、気候正義についてのお考えを国内外に発信してくださることを切に願う。
若者の声に謙虚に学べるかが問われている
審議会での将来世代からのヒアリングに話を戻そう。当日は最初に事務局(環境省)から温室効果ガス排出の現状等についての説明があり、続いて上述の若者3団体の発表があった後、委員が意見を一巡述べた。
少なくない委員が若者に発表への感謝を伝え、若者に質問する委員もいたが、「静かな暴力」といった彼らの主張の核心を正面から受け止めた応答は委員からほとんど聞かれなかった。若者の意見に全く言及しない委員もいた。
最後に、3団体の若者が委員からの質問に応答したが、途中で事務局の通信トラブルがあったり割当時間を超過して発言した委員が多かったために会議の残り時間は短く、彼らは急かされて話した。(時間が足りないのは彼らのせいではなく、ここにも小さな不正義の構造がみられた)
後日、FFFJは彼らのウェブサイトに審議会への提言を発表した。要点は以下のとおりである。
現状の審議会は各委員が一方的にポジショントークをする場になっている。双方向的に議論するプロセスが必要。
審議会の委員に倫理的な分野の専門家が必要。また、当事者である若者の継続的な参画が必要。
環境省と経産省の省益のすり合わせでなく、省庁を超えたビジョンや問題意識の共有が必要。
複数の審議会間の関連性が国民にとってわかりにくい。政策決定プロセスの可視化が必要。
筆者はどの点にも首がもげるほど同意する。特に1は「王様は裸じゃないか」と指摘された気分だ。審議会はこういうものだから仕方がないと思っていた自分が恥ずかしく感じられる。
さらにFFFJは、当日の各委員の発言に対するコメントを発表している。委員の中には、若者の発表を上から目線で論評した人もいだだろう。しかし、これを見ると逆で、各委員がその発言を彼ら若者をはじめ関心のある国民の目から厳しく評価される立場にあることを思い知らされる。
彼らの声に対して、プライドを取り繕うために無視したりマウントを取り返しに行くのではなく、自分たちが学ぶ機会ととらえて謙虚に耳を傾ける関係者が多く現れることを願う。
-------
最後に少し先回りして論じておくが、FFFJのような倫理的な主張に対して、ネット上では冷笑的な反応が多いだろう。
「誰かの犠牲の上に成り立つ生活が嫌なら、原始人みたいに生活して下さい」というような反応がきっとたくさんある。
確かに、気候変動に限らず、我々の社会は様々な格差構造の上に成り立っており、それをすべて解消しようとするのは理想主義的に過ぎるのかもしれない。
しかし、だからといって現実を受け入れて諦めましょうというのは、古い常識にとらわれた考え方だと思う。我々は少なくとも、格差が一つ一つ是正されていく社会の変化を望むことができる。
特に気候変動の場合は、それを止めることが格差の是正につながると同時に人類全体にとっての安全保障でもあり、かつ出口の方向性(=社会の脱炭素化)が見えている。出口を目指すことが既に世界のトレンドにもなっている。
人類は奴隷制も植民地主義も卒業したのだから、化石燃料文明も卒業するに違いないと筆者は信じている。
若者は臆することなく倫理的な主張をしてほしい。
きっと時代が後からついてくるのだから。
(「日本の気候変動対策に欠けているもの ―我々は若者の声に学べるか」)
「我々の多くは、これらの格差構造から恩恵を受け」と喚き立てているけれど、第8節でも説明したとおり、化石燃料の「恩恵を受け」ているのは、この若者ら。
「CO2を排出しながら暮らす先進国の我々の生活は、彼らの犠牲の上に成り立っている」のなら、「気候変動で激化する災害により生活の基盤を失い難民化する発展途上国の人々」に最も犠牲を強いているのは、この若者らのはず。
己らこそが「これらの格差構造から恩恵を受け、自分が他者に対して振るう『静かな暴力』から目を背け続けている」にもかかわらず、「『気候変動に加担していない人々が最も影響を受ける不条理』への憤りを感じた」のは「不条理」。
ということは、「不条理」を遂行するために、一部の愚かな若者に「『気候変動に加担していない人々が最も影響を受ける不条理』への憤りを感じた」と泣き喚かせている、ということ。
第4章第12節でも解説したとおり、先進国が先進国であるのは、労働者がより多くの富=剰余価値を創り出してきたから。
それに応じて労働力の価値が高まる、つまり、労働者の生活が豊かになるのは当然。
資本はより多くの剰余価値を得ようと生産力を高め、その結果、商品が豊富になるけれど、売れなければ剰余価値を実現できないから、労賃は上がらざるを得ないわけである。
その一方で、第1章第2節で解説したとおり、生産性が向上して必要労働時間が低下してきたということは、先進国の労働者はより強く搾取されてきたということ。
マルクス「資本論」、岩波文庫第三巻p91より
先進国がより多くのCO2を排出してきたということは、先進国の労働者がより強く搾取され続けてきたということなのだ。
それでも、先進国の労働者は資本家(投資家)と戦い労働力の価値を上げてきた。
「CO2を排出しながら暮らす先進国の我々の生活は、彼らの犠牲の上に成り立っているというのである。FFFJはこれを『静かな暴力』と呼んだ」のは、先進国の労働力の価値を下げさせ、一般的利潤率低下を阻止するという「不条理」を遂行するために、投資家(の僕の環境団体)が、飼い犬の江守正多らエア科学者に人為的(排出CO2)温暖化を煽り立てさせ、一部の愚かな若者を唆し扇動していることを、ハッキリと示している。
「これらの格差構造から恩恵を受け、自分が他者に対して振るう『静かな暴力』から目を背け続けている」はずの若者に大人たちを攻撃させれば、投資家が「労働者を搾取して創り出した格差構造から恩恵を受け、自分が他者に対して振るう『静かな殺戮』から目を背け続ける」ことができるのだ。
「気候正義は欧米ではかなりメジャーな概念であるが」、第4章第9節で解説したとおり、我国の累積排出量は発展途上国並み。
ところが、江守正多はその事実に知らぬ顔の半兵衛を決め込み、第8節で見たとおり、「日本の石炭火力発電の新設が世界から批判されていること。これまで一部の関心がある人たちの話題でしかなかったこれらのことが、今週、一気に日本全国の『お茶の間』に届いたことに、筆者は興奮を隠せない」と悦んだ。
ここでも「その都度に日本の本気度が世界から問われることになる」、「少なくともそのような議論についての理解がなければ、欧米のリーダーからは脱炭素化の理念の底の浅さを見透かされてしまうおそれがあると思う」と泣き喚き続ける。
「FFFJの若者たちは、このことをえぐるように指摘した」と喚いたのは、日本国民の肉をえぐるために温暖化を煽り立て続けてきたことを、ハッキリと示している。
「FFFJの彼ら自身が直面するのが世代の違いによる格差である」と泣き喚いているけれど、格差に「世代の違い」は無い。
前章第20節の [注1] で見たとおり、お年寄りの多くが貧困線上にいる。
前節でも指摘したとおり、格差は階級対立の問題。
エンゲルス「空想より科学へ」、岩波文庫p61より
投資家が庶民=労働者階級からの収奪を強めるためには、「格差問題」を圧し潰さねばならない。
そのためには階級対立を止揚しなければならない。
そのために、世代間の対立を煽らねばならない。
「FFFJの若者たちは、このことをえぐるように指摘した」のは、シャイロックのように投資家の富裕層が庶民=労働者階級の肉を「えぐる」ために、飼い犬の江守正多らエア科学者に人為的(排出CO2)温暖化を煽り立てさせ、社会的意識の全く欠落した愚か者を唆し、「気候変動でより深刻な被害を受けるのは将来世代であるにもかかわらず、対策の意思決定は上の世代によって行われている」と泣き喚かせていることを、物の見事に自白したのだ。
マルクス「経済学・哲学草稿」、岩波文庫p20より
「グレた」娘を担ぎ出して神輿に乗せ、同世代の中で最も破廉恥で醜悪な連中を唆し組織化して、若者が、若者が、と喚き続けてきたけれど、真実を曝かれてしまい、さすがに旗色が悪くなったので、今回は宇佐美とやらにも喚かせている。
しかし、第9節でも指摘したとおり、今がなければ未来はない。
「将来世代は現在世代よりも深刻なインパクトを受けるだろうことについては、最近には社会的認知が広がりつつあるように見受けられる」と言い張る輩は、「『社会的経済的に不利な人々』の未来を奪おうと考えているように見受けられる」
その証拠に、「グレた」娘は黄色いベスト運動粛清の先頭に立った。
前章第4節で解説したとおり、自らは「気候変動のインパクトを全く受けていない」にもかかわらず、前章第19節で解説したとおり、世界一の格差大国で何不自由ない生活を送っているにもかかわらず、前章第1節で紹介したとおり、国連では「自らの『夢』や『子どもらしい時期』が奪われたことへの不満をぶつけた」。
「社会的経済的に不利な人々」を全く顧みない。
先に見たとおり、「スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんがなぜ飛行機に乗らず、大西洋をヨットで横断したのかを考えてみるとよい」と泣き喚いていたけれど、富裕層の全面的な支援を受けていた。
そんな「グレた」娘に続け~、と喚き立てているFFFの連中も、「社会的経済的に不利な人々」を全く顧みない。
前章第17節で見たとおり、「FFF東京オーガナイザー」のガキは朝日新聞がブルームバーグ様と手を組んで開催したシンポジウムに」招かれ、「世界は気候変動対策をビジネスチャンスととらえています」と喚き立てていた。
そのガキは、そして、前章第19節で採り上げたブサイクなモデルも、「ダイベストメント」で投資家を正当化する「350.org」のメンバー。
「これら2つの意味での不平等を正面から受け止め」と言い張るのなら、「社会的経済的に不利な若者」に主張させねばならないけれど、FFFは該当しない。
第9節で指摘したけれど、本当に気候危機なら、「社会的経済的に不利な人々」を救うために気候変動対策をと言えば、それで十二分。
わざわざ「これら2つの意味での不平等を正面から受け止め」るのは、「事態の改善をめざす際の理念が、〈気候正義〉に他ならない」が、「富裕層の資産の改善をめざす際の理念が、〈気候正義〉に他ならない」ことを示している。[注1]
前章第19節でも引用したけれど、
エンゲルス「フォイエルバッハ論」、岩波文庫p57-58より
「気候正義」は「一階級による他階級のできるかぎりの搾取のうちにあらわれるのである」!
前節で見たとおり、「『庶民』こそが当事者である側面が大きいことを理解してほしい」と泣き喚いていたくせに、「若者の声に謙虚に学べるかが問われている」「当事者である若者の継続的な参画が必要」と泣き喚く。
「同一世代内でも、社会的経済的に不利な人々が、気候変動のインパクトを集中的に受けつつあり、今後はいっそう受けるだろう」なら、「社会的経済的に不利な人々の声に謙虚に学べるかが問われている」にもかかわらず、「この回の主な議題は『将来世代からのヒアリング』であった(この議題は画期的である)」と囃し立て、「自分たちが学ぶ機会ととらえて謙虚に耳を傾ける関係者が多く現れることを願う」。
「当事者」でない若者を押し立て、「当事者である若者の継続的な参画が必要」と泣き喚く。
なぜなら、当事者を参画させたら一大事だから。
「『多くの場合、生活の質を脅かすものである』と回答したのは、世界平均27%に対して日本では60%であった」と泣き喚いていたことからも明らかなとおり、そして、黄色いベスト運動が示したとおり、「当事者」のはずの「社会的経済的に不利な人々」は、固定価格買い取り制度やカーボンプライシングを非難するから。
投資家の富裕層の資産を没収しろ、と主張するから。
そんなことになれば本末転倒だから。
だから、当事者であるはずの市民を置き去りにして、「きっと時代が後からついてくるのだから」と言い放つ。
第4節で見たとおり、市民を見下して「彼らは新しい常識にいつのまにか従うようになるだけだろう」と高言したけれど、それと同じ。
「絶対的で排他的な正しさが主張されていると感じる人が多いのではないか」と言い逃れをしているけれど、「時間が足りないのは彼らのせいではなく、ここにも小さな不正義の構造がみられた」と泣き喚き、「FFFJのような倫理的な主張に対して、ネット上では冷笑的な反応が多いだろう」と泣き喚き、「若者は臆することなく倫理的な主張をしてほしい」と言い張るのは、「絶対的で排他的な正しさが主張されている」
「絶対的で排他的な搾取の正しさが主張されている」
当事者であるはずの市民が置き去りなのに、「出口を目指すことが既に世界のトレンドにもなっている」のは、「一般的利潤率低下からの出口を目指すことが既に支配階級の世界のトレンドにもなっている」から。
そのためには、庶民=労働者階級からの収奪を強め、労働力の価値を引き下げねばならず、そのために、江守正多らエア科学者が気候変動を煽り立て、一部の愚かな若者どもを扇動している。
第4節で説明したとおり、江守正多らに倫理観は皆無。
そんな輩が「若者は臆することなく倫理的な主張をしてほしい」のは、その事実を明確に示している。
第2節で見たとおり、「奴隷制が廃止された際も、奴隷所有者に補償があった」と言い立てたけれど、「人類は奴隷制も植民地主義も卒業したのだから、化石燃料文明も卒業するに違いないと筆者は信じている」と泣き喚き、その実は、進化した「奴隷制と植民地主義」を推し進めようというのだ。
マルクス&エンゲルス「共産党宣言」、岩波文庫p98より
[注1] 前章第16節で採り上げた2021年10月19日の朝刊紙面でも喚いていた。
第4章第5節で説明したとおり、朝日新聞社員の平均年収は1300万円で、最上位1%の富裕層。
格差構造の最上位に位する「大人たち」が、「グレた」娘やFFFを盾にして、庶民=労働者階級に指突きつけて「大人たちは」と罵り続けているにもかかわらず、そんな新聞紙上で「いずれこういう時が来ると思っていた」と囃し立てている。
そのことだけを以てしても、「事態の改善をめざす際の理念が、〈気候正義〉に他ならない」が、「富裕層の資産の改善をめざす際の理念が、〈気候正義〉に他ならない」ことは明らかであろう。
さすがに旗色が悪くなったので、その後、こんなことを言っていた。























最近のコメント