今日今晩は。
「国際環境NGO(嘘)RealCrazyClimate」の会員某で~~~す。
「『温暖化で沈む国』の全く不都合な真実」の第7節で解説しているにもかかわらず、そして、2019年9月22日の投稿、9月24日の投稿、11月16日の投稿、12月25日の投稿で糾弾したにもかかわらず、元旦の1面で泣き喚いてやがった!
「温暖化の影響で(潮位が上がり続けて)冬場の高潮の頻度が増え、20年前には数年に1度だった大規模な浸水が、1年に何度も起きるようになった」のなら、なぜ、こんなことが起きるんだ?
伊ベネチアで今度は海面が極端に低下、ゴンドラも漕げず
2020/1/15(水) 16:18配信
昨年11月、約50年ぶりの高潮で市内の大部分が浸水した伊ベネチアで、今度は水位が異常に下がってしまった。名物のゴンドラも、一部で運航ができない状態になっている。
「水の都」伊ベネチアで、水位が極端に低下している。昨年11月、約50年ぶりの高潮で市内の大部分が浸水したベネチア。
それからわずか数カ月―今度はゴンドラを漕ぐこともできないほど、水位が低くなってしまった。
複数の島々からなるベネチアは、常に潮の満ち引きの影響を受けてきた。また海面が極端に上昇したり、逆に極端に下がったりすることもしばしば発生する。
(ロイター)
CO2排出で潮位が上がり続けているのなら、こんなこと起きるわけねえだろ!
「運河の汚染 観光客消え改善」ということは、過度な観光化に因るラグーン(潟)の劣化が、「冬場の高潮の頻度が増え、20年前には数年に1度だった大規模な浸水が、1年に何度も起きるようになった」の主因ということだ。
「いま手を打たなければ街は死んでしまう」って?
遠慮すんな。
今すぐ死ね!
しかも、観光化だけが原因じゃない。
ラグーンに「健全な環境取り戻す」 伊ベネチアの取り組み
2020年10月11日 9:00 発信地:ベネチア/イタリア
 イタリア・ベネチア近くのラグーンで、アシを植える漁業関係者ら(2020年7月22日撮影)。(c)Celine CORNU / AFP
イタリア・ベネチア近くのラグーンで、アシを植える漁業関係者ら(2020年7月22日撮影)。(c)Celine CORNU / AFP
イタリア・ベネチアは観光名所のサン・マルコ広場やため息橋で有名かもしれないが、この都市には見過ごされることの多い魅力がもう一つある。それはラグーン(潟)だ。
かつては多様な魚や鳥が生息していたラグーン内は、人間の干渉によって水の塩分濃度が劇的に上昇した。
これを受け2017年、ラグーンに淡水を引き入れ、かつての栄光を取り戻すことを目指す環境整備計画「ライフ・ラグーン・リフレッシュ」が立ち上げられた。
計画を率いるイタリア環境保護調査高等研究所(ISPRA)の研究者ロッセラ・ボスコロ・ブルサ(Rossella Boscolo Brusa)氏はAFPの取材に、「河川がラグーンを迂回(うかい)するようにしたことが原因で長い間に失われた環境を再構築することが、この計画の狙いだ」と語った。
ブルサ氏によると、河川を迂回させたのは、湿地域を浄化してマラリアに対処することが目的だったという。だが、この活動は思いがけない結果を招いた。
「水の塩分濃度が上昇し、アシの生育数が減少した。アシは保護対象の生物種や商業的利益がある生物種などの非常に貴重な生息環境となる」と、ブルサ氏は指摘した。
伊ベネチア・カフォスカリ大学の専門家、アドリアーノ・スフリーソ(Adriano Sfriso)氏によると、かつてラグーンの半分以上はアシが生い茂る塩性湿地だった。その面積は約1万7000ヘクタールに及んでいたが、現在では、わずか34ヘクタールしか残っていないという。
■淡水引き入れアシ再生
アシはある程度の塩分に耐える性質がある。だが、ラグーン内部の水は塩分尺度で0~15の範囲内のはずが現在は30で、海水に近い値となっている。
「ライフ・ラグーン・リフレッシュ」計画では、シーレ川の淡水の流路を変えてラグーンに流入させている。5月から運用されているこの人工水路は、計画での必要性や潮の満ち引きに応じて水の流量を調節することができる。
また、ココナツ繊維でできた生分解性の障壁が、対象エリア内に淡水を封じ込め、アシが生育する助けとなる。
計画では全体で約20ヘクタールのアシの再生を目指すと、スフリーソ氏は話した。
■「命であり世界」
「ラグーンはわれわれの命であり、世界だ」と話すのは、アマチュアの漁師と猟師で構成される環境保護団体の代表を務めるマッシモ・パラビッチーニ(Massimo Parravicini)氏(58)だ。
「ラグーンを保護すれば、その恩恵を最大限享受でき、子孫に伝えることができる」と語るパラビッチーニさんは、今回の計画で定期的にボランティア活動を行っており、この計画のことを「生態系にとって不可欠」と表現している。
計画の成果は、フランスのイエール、スペインのアルブフェーラ、ギリシャのネストス・デルタとポルト・ラゴスなど、同様の問題を抱える地域で共有される。
(AFP/Celine CORNU)
潟自体が防波堤になっているだけでなく、潟に生えているアシが高潮を防いでる。
「河川を迂回させ」て、「水の塩分濃度が上昇し、アシの生育数が減少した」ことが、「冬場の高潮の頻度が増え、20年前には数年に1度だった大規模な浸水が、1年に何度も起きるようになった」の一因。
にもかかわらず、第3面でも破廉恥なイタリア野郎に泣き喚かせてやがった!
昨年5月6日の投稿、5月13日の投稿、5月17日の投稿、6月10日の投稿、6月17日の投稿、7月18日の投稿、7月19日の投稿、9月1日の投稿、9月19日の投稿、9月27日の投稿、10月29日の投稿、そして、11月25日の投稿で紹介したとおり、グリーンリカバリーと喚き続けてきやがったけど、「温暖化の影響で(潮位が上がり続けて)冬場の高潮の頻度が増え、20年前には数年に1度だった大規模な浸水が、1年に何度も起きるようになった」と思い込ませ、グリーンリカバリーが必要と言い張るために、「このパンデミックは、気候変動対策や地球の持続可能性といった問題の重大性について、改めて私たちに気づかせました」と喚かせてやがるんだよ。
だから、第2面を割いてコレ!
「インド北部のジャムで、全国的な都市封鎖によって大気汚染が解消したため、街中から望めるようになった山脈」という写真を掲載してるのは、昨年6月10日の投稿で採り上げた昨年6月8日の朝刊紙面と同じですな。
だから、「ホッケー・スティック曲線の虚実」で解説しているにもかかわらず、昨年1月16日の投稿と8月6日の投稿で糾弾したにもかかわらず、そして、コチラとコチラとコチラとコチラでも解説しているにもかかわらず、最上段にデカデカとホッケー・スティック曲線。
(IPCCの気候モデルはホッケー・スティック曲線に依存してるから、当然ではあるけれど。)
昨年12月9日の投稿で糾弾したにもかかわらず、ハイエイタスも消去。
(「IPCC第5次報告書の市民向け要約」の第4節で解説しているとおり、ハイエイタスはホッケー・スティック曲線の虚構を示してるから、それも当然ではあるけれど。)
昨年12月20日の投稿で指摘したとおり、西暦1000年前後は2000年と同じほど温暖だったから、1200年以降だけを表示。
しかも、だ。
「温暖化の影響で(潮位が上がり続けて)冬場の高潮の頻度が増え、20年前には数年に1度だった大規模な浸水が、1年に何度も起きるようになった」と泣き喚いてやがるけど、西暦1200年以前の地中海(の海水温)は2000年より暖かかった。

図1 「Scientific Reports,10(2020)10431」の図2より
前回の投稿で採り上げた大晦日の邪説は「『批判的な意見がたくさんあること』。評論家の加藤周一は民主主義をそう定義する」と泣き喚いてやがったけど、「これを『花森流』民主主義と呼ぶなら」、昨年7月18日の投稿と8月21日の投稿で糾弾したにもかかわらず、尚も「同年6月には・・・8万年に1回未満しか起こらない現象が現実のものとなった」と喚き立て、「人間の活動 気候を左右」と言い張り、「コロナ禍は地球環境への人類の影響の大きさを改めて示した。二酸化炭素の排出をゼロにするなどのドラスティックな変化を、今すぐ始めなければならない。間に合うかどうか、時間との闘いだ」と泣き喚く「『左翼・温暖化信者流』民主主義とは似ても似つかぬ」!
だから、やはり元旦から、こんな連載を始めやがった!
電気代は月200円 5アンペアで暮らす僕が結婚したら
斎藤健一郎
2021年1月1日 10時00分
東日本大震災を福島赴任中に経験し、原子力発電所の事故で多くの人の家や土地が奪われる姿を間近で見た記者は、2012年に節電の道を歩み始めました。電力会社との契約を5アンペアに下げ、1カ月の電気代は200円弱。電力会社の電気をほとんど使わないで暮らせるようになりました。その後、結婚し、子どもが生まれたことで節電生活は見直しを迫られましたが、元の電気じゃぶじゃぶ生活に戻るつもりはありません。目指すのは「自然エネルギー100%」の暮らしです。
電気に極力頼らず暮らしたい――。
突き上げるような衝動に従って、節電の道に分け入ったあの夏から8年余が過ぎた。
あの夏……。東日本大震災で東京電力の原発が史上最悪レベルの事故を起こした日から1年余、政府が原発の再稼働を決めた2012年の夏である。
僕は福島の郡山支局員だった時に原発事故に遭った。住んでいた家が地震で半壊になったこと以上に心を細らせたのは、原発災害だった。日々放射性物質が拡散されている原発を誰も止めることができない。その事実を突きつけられたショックは大きかった。たくさんの人が土地と家を奪われるのを間近で取材しながら、自分自身も放射能という見えない敵におびえ、住む場所を転々として暮らした。
多くの人の安寧な日々を奪い、人類で誰ひとり完璧にコントロールをできる人がいないとわかってしまった原発が、「人々の暮らしを守る」という名目で再び稼働することに決まったのは12年6月。あんなつらい経験は二度としたくない。誰にも経験させてはいけない、そのためになにができるかと真剣に考えた。
その結果が節電だった。国会周囲で原発再稼働に反対するデモが毎夜繰り返されていたが、原発停止の鍵を握るのは国会ではなく、僕たち一人ひとりの暮らしにある。電気を使わないでも暮らせるかどうかに挑んでみたいと思った。経験もなければ、成算もない。とにかくやってみよう。福島から東京に異動になっていた僕は相変わらず独身で、無鉄砲はいくらでも許された。迷いはなかった。
はじまりは、アンペアダウンから。東京電力との契約アンペア(A)をそれまでの40Aから最小の5Aに下げた。これで500ワットを超える家電は使えなくなる。甘えが出ないように、物理的に退路を断ってみたのだ。完全ゼロにしなかったのは、現代社会とのつながりまでゼロにするわけにはいかないから。仕事し、生きていく以上、パソコンや携帯電話は使い続けなければならない。
電子レンジ、トースター、電気炊飯器、エアコンを次々と手放した。その試みを「5アンペア生活」と題して新聞の生活面で書くと、想像を超えた反響が届いた。原発事故後に電力が不足し、誰もが節電意識を強く胸に刻んでいた頃、寄せられる反響のほとんどは賛否の「賛」のほうだった。
本気になった。一時の実験にはしたくない。節電の苦しみや忍耐を喜びに変え、しゃにむに節電道を突き進む。次から次へとアイデアが浮かび、浮かんだ端から試していった。
便利な暮らしにひたりきった私たちがもし、家電を次々と手放したら、どんな生活が待っているのか。原発事故をきっかけに5アンペア生活に踏み出した記者、8年余の記録を連載します。連載初回は節電生活の始まりをつづります。
それまで月4千円ほどだった電…
(朝日新聞デジタル)
前回の投稿で採り上げた昨年12月28日の邪説は「たとえば、再生可能エネルギーについて『最大限の導入をはかる』と強調しながら、『電力の100%をまかなうのは困難だ』とし、目安として『50~60%』をあげた。これは欧州の主要国が30年にめざしている水準に過ぎない」と泣き喚いてやがったけど、現在の消費電力を100%再生可能エネルギーで賄えるのなら、なぜ「電気に極力頼らず暮らしたい――」と喚く必要がある?
あ?
「原発停止の鍵を握るのは国会ではなく、僕たち一人ひとりの暮らしにある。電気を使わないでも暮らせるかどうかに挑んでみたいと思った」ということは、原発が無ければ電気は足りなくなるということだろ。
「電気代は月200円」、「元の電気じゃぶじゃぶ生活に戻るつもりはありません。目指すのは『自然エネルギー100%』の暮らしです」ということは、自然エネルギーでは現在の消費電力の10分の1も賄えないということだろ。
にもかかわらず、前回の投稿で採り上げた昨年12月28日の邪説は「炭素税や排出量取引のようなカーボンプライシングにも取り組む……。示された方針や方策には、うなずける点も多い」と歓んだ。
消費電力の10分の1も賄えないのに、「研究開発が進む洋上風力発電。温室効果ガス排出の実質ゼロに向けて後押しする事業が来年度の当初予算案に盛り込まれた」と歓んだ。
消費電力の10分の1も賄えないのに、昨年10月26日の投稿で採り上げた昨年10月23日の邪説は「送電網の使い方の工夫や、蓄電池など電気をためる技術の革新に目を配ることが欠かせない」と喚き立て、11月1日の投稿で紹介したとおり、「再生エネ普及へ地域間送電網を複線化」。
実際には、基幹送電線にほとんど流れない(から、消費電力の10分の1も賄えない)再エネ(と称する紛い物)を消費電力の何十倍も、それも高値で売りつけ、「ぼくらの暮しを」を破綻させ、「ぼくら」を苦しめ殺して、利を貪るために、「コロナ禍は地球環境への人類の影響の大きさを改めて示した。二酸化炭素の排出をゼロにするなどのドラスティックな変化を、今すぐ始めなければならない。間に合うかどうか、時間との闘いだ」と泣き喚いていることは明らかだろ。
しかも、ほんの少し前は「パソコンや携帯電話」は無かった。
それでも、生活に大きな不足は無かった。
にもかかわらず、「生きていく以上、パソコンや携帯電話は使い続けなければならない」と泣き喚き、「電子レンジ、トースター、電気炊飯器、エアコンを次々と手放した」と言い立て、「便利な暮らしにひたりきった私たち」罵るのは、「ぼくらの暮しを」を破綻させ、「ぼくら」を苦しめ殺して、利を貪るために、「コロナ禍は地球環境への人類の影響の大きさを改めて示した。二酸化炭素の排出をゼロにするなどのドラスティックな変化を、今すぐ始めなければならない。間に合うかどうか、時間との闘いだ」と喚き立てていることを、ハッキリと示してるな。
だから、元旦に、さらにこんな記事。
縮む氷河、私のせい? 元ミステリーハンターは決心した
鈴木友里子
2021年1月1日 8時00分
普段、必要な何かを買う時、少しの思いやりで地球温暖化や児童労働などの問題解決に貢献する方法がある――。世界80カ国を旅した元「ミステリーハンター」の末吉里花さん(44)は、エシカル協会の代表理事として「エシカル(倫理的な)消費」を提唱しています。エシカル消費とは何なのか? どう始めればいいのか? 末吉さんにお話を聞きました。

エシカル協会代表理事・末吉里花さん=一般社団法人エシカル協会提供
――エシカルとは?
エシカルは英語で「倫理的な」という意味です。かみ砕くと「人や地球環境、社会や地域に配慮した考え方や行動」を取ることです。覚えやすく「影響をしっかりと考える」(頭文字をとるとエシカル)と理解していただくのもいいと思います。
キリマンジャロで受けた衝撃
――末吉さんがエシカル消費に興味を持ったきっかけは?
私はもともとフリーアナウンサーとして、TBS系の番組「世界ふしぎ発見!」でミステリーハンターをしていたので、プライベートを含めて世界80カ国くらい旅をしました。各国の秘境と呼ばれる地域を巡る中で、ある共通点を見つけました。それは、「一握りの権力や利益のために美しい自然や弱い立場の人が犠牲になっている」という構造でした。
頭では理解できているつもりで…
(朝日新聞デジタル)
CO2を排出して利を貪ったのは最上位1%の富裕層だから、「縮む氷河」はCO2排出が原因なら、「縮む氷河、富裕層のせい」。
それを「私のせい?」と喚き立てるのは、最上位1%が己らの排出したCO2を利用して、「便利な暮らしにひたりきった私たち99%が悪い」と思い込ませ、99%からの収奪を強めて利を貪るために、「コロナ禍は地球環境への人類の影響の大きさを改めて示した。二酸化炭素の排出をゼロにするなどのドラスティックな変化を、今すぐ始めなければならない。間に合うかどうか、時間との闘いだ」と喚き立てていることを、ハッキリと、ハッキリと示してるな。
だから、初めの紙面のネット版の見出しはこうなってる。
ベネチアの水が透明に コロナ禍に浮き出た人間の身勝手
ベネチア=河原田慎一 奈良部健、北京=高田正幸 水戸部六美、阿部朋美 合田禄、石井徹
2021年1月3日 8時00分
係留されたゴンドラが、流れにもてあそばれるように激しく揺れ始めた。運河から水があふれ出し、ひたひたと迫ってくる。石畳の広場はあっという間に水に覆われ、市民らが渡し板の上を足早に行き交う。12月1日、イタリアの「水の都」ではこの日も例年の光景が繰り返された。
世界的な観光地ベネチア。世界遺産のこの街が近年、相次ぐ高潮の被害に見舞われている。地球規模の温暖化の影響で冬場の高潮の頻度が増え、20年前には数年に1度だった大規模な浸水が、1年に何度も起きるようになった。
 高潮で水に覆われたイタリア・ベネチアのサンマルコ広場。コロナ禍で観光客が激減し、マスク姿のカップルが広場を独占していた=2020年12月4日、ステファノ・ダルポッツォロ氏撮影
高潮で水に覆われたイタリア・ベネチアのサンマルコ広場。コロナ禍で観光客が激減し、マスク姿のカップルが広場を独占していた=2020年12月4日、ステファノ・ダルポッツォロ氏撮影
家や店の入り口に防潮板を立てても水が入り込み、大理石でできた歴史的建造物が塩害で内部から崩れていく。40年前に約10万人だった旧市街の人口は、約5万人にまで減った。
「自然環境を壊さずに、未来にどうベネチアを残すか。いま手を打たなければ街は死んでしまう」。ルイジ・ブルニャーロ市長(59)は危機感を強める。
高潮被害だけではない。年に1…
(朝日新聞デジタル)
「人間の身勝手」と言い立て、99%の責に帰そうと図るのは、「便利な暮らしにひたりきった私たち99%が悪い」と思い込ませ、99%からの収奪を強めて利を貪るために、「コロナ禍は地球環境への人類の影響の大きさを改めて示した。二酸化炭素の排出をゼロにするなどのドラスティックな変化を、今すぐ始めなければならない。間に合うかどうか、時間との闘いだ」と喚き立てていることを、ハッキリと、ハッキリと、ハッキリと示してるな。
「共生のSDGs」と言い立てるのも全く同じ意図。
実は、99%に搾取を「強制のSDGs」。
昨年6月1日の投稿で紹介したとおり、わざわざグレた娘を盾にして、「私たちは大量絶滅の入り口にいる――。地球温暖化問題に取り組む少女グレタさんは国連でそう言った」「人類を含む現代の生物が大量絶滅したら、6600万年ぶり6回目となりそうだ」だの、昨年6月10日の投稿で紹介したとおり、「トゥンベリは、畜産は気候変動の一つの主要な要因であり、その気候変動は(人間が原因で地球上の生物を絶滅させる)『第6の絶滅』に帰着すると語る。早急に生活習慣を変えなければ、ハルマゲドンはそこまできていると呼びかける」と喚き立ててやがったけど、第2面で「地球は『第6の絶滅時代』に入ったと警告する科学者たちもいる。・・・『人の祖先は省エネだったので生き残れた。人間が恐竜と同じ状況に陥る可能性は十分にある』と警報を鳴らす」のは、昨年12月18日の投稿で指摘したとおり、お前ら99%は清く貧しく細く短く生きろと言うことに他ならず、そのためにグレた娘を担ぎ出してきて、「気候危機」と煽り立ててるんだね。
だから、同じ元旦の邪説でコレ!
核・気候・コロナ 文明への問いの波頭に立つ
長崎原爆資料館の入り口に、「長崎からのメッセージ」が掲げられたのは昨年4月10日のことだった。被爆から75年の節目、核廃絶に向けたステップの年に、との意気込みにもかかわらず、館はこの日からコロナ対策で臨時休館となった。
メッセージは、核兵器、環境問題、新型コロナという「世界規模の問題」を三つ挙げ、それらに「立ち向かう時に必要なこと その根っこは、同じだと思います」と語りかける。
すなわち「自分が当事者だと自覚すること。人を思いやること。結末を想像すること。そして行動に移すこと」。
誰もがウイルスに襲われうることを人々は知った。感染や、その拡大という「結末」を想像し、一人ひとりが行動を律する必要も、人々は知った。
そんな時期に、核や地球温暖化でも、誰もが「当事者」であり、みんなの「行動」が求められていることを訴えたい。休館を前にした市職員らの思いが、メッセージには込められた。
資料館は6月に再開、メッセージは年を越し、いまも玄関に掲げられている。
■牙をむく巨大リスク
パンデミックが世界を覆い尽くす速度は昔日の比ではない。
地球環境は「気候危機」に立ち至った。
核の恐怖を伝える「終末時計」は昨年、人類滅亡まで「残り100秒」を指し、史上最悪を記録した。
いずれも、現代文明が産み落としたグローバルな巨大リスクである。
3・11の東日本大震災と福島原発事故の3カ月半後、政府の復興構想会議が出した提言の一節が思い出される。
「われわれの文明の性格そのものが問われているのではないか」
人類に豊かさをもたらしたはずの文明が、人類に牙をむく。この逆説を、改めて深く銘記せざるをえない。
コロナ禍という非常時は、以前からあった数々の問題を大写しにした。生態系への野放図な介入しかり、都市への人口密集しかり、である。
効率優先の行き着くところ、社会の余力がそぎ落とされ、医療崩壊につながった地域がある。看護、介護、物流といった日常を支える「エッセンシャルワーカー」の役割に光が当たったが、テレワークが広がり、デジタル化が加速する見通しの一方で、対面労働に携わる人々との格差が論点となる。
これらの課題にどう答えを出すか。感染の抑え込みに加え、人類社会が課される荷は重い。
■世界は覚醒できるか
興味深いことに、コロナ禍で傷んだ経済の再生を、脱炭素や生態系の保全といった気候変動への取り組みと連動させようという機運が生じている。「グリーンリカバリー(緑の復興)」である。
「経済を回す」ことを単に取り戻すのではなく、環境に目配りし、次代の人類社会の姿を描きつつ、二兎(にと)を追う。
命か、経済か。時に口の端にのぼった二分法からの、発想の転換といっていい。
この分野では今年、国際社会が様変わりを見せる。バイデン政権が発足する米国は、温室効果ガスの排出削減をめざす枠組み「パリ協定」に復帰する。
日本政府も昨年10月、「2050年に実質排出ゼロ」を打ち出した。世界的な潮流に押され、やはり「発想の転換」(菅首相)に踏み切った。
「終末時計」の針を後戻りさせることは可能だろうか。
今月22日に核兵器禁止条約が発効する。核兵器は非人道的で違法だとする国際規範であり、「核なき世界」への大きな一歩である。
広島、長崎の被爆者に加え、国際的な非政府組織に集う世界の市民が運動を繰り広げ、有志国の政府との連帯を通じてこぎつけた。
米ロはじめ核保有国と、「核の傘」の下にある日本などは、この条約に背を向ける。「恐怖の均衡」による核抑止論から抜け出せていない。世界はなお、偶発的な核惨事が発生する危険と隣り合わせである。
こんなことをいつまでも続けていていいのか――。危機への覚醒いかんが、時計の針を進めもすれば遅らせもする。
■未来の当事者が動く
10年前の原発事故後、思想史家の渡辺京二氏は短い文章を書いた。「人類の生きかた在りかたを変えねばならぬのは、昨日今日始まった話ではないのだ」「つまり、潮時が来ていたのだ」(『未踏の野を過ぎて』)
潮目の変化がはっきりしているのに、頑として動かない山もある。それでも2021年は、山を動かす挑戦をより一層進める好機である。
環境活動家のグレタ・トゥンベリさんをはじめ、様々な領域で若い世代が声を上げていることは心強い。未来社会の当事者たちが、このままで人類は持続可能なのかという問いの波頭に立っている。
はい!
邪説の最後でグレた娘を持て囃してます。
「何度言っても言い足りない」けれど、CO2を排出して利を貪ったのは最上位1%の富裕層。
2015年4月28日の投稿で指摘したとおり、平均年収1300万のコヤツらも最上位1%の富裕層。
(「電気代は月200円」が醜悪で卑劣なプロパガンダにすぎないことは明らかだろ。)
「これを『花森流』民主主義と呼ぶなら」、「誰もが『当事者』であり、みんなの『行動』が求められていることを訴えたい」と泣き喚く「『左翼・温暖化信者流』民主主義とは似ても似つかぬ」!
「地球環境は『気候危機』に立ち至った」と泣き喚き、「興味深いことに、コロナ禍で傷んだ経済の再生を、脱炭素や生態系の保全といった気候変動への取り組みと連動させようという機運が生じている。『グリーンリカバリー(緑の復興)』である」と言い立てて、己ら富裕層の排出したCO2を逆手に取り、「便利な暮らしにひたりきった私たち99%が悪い」と思い込ませ、「ぼくらの暮し」を破綻させ、「ぼくら」を苦しめ殺して利を貪るために、「誰もが『当事者』であり、みんなの『行動』が求められていることを訴えたい」んだね。
「グリーンリカバリー(緑の復興)」と言い立てて、「最上位1%の富裕層に豊かさをもたらしたはずの文明が、99%の人類に牙をむく。この真実を、改めて深く銘記せざるをえない」。
「これを『花森流』民主主義と呼ぶなら」、「人類に豊かさをもたらしたはずの文明が、人類に牙をむく。この逆説を、改めて深く銘記せざるをえない」と泣き喚く「『左翼・温暖化信者流』民主主義とは似ても似つかぬ」!
昨年5月6日の投稿で「新型コロナウイルスからの経済復興計画が格差解消に沿うものでなければならない」と、5月13日の投稿でも「経済や社会を立て直す際、忘れてならないことがほかにもある。単に元通りに戻すことだけを考えていると、格差拡大の回避が難しくなるという点だ」と、そして、5月17日の投稿でも「『未知の感染症との出会いや急速な拡大も、この経済社会システムの延長線上にあると見られている』ということは、深刻な格差を生み出した経済社会システムの問題、ということ」と言ったけれど、「『経済を回す』ことを単に取り戻すのではなく、格差に目配りし、次代の人類社会の姿を描きつつ、最上位1%の富裕層を追い払う」ことこそが、「民主々義の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」。
「これを『花森流』民主主義と呼ぶなら」、「『経済を回す』ことを単に取り戻すのではなく、環境に目配りし、次代の人類社会の姿を描きつつ、二兎(にと)を追う」と言い張る「『左翼・温暖化信者流』民主主義とは似ても似つかぬ」!
「経済」とは、すなわち、経世済民
「経世済民の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」。
「二兎」ではない。
「二兎を追う。命か、経済か。時に口の端にのぼった二分法からの、発想の転換といっていい」とは、すなわち、「99%の経済か、1%の経済か。時に口の端にのぼった二分法からの、発想の転換といっていい」に他ならない。
前回の投稿で、「これを『花森流』民主主義と呼ぶなら、『安倍・菅流』民主主義とは似ても似つかぬ」のなら、そんな政権が「2050年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにするため、政府が『グリーン成長戦略』をまとめた」のは、「民主々義の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」に反するはず、と糾弾したにもかかわらず、「日本政府も昨年10月、『2050年に実質排出ゼロ』を打ち出した。世界的な潮流に押され、やはり『発想の転換』(菅首相)に踏み切った」と囃し立てるのは、その事実をハッキリと示してるな。
グレた娘は「民主々義の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」を打ち砕く「波頭に立っている」んだよ。
だから、こんなことまで記事にしやがる!
グレタさん18歳の成人に 「今晩はパブで秘密を暴露」
半田尚子
2021年1月4日 18時48分
 グレタ・トゥンベリさんが誕生日のメッセージで投稿した自身の写真。ツイッターから=ロイター
グレタ・トゥンベリさんが誕生日のメッセージで投稿した自身の写真。ツイッターから=ロイター
3日に18歳の誕生日を迎えたスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥンベリさんが同日、自身のツイッターに「私はついに自由だ!」と投稿した。同国の成人年齢は18歳。親指を立てたグレタさん自身の写真が添えられたメッセージには、世界中から祝福の言葉が寄せられ、投稿から17時間余りで『いいね』は18万3千件以上に達した。
『地球のために立ち上がってくれてありがとう』『これからも闘い続けて!』『世界中があなたを誇りに思っているよ』――。グレタさんのツイッターには、子どもから大人まで誕生日を祝福する幅広い世代の言葉が投稿された。ウガンダの女性は18本の木を植えて祝福し、「グレタは私の活動のエネルギーの源です」と投稿した。
スウェーデンでは18歳になると、飲食店での飲酒が認められる。グレタさんは誕生日の夜の過ごし方について、ツイッターに「今晩は地元のパブで、気候(問題)の秘密、学校ストライキの陰謀、私をもうこれ以上は支配できない悪の手先たちについて全て暴露する」とも書き込んだ。
誕生日に先立ち、英紙サンデー…
(朝日新聞デジタル)
「何度言っても言い足りない」けれど、黄色いベスト運動は「民主々義の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」と訴えた。
ところが、2019年2月28日の投稿で紹介したとおり、ダボスに招かれたグレた娘が「殺(や)るか、殺(や)らないか」と喚き立てた翌日に、「真黒ん」が武力行使し、2019年12月1日の投稿で紹介したとおり、多くの〈民〉が傷けられ、果ては、祖国を追われた。
にもかかわらず、2019年8月2日の投稿で紹介したとおり、その功績(?)を賞されてニンマリしてた。
2019年11月8日の投稿で紹介したとおり、チリでも「民主々義の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」と訴えたけれど、グレた娘は顧みずに「助けが必要」「SOS」と泣き喚き、2019年12月1日の投稿と昨年元旦の投稿で紹介したとおり、やはり多くの〈民〉が傷つけられた。
グレた娘は「民主々義の〈民〉は 庶民の民だ ぼくらの暮しを なによりも第一にするということだ」を粉々に打ち砕く「波頭に立っている」んだよ。
だからこそ、邪説の最後で「環境活動家のグレタ・トゥンベリさんをはじめ、様々な領域で若い世代が声を上げていることは心強い」と歓び勇み、こんな記事まで書きやがるんだね。

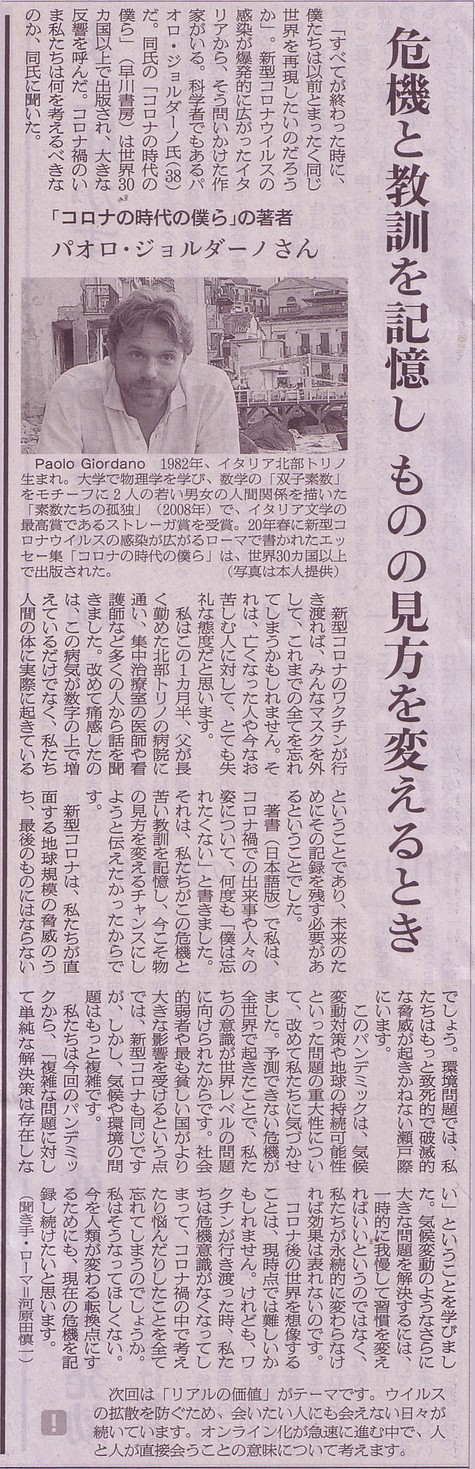





最近のコメント